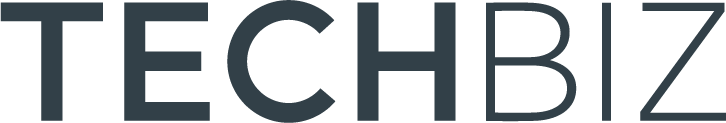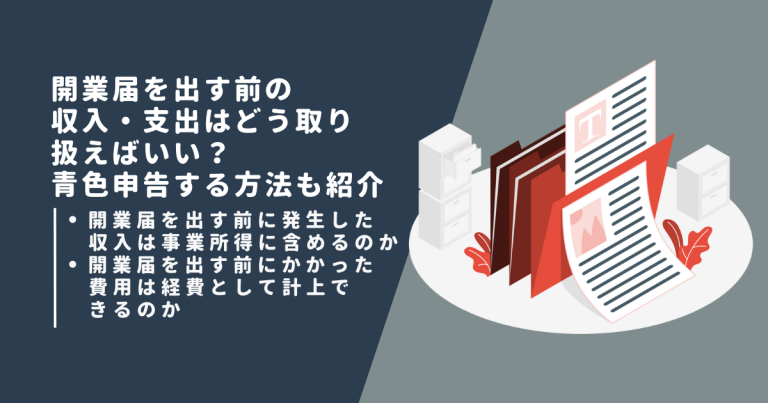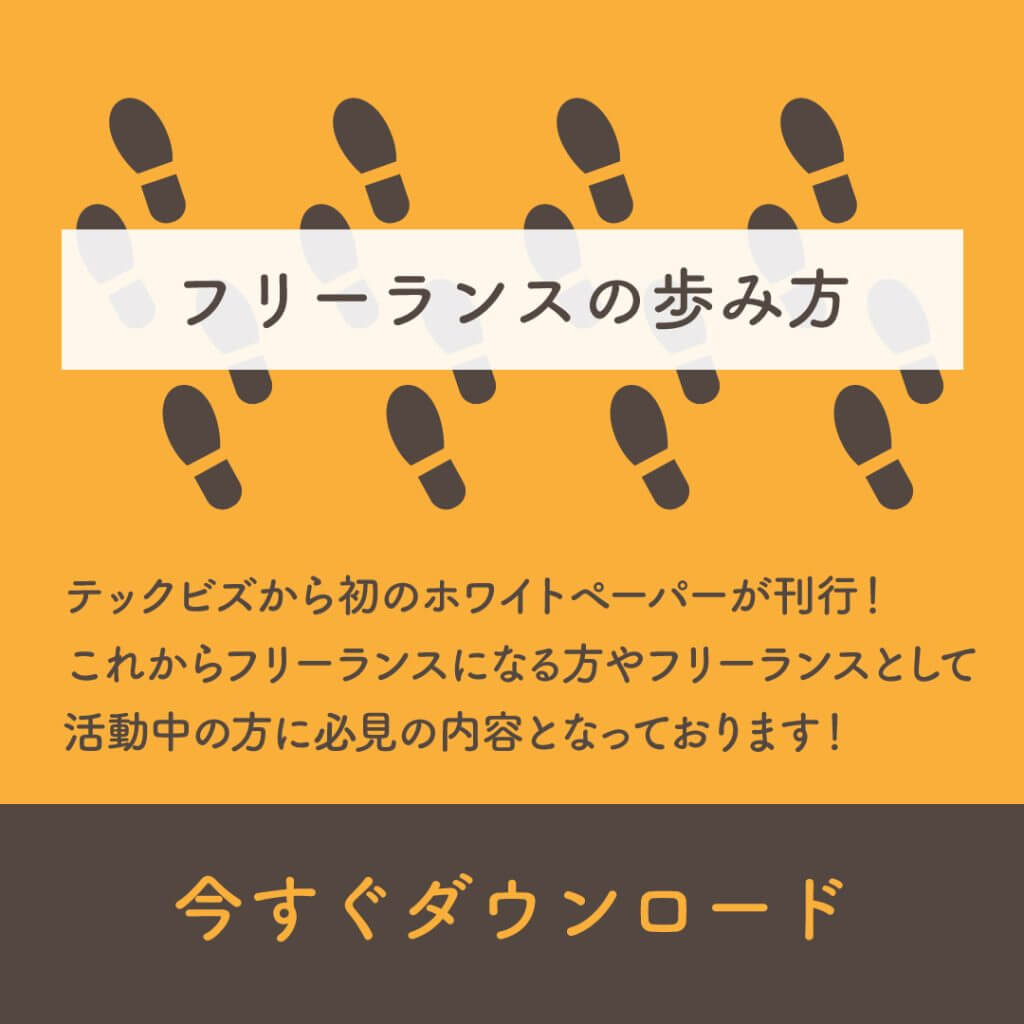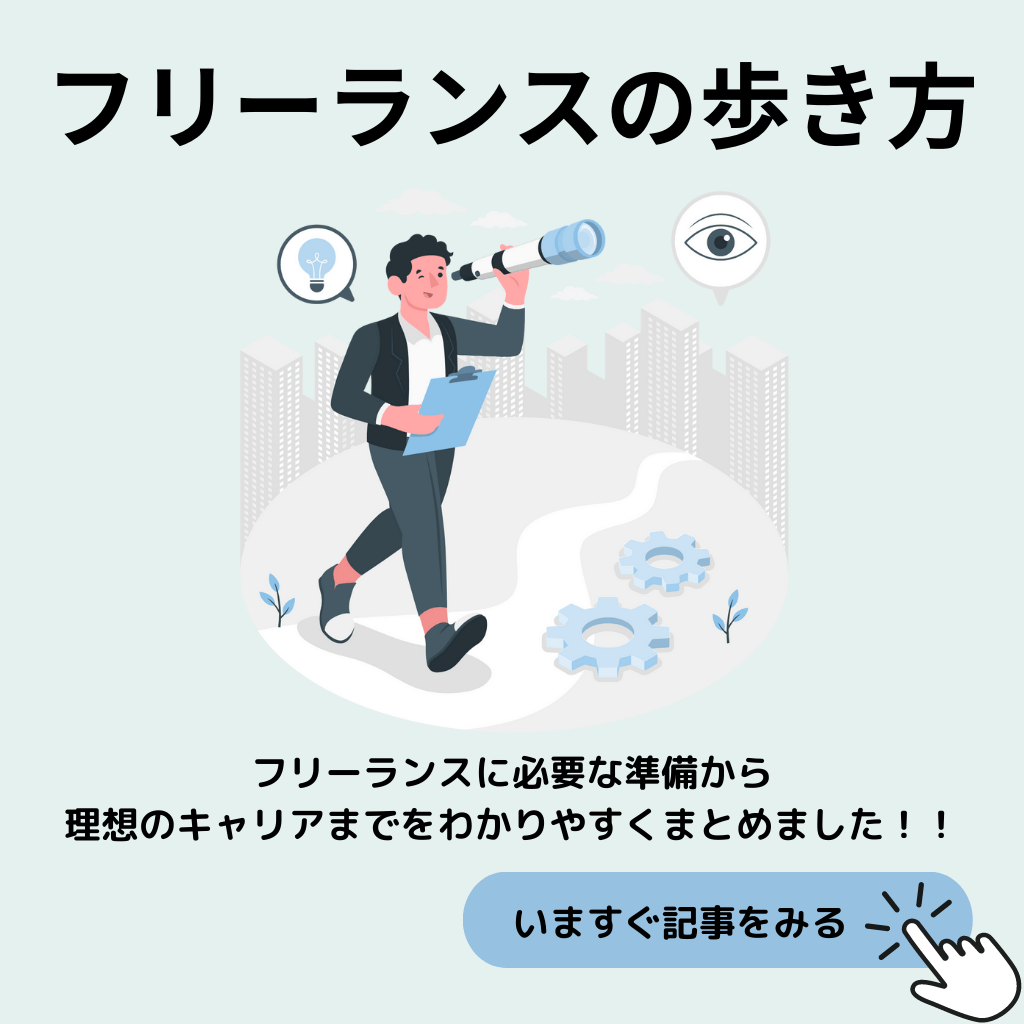・おすすめの領収書の整理方法
・領収書を整理すると確定申告がスムーズになる
・領収書の整理の注意点
確定申告のための領収書整理に頭を悩ませ、時間短縮の方法を探しているフリーランスの方々も多いのではないでしょうか。確定申告に多くの時間を費やすと、本業に専念する時間が減少し、ビジネスに影響を及ぼす可能性があります。そこで今回は、確定申告のプロセスをスムーズに進めるための領収書の整理方法をご紹介します。また、会計ソフトの効果的な活用方法についても説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
領収書を整理整頓しておくと確定申告は楽になる
領収書を適切に整理しておくことで、確定申告の作業が格段に楽になります。例えば、青色申告を行う際には、財務諸表の作成が必要となります。その作成にあたっては、領収書の内容を参照しながら仕訳を作成することが一般的です。しかし、領収書が整理されていないと、必要な領収書を探すのに時間がかかり、仕訳作成に無駄な時間を消費してしまいます。一方で、領収書が整理されていれば、必要な書類をすぐに見つけることができ、作業がスムーズに進みます。さらに、作業終了後に財務諸表と領収書の内容を比較確認する際も、整理された領収書は探しやすく、作業の効率化に寄与します。以上のことから、確定申告をスムーズに進めるためには、領収書の整理整頓が重要であると言えます。
紙媒体での整理・管理の仕方
領収書の整理・管理の重要性は理解していても、具体的な方法がわからないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一度方法を覚えてしまえば、領収書の整理・管理はそれほど難しくありません。ここでは、紙の領収書の整理・管理方法を3つご紹介します。
封筒で月別に仕訳ける
領収書を月ごとに分けて封筒に入れ、保管する方法があります。その際、封筒に「20〇〇年×月経費」と記載しておくと、中身を見なくても何月分の領収書かが一目でわかります。ただし、支払い月と費用計上月が異なる領収書が存在することに注意が必要です。
例えば、10月1日に搭乗する航空チケットの代金10万円を5月1日に現金で支払ったとします。この場合、領収書は1枚ですが、仕訳は2つ発生します。
5月1日:(借方)前払費用 10万円/(貸方)現金 10万円
10月1日:(借方)旅費交通費 10万円/(貸方)前払費用 10万円
このような場合、5月分と10月分の封筒に同じ領収書が入っていなければ、記帳漏れが起こる可能性があります。しかし、2つの封筒に同じ領収書を入れてしまうと、仕訳作成時に二重で旅費や交通費を計上してしまう恐れがあります。
これを防ぐためには、以下の3つのステップを踏むことが効果的です。
- 領収書をコピーする
- 5月分の封筒には、コピーした領収書に「前払費用として計上(旅費交通費としては計上しない)」と記載して入れる
- 10月分の封筒には、領収書の原本をそのまま入れるこれにより、記帳漏れや旅費交通費の二重計上を防ぐことができます。特に、前払い・前受(前もって代金を受け取る)・未払い・未収(料金を後日回収する)に関する取引では、1回の支払いで2つの仕訳を作成するケースが発生するため、注意が必要です。
勘定科目別に仕分ける
また、勘定科目ごとに領収書を分けて保管する方法もあります。具体的には以下のようなイメージです。
売上原価(仕入)
旅費交通費
外注費
支払利息
水道光熱費
勘定科目ごとに領収書を分けた上で、会計ソフトの「複製機能」を活用すれば、仕訳入力時の作業が軽減されます(ただし、全ての会計ソフトにこの機能があるわけではありません)。複製機能とは、会計ソフト上で同じ内容の仕訳を複製する機能のことです。
以下の3つのステップで操作すると、複製機能を効果的に使うことができます。
- 仕分けを入力した後に、複製ボタンを押す
- 複製ボタンを押すと、同じ内容の仕訳が表示される
- 金額や日付を変えれば、別取引の仕訳が完成
勘定科目別に領収書を分けて、上記のステップを踏むことで、勘定科目を入力する操作が減り、仕訳の作成時間が短縮されます。したがって、会計ソフト上での仕訳作成時間を減らしたい方にとって、この機能は覚えておくと良いでしょう。
ファイルで保管
封筒に入れたり、勘定科目ごとに領収書を分けて保管する方法でも、領収書を紛失することを心配する方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には、ファイルに領収書を保管する方法がおすすめです。ファイルは封筒よりも大きいため、紛失するリスクを減らすことができます。
ファイルに保管する際の手順は以下のとおりです。
- 厚さ約2cmの厚紙でできているファイルを用意し、「20〇〇年経費分の領収書」と表面に記入します。
- ファイルの中に、クリアファイルを複数枚とじます(月別で分ける場合は12枚、勘定科目別で挟む場合は、勘定科目の数に合わせた枚数を用意します)。
- クリアファイルに1枚ずつ見出しを付けます(月別で分ける時は「1月分、2月分」など、勘定科目別で分ける時は「旅費交通費、水道光熱費、通信費」などと付けます)。
- 該当するクリアファイルに領収書を入れます。この方法で領収書を保管すると、紛失する確率が低くなり、対象の領収書を探しやすくなるため、非常に便利です。なお、クリアファイルを安く購入したい方は、100円ショップを利用すると、税別100円で複数枚購入できます(ただし、取り扱っていない店舗もあります)。
領収書を保管する時の注意点
3つの保管方法を紹介しましたが、紙媒体の領収書を保管する際は、いくつかの注意点があります。
ここでは、その注意点を見てみましょう。
領収書の印字面が消えないようにする
領収書の印字面が消えてしまうと、それが経費で使用した証明となる領収書であることを証明することができなくなります。そのため、保管する際には印字面が消えないように注意が必要です。特に、感熱紙を使用した領収書は、光に触れると印字面が消えてしまうことがあります。印字面を内側に折る、封筒やクリアファイルに入れるなどして、印字面が光に触れないように保管しましょう
クリップでまとめて保管する
領収書を複数枚保管する際には、クリップでまとめて保管することをおすすめします。クリップで領収書をまとめると、封筒やクリアファイルから取りだす際に紛失するリスクが減ります。また、領収書を見る際も、クリップでまとめられていると便利です。
一方で、ホッチキスで領収書をまとめる方もいらっしゃいますが、ホッチキスでまとめた場合、領収書を取り外すのが手間になることがあります。また、力加減によっては、領収書を取り外す際に破れてしまう可能性もあります。さらに、ホッチキスの針が指に刺さる危険性もあります。
領収書を保管した後のことを考えると、クリップでまとめて保管する方が良いでしょう。
会計ソフトの機能を使えば確定申告はスムーズに進む
現代では、確定申告を行う際に会計ソフトを活用する方も多いです。しかし、その機能を十分に活用できず、確定申告作業に苦労するケースもあります。ここでは、確定申告をスムーズに進めるために役立つ、会計ソフトの機能について見ていきましょう。
クレジットカード明細との連携
クレジットカード明細との連携とは、クレジットカードでの支払い明細を会計ソフトのデータに自動的に反映させる機能のことを指します。会計ソフト上で連携の設定を行うと、クレジットカードの明細が自動的に会計ソフト上に反映されます。ただし、連携の設定方法や連携可能なクレジットカードの種類は、使用する会計ソフトによって異なるので注意が必要です。
経費品目の自動仕訳
経費品目の自動仕訳とは、会計ソフト上で取り込んだ決済データを自動的に仕訳に変換する機能のことを指します。通常、領収書に記載されている内容を仕訳入力する際には、日付や勘定科目、金額などを手動で入力します。
しかし、自動仕訳機能を使用すると、勘定科目や金額などの一部が自動的に入力され、作業時間を短縮することができます。勘定科目を選ぶ必要がないため、会計に不慣れな人にも便利な機能と言えます。
ただし、自動で入力される項目は使用する会計ソフトによって異なるので、注意が必要です。
口座連携で支払・請求の一元化
口座連携で支払・請求の一元化とは、会計ソフトと口座を連携させて、支払いや請求の仕訳作業を一元化する機能のことを指します。一元化しないパターンと一元化するパターンの違いを例を挙げて説明します。
例えば、クライアントへの請求書100枚分の仕訳を作成する場合を考えてみましょう。
通常パターン(一元化しないパターン)では、請求書の内容を1つずつ会計ソフト上に入力します。つまり、「請求書1の仕訳を作成→請求書2の仕訳を作成…請求書100の仕訳を作成」という流れで作業を行います。これは、仕訳を作成する作業が100回発生することを意味します。
一方、口座連携で支払・請求の一元化したパターンでは、100枚の請求書データを会計ソフト上に一括で取り込むことができ、自動的に記帳が行われます。手入力で仕訳を100回作成する必要がありません。つまり、100個の仕訳を100分かけて記帳していた人が一元化すれば、100分の余裕時間が生まれるということです。
大量の請求書データを記帳している人にとって、この機能は非常に便利であると言えます。
紙媒体と会計ソフトを併用で管理しよう
紙媒体の領収書と会計ソフトを併用することで、確定申告前の準備作業がさらに楽になります。特におすすめなのは、紙媒体の領収書をスキャンし、そのデータを会計ソフト上に反映させる方法です。この機能は、会計ソフトとスキャナソフトを連携させることで利用可能となります。
この方法を活用すれば、手入力で仕訳を作成する手間が大幅に減ります。スキャナーがない場合でも、スマートフォンのカメラ機能を使って領収書をデジタル化できる会計ソフトも存在しますので、ぜひ活用してみてください。
おすすめのクラウド会計ソフト
最近では、クラウド上で利用できる会計ソフトも誕生しています。
ここでは、おすすめのクラウド会計ソフトを3本紹介します。
MF(マネーフォワード)クラウド
MF(マネーフォワード)クラウドは、2012年5月に設立された「株式会社マネーフォワード」が提供する会計ソフトです。設立から間もないにもかかわらず、クラウド会計ソフト業界で名高い企業であり、会計ソフト以外にも10種類以上のクラウドサービスを提供しています。
POSレジや電子マネーの情報を会計ソフトと連携させることができ、AIが会計ソフト上のデータを基に自動的に仕訳を行う機能が付いています。これにより、飲食店や小売店などにとても適しています。
さらに、スマートフォンを使って請求書の内容を読み取り、その場で(スマートフォンの)アプリ上で承認することができます。そのため、外出先でも請求書の承認作業を進めたい方にとって、非常に便利な会計ソフトと言えます。
参考:MFクラウド
freee
freeeは、2012年7月に設立されたfreee株式会社が運営する会計ソフトです。設立から間もないにも関わらず、クラウド会計ソフト業界でその名を知られています。
freeeの特徴は、確定申告書類の作成が非常に簡単であることです。freeeでは、いくつかの質問に回答するだけで確定申告の書類が作成されます。そのため、確定申告に関する知識がない人でも利用しやすいでしょう。
さらに、スマートフォンを使ってレシートの画像を読み取り、経費の自動入力が可能なアプリも提供しています。そのため、会計に詳しくない人にも、freeeはおすすめの会計ソフトと言えます。
参考:freee
やよいの青色申告シリーズ
弥生株式会社は、1978年に創立された企業で、クラウド会計ソフトを提供しています。もともとはパソコンにダウンロードするタイプのソフトを主に取り扱っていましたが、近年ではクラウド製品にも力を入れています。
弥生の特徴は、その親切なサポート制度です。カスタマーセンターの担当者が操作画面を共有しながら説明を行うため、口頭だけでは伝わりにくい内容も理解しやすくなっています(ただし、質問内容によっては口頭のみの回答となる場合もあります)。
ただし、利用するプランによってはサポート制度を利用できない場合もあるので、その点は注意が必要です。
参考:弥生
領収書・請求書は確定申告後より最大7年間保管する
個人事業主の方は、確定申告が完了した後も、領収書や請求書は7年間保管する必要があります(白色申告者の場合は5年間)。また、その他の書類(注文書など)も5年間保管することが義務付けられています。
保管年数について迷う方は、確定申告が終わった後から7年間すべての書類を保管するという方法を採ると良いかもしれません。これならば、ルール違反になる心配はありません。
毎月のこまめな整理で確定申告を乗り越えよう
領収書は毎月定期的に整理することで、確定申告をスムーズに乗り越えることができます。特におすすめの方法は以下の通りです。
まず、領収書用のボックスを用意し、領収書が発生したらそのボックスに入れておきます(当月分と翌月分のボックスをそれぞれ用意します)。
月末になったら、ボックスの中に入っている領収書を勘定科目ごとに分けます。
そして、クリップでその月の領収書をまとめ、ファイルに保管します。
この方法を使えば、領収書が月ごと、かつ勘定科目ごとに整理されているため、記帳をする際も楽になります。
1年間の領収書を一度に整理しようとすると、時間がかなりかかります。そのため、領収書の整理に時間をかけずに済むよう、1カ月ごとに整理することをおすすめします。
ビジネスカードでの明細管理が簡単
個人事業主の方にとって、ビジネスカードを使用して経費を支払うと、明細の管理が楽になります。先ほど述べたように、クレジットカードで支払った明細を会計ソフトのデータに反映させることで、記帳の手間を省くことができます。これにより、確定申告にかける時間を減らし、本業に集中することが可能となります。
しかし、それでも自分で確定申告を行うのが面倒だと感じる方もいるでしょう。そんなフリーランスの方におすすめしたいのが、テックビズゴールドカードです。
このカードの注目点は、「税務サポート」が利用できることです。「税務サポート」とは、記帳や確定申告作業を外部に委託できるサービスのことで、毎月5000円から利用可能です。これにより、費用を抑えつつ確定申告の手間を省くことができます。
さらに、福利厚生が充実していたり、会員向けの融資サービスも提供されているため、様々な面で活用することが可能です。ぜひ、このサービスを利用してみてください。
まとめ
確定申告でフリーランスが楽をするための、領収書の整理術を紹介しました。
今回押さえるべきポイントはこちらです。
✓紙媒体での整理・管理の仕方
①封筒で月別に仕分ける
②勘定科目ごとに仕分ける
③ファイルで保管
✓会計ソフトでの整理・管理の仕方
①クレジットカード明細との連携
②経費費目の自動仕訳
③口座連携で支払・請求の一元化
領収書の整理方法だけでなく、会計ソフトの活用度によっても、確定申告にかかる時間は大きく変わります。確定申告にかかる時間を減らし、本業に専念する時間を増やすことで、ビジネスの成績を向上させる可能性があります。
フリーランスとして活動を続けるためにも、確定申告を効率的に行うことを意識してみてください。これにより、ビジネスの運営により集中することができ、より良い結果を得ることができるでしょう。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /