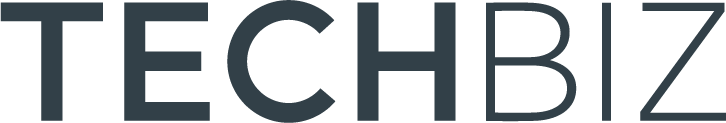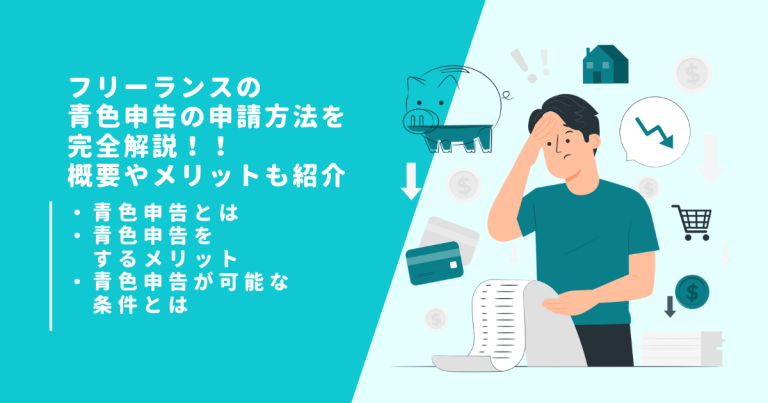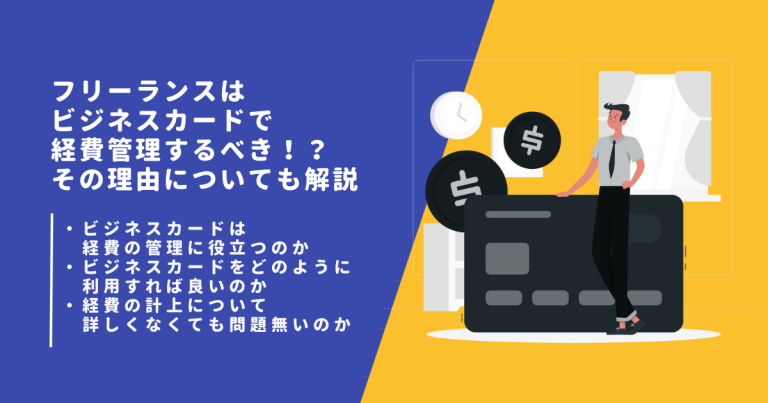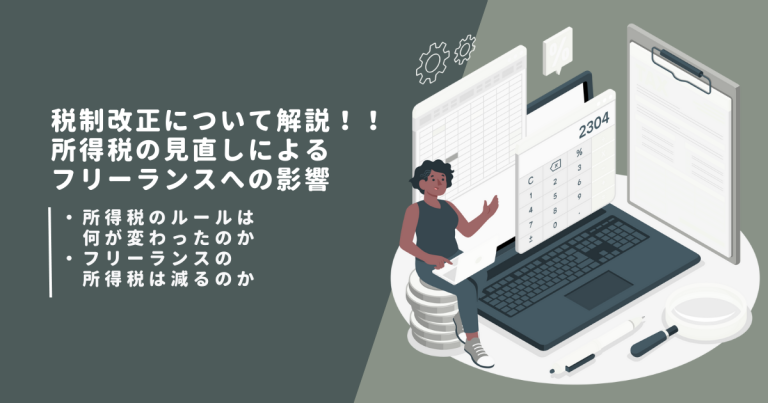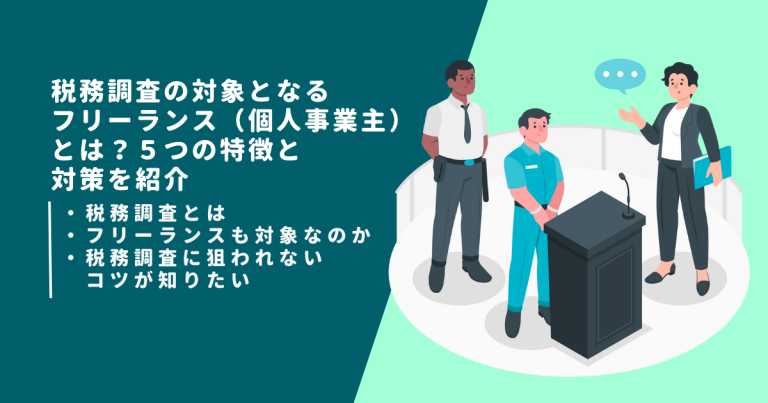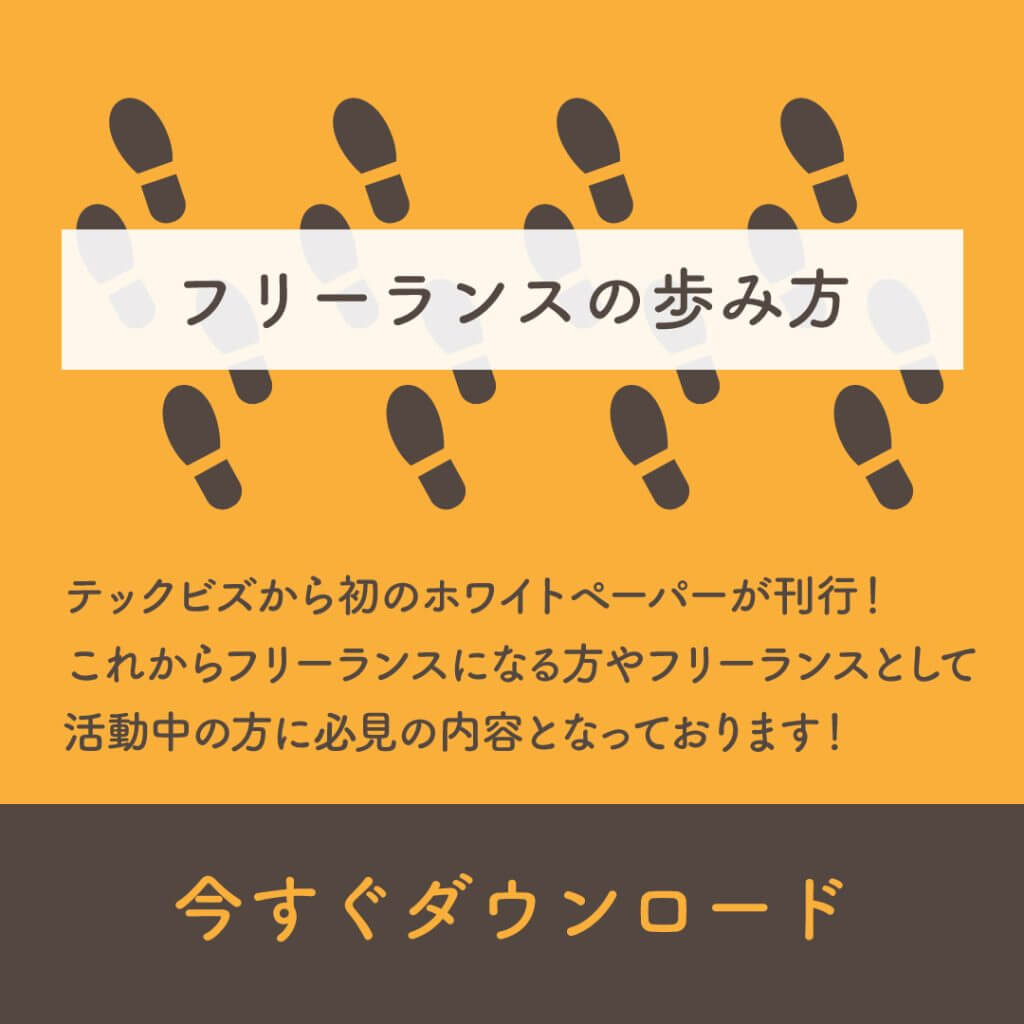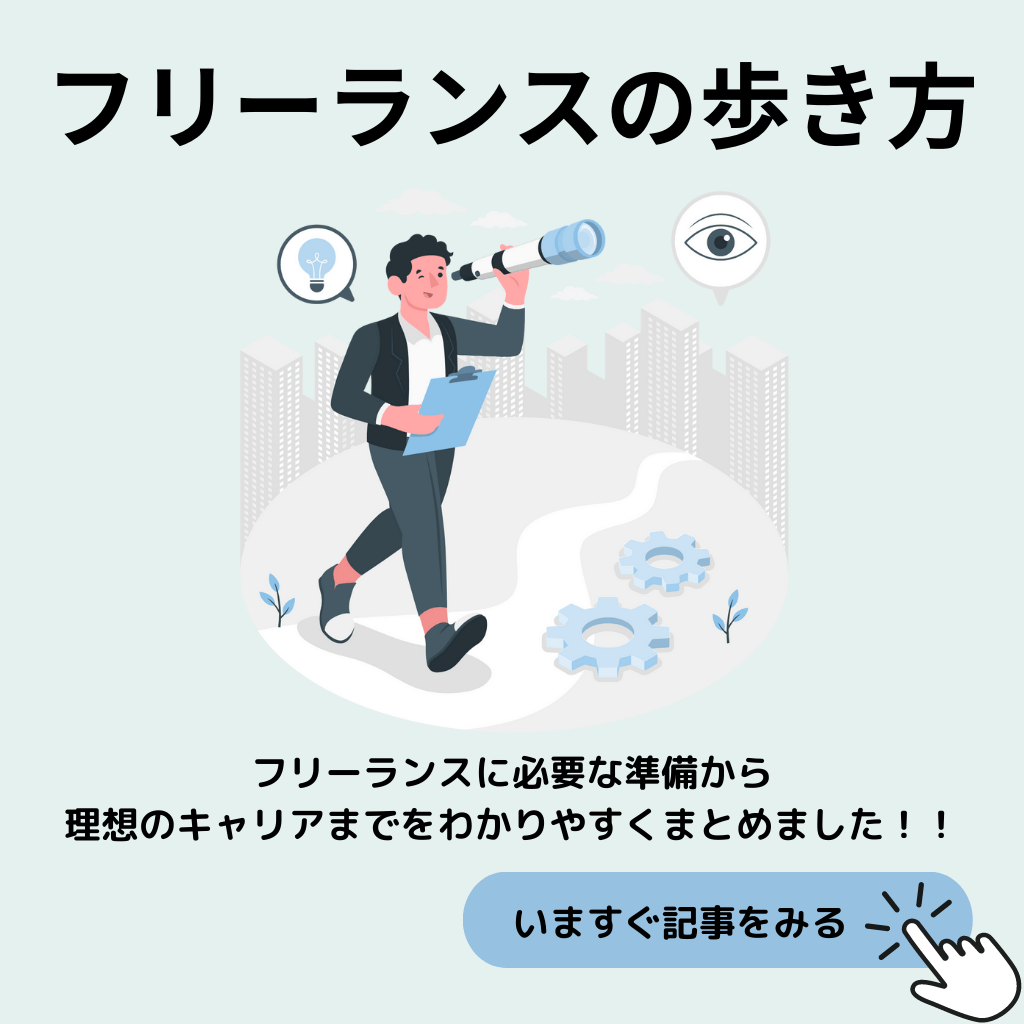・青色申告とは
・青色申告をするメリット
・青色申告が可能な条件とは
以上述べた通り、青色申告について困惑している方もいらっしゃるでしょう。フリーランスとして活動を始めたために青色申告を活用しようと考えている方もいるかもしれません。しかし、一定の条件を満たさなければ利用は許可されません。だからこそ、青色申告を使用する際には、そのルールを理解することが大切となります。しかし、専門的な用語が多くて自分で理解しようと試みたが断念した方もいるでしょう。そこで、今回の記事では、青色申告の詳細や利点などを、初めて確定申告を行う方でも理解できるように説明します。
青色申告とは確定申告の一種
確定申告を行う人は、大きく分けて青色申告と白色申告の二つの種類に区分されます。それぞれの申告の特性は以下のとおりです。
- 確定申告:基本的に全てのフリーランスが行うべき申告手続きです。
- 青色申告:確定申告を行う中で、青色申告の要件を満たす人がこれを選択します。
- 白色申告:確定申告を行う人の中で、青色申告の要件を満たさない人がこれを選択します。青色申告を選択すると、確定申告時に税制上の優遇措置を受けることが可能です。一方、白色申告を選ぶ人には、青色申告のような税制上の優遇はありません。ただし、青色申告を選択するには特定のルールがあり、それを遵守する必要があります。このため、フリーランスの中には、青色申告を希望しながらも、ルールの遵守や所得が少なく節税効果が少ないという理由から、意図的に白色申告を選択する人も存在します。
サラリーマンの副業でも青色申告はできるの?
サラリーマンが副業をしている場合でも、青色申告を利用することは可能です。しかしながら、「事業所得・不動産所得・山林所得」のいずれかに該当しなければ、青色申告は行えません。これら3つの所得の特徴は以下の通りです。
事業所得:事業を行って得られた収入
不動産所得:不動産投資から得られた収入
山林所得:農林活動(山林の伐採や売却等)から得られた収入
しかしなお、一時的な収入や所得額が少ない場合は、「雑所得」とみなされることがあります。雑所得に該当する場合、青色申告の利用は許されません。
青色申告をするメリット・意味
青色申告が良いと聞くものの、どんなメリットがあるかイメージできない人もいるでしょう。
ここでは、青色申告をするメリットや意味を紹介します。
青色申告特別控除が認められている
青色申告の最大の利点は、青色申告特別控除が利用可能であることです。この制度を利用すれば、所得から最大65万円が控除されます。その結果、所得税や住民税、社会保険料などの課税対象金額が減少し、節税効果を享受できます。
具体的な数字を用いて、青色申告特別控除を利用した場合と利用しなかった場合の、年間の所得税額の違いを見てみましょう。
例:年間売上が300万円、経費が100万円、所得控除が50万円、所得税率が5%の場合、
青色申告特別控除で65万円が控除される場合:
(300万円-100万円-65万円-50万円)×5%=4万2,500円
白色申告で青色申告特別控除を利用できない場合:
(300万円-100万円-50万円)×5%=7万5,000円
以上の例から、青色申告特別控除で65万円控除した場合、年間の所得税が3万2,500円節約できることがわかります。
純損失の繰り越し・繰り戻しが可能
青色申告の対象者は、損失分を次の期間へ(最長3年まで)繰り越すことができます。具体的な例を見てみましょう。
例:前期に10万円の純損失が発生し、それを当期に繰り越す。なお、当期の純利益は100万円とします。
100万円-10万円=90万円(当期における確定申告で適用される純利益額)
このように、当期の純利益額を減らして確定申告を行うことで、赤字が出たとしても翌年以降の節税効果が期待できます。ただし、全ての赤字が繰り越し対象とは限らないため、具体的な項目を確認した上で繰り越しを行ってください。
貸倒引当金の計上が認められている
青色申告を行う人には、貸倒引当金の設定が認められています。貸倒引当金とは、売上が得られなかった際に備えて設けられる予備資金のことを指します。これは債権が回収できなかったときの保険とも言える資金で、その存在があることにより、債権回収が難しくなった場合でも、その引当金でカバーすることが可能になります。そのため、資金繰りに困らないようにしたい人には特におすすめの制度です。
取得価額が10~30万円未満であれば、減価償却費として一括計上できる
減価償却費とは、固定資産の価値が低下する際に発生する経費のことを指します。例えば、25万円で購入した固定資産の価値を5年かけて0にする場合、毎年5万円ずつ減価償却費として計上できます。
しかし、青色申告の対象者である場合、固定資産の取得価額が10~30万円未満であると、一括で減価償却費として計上することが許されます(少額減価償却資産の特例)。つまり、25万円の減価償却費を一度に計上することが可能となります。
ただし、1年間で計上できる上限額は300万円までとなっています。さらに、事業を開始してから1年が経過していない状態で確定申告をする場合は、「事業年度の月数×25万円」が上限となりますので、注意が必要です。
青色申告特別控除で65万円控除してもらう時の条件を5つ紹介
青色申告の最大の利点は「青色申告特別控除」であり、これによって最大で65万円が所得から控除されることです。ただし、この特別控除を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。ここでは、それらの条件について見ていきましょう。
青色申告承認申請書の提出をしている
「青色申告承認申請書」を提出することが必要です。この書類は、管轄の税務署に提出するもので、事業開始後に一度だけ提出すれば良いです。申請書は、税務署で直接受け取ることも可能ですし、国税庁の公式ウェブサイトから印刷することもできます。
複式簿記で記帳をしている
複式簿記による記帳が必要な要件となっています。
現金主義による記帳は許可されていません。
具体的な例を挙げて、現金主義と複式簿記の仕訳の違いを比較してみましょう。
例:1月1日に10万円の商品を信用販売し、1月31日に売上金を回収した場合。
現金主義の場合
1月31日:(借方)現金10万円 (貸方)売掛金10万円
複式簿記の場合
1月1日:(借方)売掛金10万円 (貸方)売上10万円
1月31日:(借方)現金10万円 (貸方)売掛金10万円
現金主義では、金銭の出入りに関する取引のみを記帳します。
しかし、複式簿記では、金銭の出入りがない取引でも記帳が必要となります。
したがって、青色申告対象者の方は、記帳内容がより詳細であると言えます。
必要な帳簿が保管されている
帳簿の保管も義務付けられています。
主な帳簿には以下のものがあります。
仕訳帳
総勘定元帳
買掛金元帳
売掛金元帳
現金出納帳
売上帳
仕入帳
固定資産台帳
これらの帳簿は、全て保管する必要があります。
さらに、取引に関連する書類(請求書、見積書、契約書、注文書、財務諸表など)の保管も義務付けられています。
税務調査の際には、これらの書類を提示する必要があるため、年度ごとに整理して保管しましょう。
財務諸表と確定申告書を期日内に提出している
確定申告書と共に、財務諸表を期限内に提出することも必要な条件となっています。
財務諸表とは、「損益計算書」、「貸借対照表」、「キャッシュフロー計算書」のことを指しますが、フリーランスの確定申告では、損益計算書と貸借対照表を提出します。
損益計算書とは、費用と収益に関する勘定科目の金額を計算し、まとめた表のことを指します。
一方で、貸借対照表とは、資産と負債、純資産に関する勘定科目の金額を計算し、まとめた表のことを指します。
「電子帳簿保存」or「e-tax」にて確定申告している
2020年分の確定申告から、「電子帳簿保存」または「e-taxによる確定申告」のいずれかを行わないと、青色申告の特別控除額は最大で55万円までとなります。
これら2つの要件について、詳しく見ていきましょう。
電子帳簿保存
電子帳簿保存とは、コンピューターやネットワーク上で帳簿を保存することを指します。
紙での保管と比較して、保管場所を取らない利点があり、帳簿を紛失するリスクも低くなります。
そのため、保管の手間を省きたい方にとって、電子帳簿保存は便利な選択肢と言えます。
ただし、電子帳簿保存を利用する際は、事前に税務署への申告が必要となります。
e-tax
e-taxとは、国税庁が提供するネットワーク上で確定申告を行うシステムのことを指します。
インターネット環境があれば、どこからでも確定申告の手続きが可能で、税務署での確定申告の順番待ちをする必要もありません。
ただし、e-taxを利用する際は、初期登録やe-taxソフトの使用準備など、事前に必要な手続きがあるため、ご注意ください。
ここまでの内容も踏まえ青色申告のやり方を見てみよう!!
ここからは、さきほどの内容も踏まえて青色申告のやり方を見てみましょう。
①青色申告承認申請書を提出
青色申告承認申請書は、最寄りの税務署に提出します。
ただし、提出のタイミングによって適用開始年度が変わるため、注意が必要です。
例えば、2023年分の確定申告で青色申告を利用したい場合、2023年の3月15日までに提出する必要があります。
その年の1月16日以降に事業を開始した場合は、事業開始日から2カ月以内に提出することとなっています。
青色申告承認申請書を提出した年の翌年から青色申告が適用される場合もあるので、注意してください。
②日ごろの取引内容を仕訳処理する
事業で発生した取引の内容を仕訳処理しましょう。
取引内容に合わせて、借方と貸方に勘定科目と金額を記入します。
なお、借方と貸方に書くケースは、こちらの通りです。
~借方に書くケース~
資産の増加
負債の減少
純資産の減少
費用の増加
収益の減少
~貸方に書くケース~
資産の減少
負債の増加
純資産の増加
費用の減少
収益の増加
仕訳の例を、いくつか見てみましょう。
1.現金1万円を支払って備品を買った
(借方)備品1万円<資産の増加>(貸方)現金1万円<資産の減少>
2.借入金1万円を現金で返済した
(借方)借入金1万円<負債の減少>(貸方)現金1万円<資産の減少>
3.会議へ出かけるために新幹線代を2万円支払った
(借方)旅費交通費2万円<費用の増加>(貸方)現金2万円<資産の減少>
4.20万円分の商品を売り上げ、10万円を現金で受け取り、残りを後払いにした
(借方)現金10万円、売掛金10万円<資産の増加>(貸方)売上20万円<収益の増加>
5.商品を売り上げて10万円を現金で得ていたが、その後お客様へ返金することになった
(借方)売上10万円<収益の減少>(貸方)現金10万円<資産の減少>
勘定科目の種類や金額の増減を考えると、仕訳処理をしやすいでしょう。
③仕訳の内容を基に、財務諸表・帳簿を作成する
仕訳の金額を基に、財務諸表や帳簿を作成します(これを転記と言います)。
転記先が異なると、複数の帳簿で金額が一致しないという問題が生じます。
金額が一致しない状況を放置すると、確定申告後に税務署から指摘を受ける可能性がありますし、税務調査の対象になる恐れもあるため、注意が必要です。
④確定申告書を財務諸表と一緒に提出する
財務諸表と帳簿の作成が完了したら、財務諸表は確定申告書と一緒に税務署へ提出します。
提出期間は毎年2月16日から3月15日までです(ただし、休日の場合は日程がずれることがあります)。
郵送で提出する場合は、封筒に押された消印日が提出日となります。
一方、e-taxで確定申告を行う場合は、財務諸表と確定申告書を税務署へ提出する必要はありません。
インターネット上で確定申告が完了した日が提出日となります。
ただし、e-taxでの申請はネットワークが混雑する場合もあるため、余裕を持って申請を完了させることをお勧めします。
⑤提出後は関係書類を保管しておく
提出後も、帳簿や領収書などの書類は保管しておく必要があります。
帳簿や決算関連の書類、現金や預金に関する書類は7年間、その他の書類は5年間の保管が義務付けられています。
ただし、2年前の確定申告で所得が300万円以下だった場合は、保管のルールが一部異なることがあります。
詳細な内容は国税庁のホームページに掲載されていますので、確認しておきましょう。
参考:国税庁
青色申告をする時は会計ソフトを使うと便利!
青色申告の場合は、会計ソフトを活用すると便利です。
最後に、会計ソフトが便利な理由を紹介します。
仕訳の内容が自動で帳簿や財務諸表に転記される
多くの会計ソフトでは、入力した仕訳の内容が自動的に帳簿や財務諸表に転記されます。
つまり、自分で帳簿や財務諸表への転記作業を行う必要がないということです。
転記作業が減ることで、確定申告に関する作業時間も短縮されるため、このような会計ソフトの利用はおすすめです。
コンピュータ上で帳簿を保管できる
会計ソフトを利用すると、コンピュータ上で帳簿を保管することが可能になります。
そのため、紙ベースで帳簿を保管する必要がなくなります(ただし、電子帳簿保存の申請を行っていることが条件となります)。
クレジットカードと会計ソフトの自動連携ができる
クレジットカードの支払い内容を会計ソフトに自動連携できるソフトも存在します。
例えば、10万円の備品をクレジットカードで購入した場合、購入日や金額などは自動的に会計ソフトに反映されます。
自分で会計ソフト上に仕訳を入力する必要がないため、作業の簡略化に役立ちます。
会計ソフトの中には、勘定科目まで自動で設定できるサービスが付いているものもあり、簿記や会計の知識がない人にもおすすめの機能です。
ただし、クレジットカードのブランドによっては、自動連携の機能が利用できない場合もあるので、注意が必要です。
自身で確定申告ができない時は税理士への委託が便利
読者の中には、簿記や会計の知識がない、または確定申告の作業時間を確保できないため、自分自身で確定申告の準備が難しいと感じる方もいるでしょう。
そのような場合、税理士に委託する方法も考えられます。
税理士に委託すれば、確定申告にかける時間を削減できるだけでなく、確定申告でミスが生じる可能性も低くなるため、おすすめです。
しかし、費用が高額で利用できないと感じる方もいるかもしれません。
費用を抑えるために税理士以外に委託を考える方もいるかもしれませんが、法律上、税理士資格を持たない人への業務委託は許可されていません。
そのような方には、「Tech Bizカード」の会員向けサービスである「税務代行サポート」の利用も一つの選択肢となるでしょう。
関連記事:Tech Bizカードについて
このサービスは、毎月5000円から税務処理の一部を委託できるサービスです。
税理士の資格を持つ専門家が、あなたの代わりに税務処理を行います。
税理士事務所に依頼する場合の相場と比べて、月々の費用が安いのが特徴です。
手頃な価格で税理士に委託したい方は、このサービスを選択肢に入れておくと良いでしょう。
まとめ
フリーランスの青色申告に関することを中心に紹介しました。
まとめると、このようになります。
✓青色申告のメリット・意味
①青色申告特別控除が認められている
②純損失の繰り越し・繰り戻しが可能
③貸倒引当金の計上が認められている
④10~30万円未満であれば、減価償却費として一括計上できる
✓フリーランスが青色申告特別控除で65万円控除してもらう時の条件
①青色申告承認申請書の提出をしている
②複式簿記で記帳をしている
③必要な帳簿が保管されている
④財務諸表と確定申告書を、期日内に提出している
⑤電子帳簿保存or「e-tax」にて確定申告している(2020年分の確定申告~)
ルールを無視して、勝手に青色申告の制度を利用することは許されていません。
申請を行い、ルールを遵守した上での利用が基本となります。
確定申告後に問題が発生しないように、ルールを確認した上で青色申告の制度を利用しましょう。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /