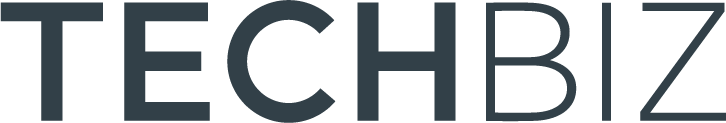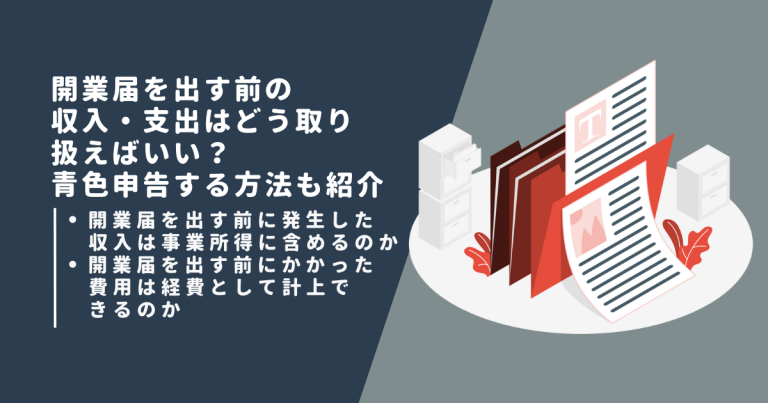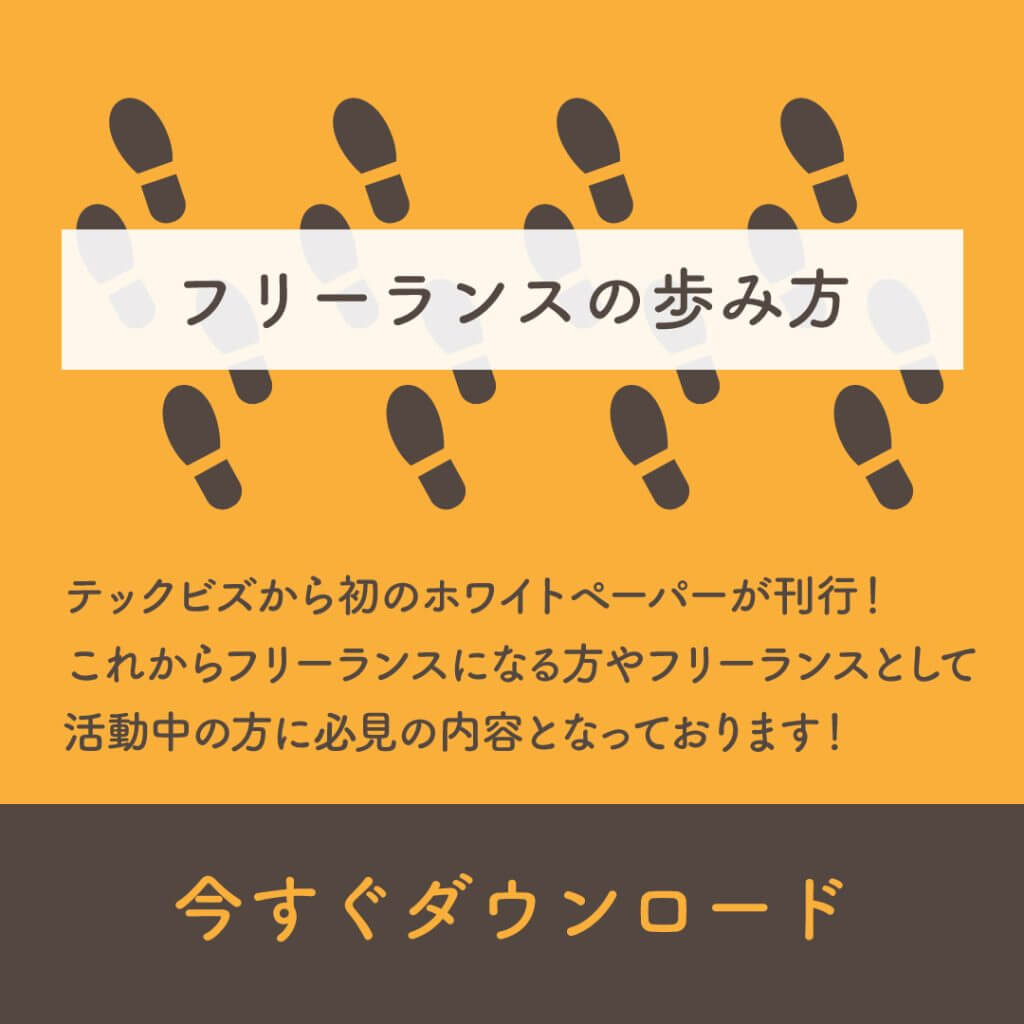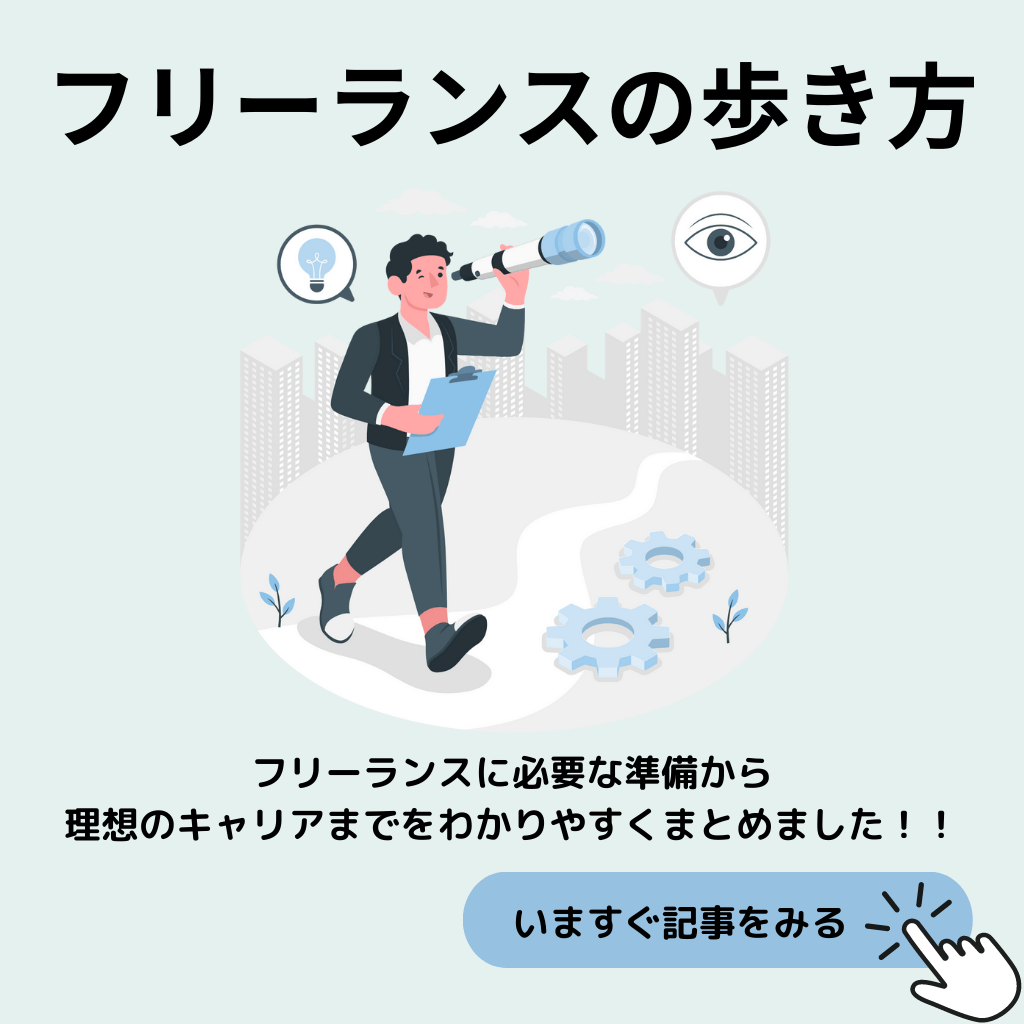・フリーランスの準委任契約とは
・業務委託契約と準委任契約の違いとは
・準委託契約を結ぶ時の注意点とは
フリーランスの皆さんの中には、クライアントから「準委任契約でお願いします」と依頼され、その意味を知らない方もいるかもしれません。
契約の詳細を理解しておくことは非常に重要です。なぜなら、仕事が始まってから契約内容を理解しなかった結果、不利益を被る可能性があるからです。契約の内容は、報酬の形式や仕事の進め方に大きな影響を及ぼします。できるだけストレスフリーな状態で仕事を行うためには、契約内容を知ることが重要となります。
したがって、今回は準委任契約の基本情報を提供し、そのメリット・デメリット・注意すべき点などについても触れていきます。
準委任契約の概要
準委任契約とは、業務委託契約の一部であります。業務委託契約とは、クライアントが業務をアウトソーシングする際に結ばれる契約で、これには準委任契約の他に「委任契約」、「請負契約」が含まれます。
なお、準委託契約は、「履行割合型」と「成果報酬型」の2つのタイプに分けられます。
履行割合型
これは、業務量や作業時間に対する報酬支払いの制度を指します。例えば、時間報酬の単価が同じであった場合、50時間働いた人よりも100時間働いた人の方が多くの報酬を受け取ることができます。
成果報酬型
これは、成果物が完成した時点で報酬が支払われる方式を示します。たとえば、システムエンジニアの場合、システムの納品が完了した段階で報酬が発生するということです。
委任契約と準委任契約の違い
委任契約と準委任契約の違いは、法律に関する業務が委託されるかどうかです。
委任契約は、法律に関する業務を委託する場合の契約で、その代表的な例としては「弁護士への訴訟代行の依頼」が挙げられます。訴訟代行は法律に関わる業務であるため、これは委任契約に該当します。
一方で、準委任契約は法律に関する業務以外を委託する際に結ばれる契約です。例えば、システムエンジニアによるシステム構築は法律に関わる業務ではないので、ここでは準委任契約が適用されます。
準委任契約を結ぶメリット
ここでは準委任契約を結ぶメリットを見てみましょう。
成果物が完成していなくても報酬を受け取る権利がある
履行割合型の契約を結んだ場合、進捗状況や作業時間に応じて報酬が支払われます。そのため、成果物が完成しなかった場合や、プロジェクトが途中で終了してしまった場合でも報酬を得ることが可能です。
仕様を変更しやすい
履行割合型の契約の場合、クライアントの負担を軽減する、またはより有利な提案をすることで、仕様の変更を受け入れてもらえる可能性があります。なぜなら、作業過程自体に報酬が発生するからです。
例えば「作業時間を削減する」などの提案を行うと、それが作業量や労働時間の減少、そして人件費の節約に繋がるかもしれません。そのため、クライアントにとってメリットがあるなら、仕様変更の要求が認められる可能性は十分に考えられます。
瑕疵担保責任がない
瑕疵担保責任とは、納品した成果物に問題が発生した場合の責任についてのことを指します。請負契約では、成果物を納品したとしても、問題が生じた場合には契約終了後も対応しなければなりません。
しかし、準委任契約の場合、受託者の瑕疵担保責任についての規定はありません。定められた通りの成果物を納品していれば、納品後に問題が生じたとしてもその対応は必要ありません。納品後の責任は、ワーカーからクライアントに移行します。
準委任契約を結ぶデメリット
その一方、準委任契約を結ぶデメリットもあります。
ここでは履行割合型のパターンを基に、デメリットを3つ紹介します。
途中で開発が止まる恐れがある
以下のような理由から、開発が途中で停止することがあります:
予算が枯渇したため開発を中止する
工程や作業時間を再評価し、報酬を減らすために開発を停止する
他のプロジェクトチームへ予算を振り向けるため開発を中止する
プロジェクトの進行方向が決定されたとしても、必ずしも100%その通りに進行する保証はありません。途中で開発が停止し、仕事がなくなる可能性も考えられます。
そうならないように、日々の備えが大切です。
契約解除されるリスクがある
完成に時間がかかりそうなプロジェクトであっても、契約解除されるリスクは十分に存在します。
「履行報酬型」では作業過程に対して報酬が発生します。したがって、「完成までの期間が長いからといって安心して仕事に臨む」、という考え方は避けた方が賢明です。
進行状況をコマメに報告することが多い
作業プロセスに対して報酬が支払われるため、進行状況の報告が求められる場面は増えます。
「ちゃんと仕事を進めているか?」「業務に関する専門知識を持っているか?」といったことを確認する目的で、報告を求めるクライアントも存在します。報告書の作成が煩わしいと感じる人にとっては、これが負担に感じられることもあるでしょう。
準委任契約の流れ
契約書をよく読みましょう。特に、「履行割合型」か「成果報酬型」かを確認することが重要です。
契約の内容によって、報酬を受け取る基準が変わります。「あとで考えてみたら、もう一方が良かった」とならないように、契約を結ぶ前の段階でしっかりと確認しておきましょう。
確認した後は、契約書に署名し、その控えを保管しておくことを忘れないでください。
準委任契約を結ぶ時の注意点
準委任契約を結ぶ時には注意点もあります。
最後に注意点を3つ紹介します。
業務のタイミングによって短期で解約される場合がある
準委任契約を結んだ場合でも、業務が必要ないと判断されれば契約解除となります。
数カ月から数年間続く業務であれば、長期にわたり仕事に携わることができるかもしれません。しかし、プロジェクトによっては2,3カ月で終了してしまうものもあります。
短期の案件が多いと、新たな仕事を探すための営業活動が増え、生活に影響を及ぼす可能性もあります。1つの仕事に長期間携わりたいと考えている人は、予想される業務期間を考慮しながら、案件を探すことをおすすめします。
再委託は原則できない
再委託とは、自分が受け取った仕事を別の人に依頼する行為を指します。準委任契約では通常、再委託は認められていませんので、基本的には自分自身で作業を行うことになります。ただし、クライアントから許可を得られれば、再委託が可能となります。
時間給や日当で支払われることが多い
準委任契約は、多くの場合、時間給や日給で報酬が支払われます。つまり、働いた時間や日数が多ければ多いほど、報酬も増えます。一方で、請負契約の場合は、成果物に対して報酬が支払われるので、作業時間が短い人ほど時給換算での収入が高くなります。
したがって、短時間で作業が終わる人や、労働時間が少ない人にとっては、準委任契約では得をしないと感じるかもしれません。
善管注意義務が発生する
善管注意義務とは、作業を行う際に必要な最低限の注意を払うべき義務のことを指します。
注意が求められる範囲は、業務を行う者のスキル、経験、専門性等によって決定されます。例えば、システムエンジニアであれば、「他のシステムを誤って操作しないようにする」や、「インシデントが発生した場合に適切に対応する」といった事柄が該当します。
この善管注意義務を違反した場合、クライアントから損害賠償を求められたり、契約解除を通告されることもあります。
まとめ
準委任契約を中心に紹介しました。
まとめると、こちらです。
✓準委任契約のメリット
①成果物が完成していなくても報酬を受け取る権利がある
②仕様を変更しやすい
③瑕疵担保責任がない
✓準委任契約を結ぶ時の注意点
①業務のタイミングによって短期で解約される場合がある
②再委託は原則できない
③時間給や日当で支払われることが多い
準委託契約は、業務終了後に負わなければいけない責任が請負契約と比べて小さいものの、仕事がしにくいと感じる人もいます。自分の働き方に合った契約内容か確認してから、仕事を始めましょう。
※本記事の内容などは2020年8月現在の情報です。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /