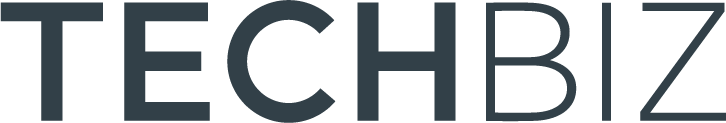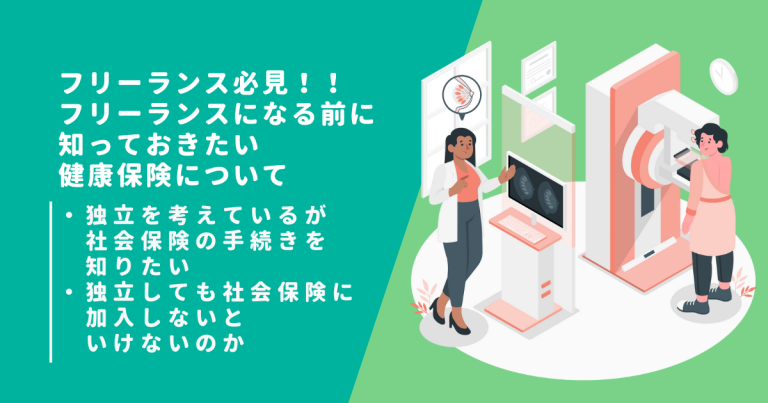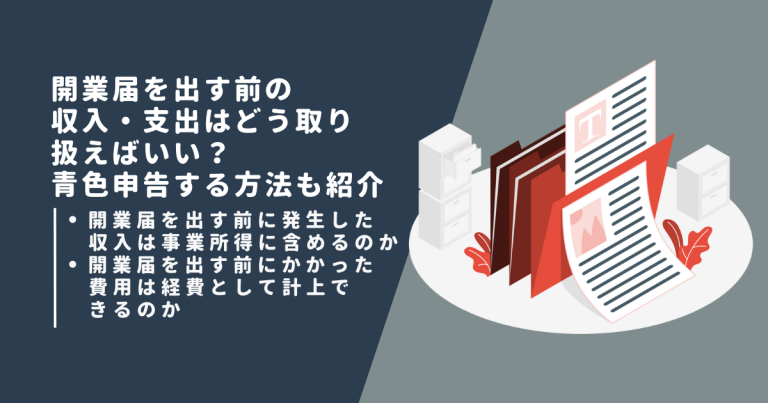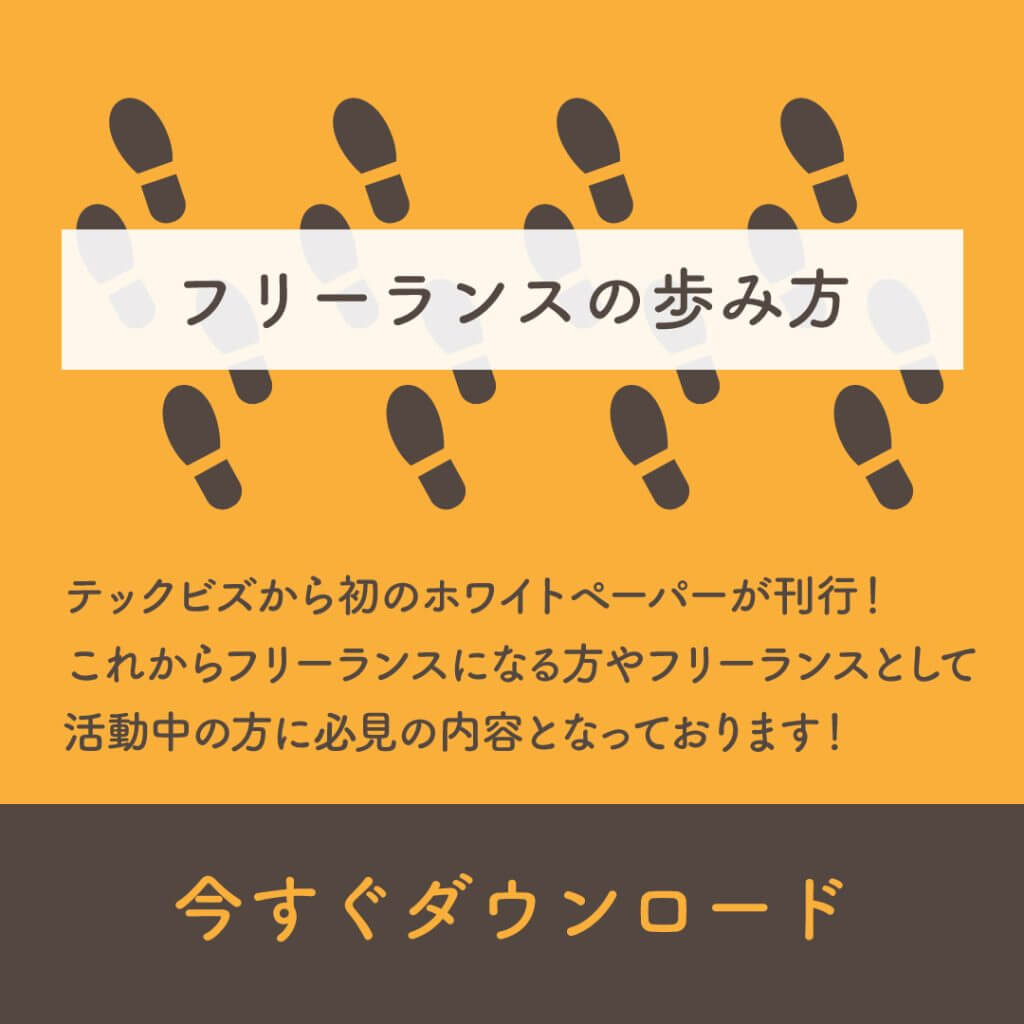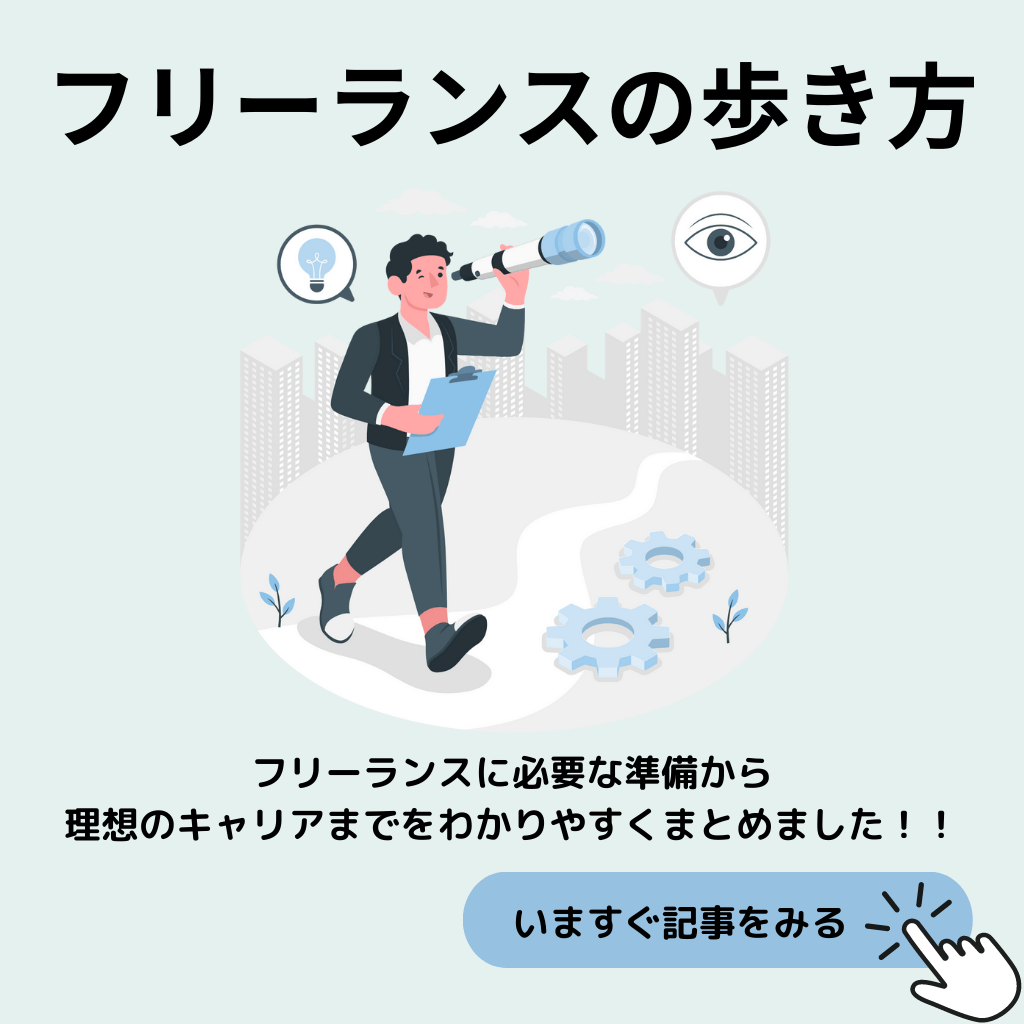・独立を考えているが社会保険の手続きを知りたい
・独立しても社会保険に加入しないといけないのか
・独立後の保険料を抑えるコツとは
フリーランスとして活動する際には、自分自身で社会保険の手続きを行う必要があります。社会保険は様々な保険から構成される制度で、特に健康保険については理解しておくことが重要です。その理由は、独立した後の保険料に大きな影響を及ぼすからです。
今回は、フリーランスとして独立した後の健康保険やその加入方法について解説します。
【はじめに】社会保険の概要を解説
社会保険は、2つの意味合いで使われます。
- 会社員が加入する公的保険
- ほとんどの日本国民が加入する公的保険
社会保険の比較を行う際、会社員とそれ以外の人々(例えば、個人事業主)が加入している公的保険を対比するときは、主に①の観点から話されることが多いです。一方で、税金や保険料など社会保険の具体的な内容について説明する際には、②の観点が主に用いられます。
広範な視点から見ると、社会保険は4つの保険から構成される公的な制度です。ここでは、社会保険がどのような保険から成り立っているのかを紹介します。
年金保険
日本国民である20歳から60歳までの全ての人々は、必ず加入しなければなりません。年金の支給は基本的に65歳から開始されますが、支給開始日を前倒しにしたり、後ろ倒しにしたりすることも可能です。支給開始日を早めると毎月の受取額は少なくなり、逆に遅らせると増えます。ただし、支払期間が10年未満の人は年金を受け取ることはできません。厚生年金と国民年金の違いについては、別の記事で詳しく解説しています
関連記事:国民年金と厚生年金の違い!会社員を辞めてフリーランスになったら切り替えが必要
雇用保険
雇用保険は、雇用の安定や就職環境の整備を目的として設立されました。その特徴としては、退職後に「失業給付」を受け取ることができる点が挙げられます(ただし、受け取れない場合もあります)。失業給付とは、失業者(無職)に対して一定期間支給される制度で、過去の給与や年齢などに基づいて給付金額が決定されます。
ただし、申請時に虚偽の報告を行い、失業給付を不正に受け取る行為は不正受給となります。不正が発覚した場合、失業給付金の返還だけでなく、罰金の支払いも命じられます。
参考:ハローワーク
労災保険
労働者災害補償保険は、仕事中や通勤中に怪我をしたり、病気になったりした従業員に対して支給される保険です。この保険の対象となるのは、企業に雇用されている正社員や非正規社員です。
参考:厚生労働省
健康保険
健康保険に加入している場合、医療費の支払いは最大で3割までとなります(ただし、保険適用外の医療費は除く)。また、加入者は高額療養費制度の対象となります。高額療養費制度とは、1ヶ月間の医療費が自己負担額の上限を超えた分が免除される制度のことを指します(ただし、対象外の費用もあります)。例えば、1ヶ月間の医療費が10万円で、自己負担額の上限が5万7,600円だった場合、4万2,400円(10万円-5万7,600円)は支払いが免除されます。なお、自己負担額の上限は5段階あり、年収や年齢が高くなるほど自己負担額も増えます。
健康保険には、会社員が加入する健康保険(社会保険)や、自営業者が加入する国民健康保険など、複数の種類があります。さらに、民間企業の従業員とその扶養者は「組合健保・協会けんぽ」に、公務員は各種共済組合に加入しています。しかし、どの健康保険に加入していても、「最大3割負担」や「高額療養費制度」のルールは変わりません。
参考:全国健康保険協会
フリーランスになるとき健康保険の選択肢は3つある
会社を辞めて独立する場合、健康保険については3つの選択肢があります。独立する人の収入や世帯構成などによって、どの選択肢が最も適しているかは異なります。
ここでは、それぞれの選択肢について詳しく見ていきましょう。
①市区町村による「国民健康保険」(国保)
国民健康保険は市区町村単位で運用されている保険制度です。異なる自治体に引っ越す場合は、保険の変更手続きを行う必要があります。
国民健康保険の加入者は、所得額が一定基準を下回った場合、減免制度を利用することができます。減免とは、支払額が免除(または減額)される制度のことで、収入が一定額以上減少したり、所得が少ない人を対象とした制度です。減免を申請できる基準は、その年の所得額や生活状況、世帯人数によって変わります。
国民健康保険への手続き方法
国保の加入方法を見てみましょう。
1.居住地の市区町村の役所へ行く
国民健康保険への加入は、居住地を管轄している役所(役場)で申し込みを行います。国民健康保険の窓口が設けられているので、そこで手続きを進めます。
必要な書類は以下のとおりです(ただし、自治体によって異なる場合があります)
本人確認書類
国民健康保険への加入は、居住地を管轄している役所(役場)で申し込みを行います。国民健康保険の窓口が設けられているので、そこで手続きを進めます。
必要な書類は以下のとおりです(ただし、自治体によって異なる場合があります)
退職した企業から取り寄せる必要のある書類もあるため、早めに手続きを始めることをおすすめします。手続きは役所の窓口または郵送で行うことができます。
2.国民健康保険の健康保険証が送付される
国民健康保険への加入が完了すると、健康保険証が自宅に送られてきます。健康保険証には有効期限が設定されており、定期的に新しい健康保険証が発行されます。期限が過ぎた健康保険証は使用できません。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、以下の3つの計算式から算出されます。なお、税率や均等割・世帯割の金額は自治体によって異なります。計算方法は以下の通りです。
医療分:(所得額-基礎控除)×税率 + 均等割の金額 + 世帯割の金額
支援分:(所得額-基礎控除)×税率 + 均等割の金額 + 世帯割の金額
介護分(40〜64歳が対象):(所得額-基礎控除)×税率 + 均等割の金額 + 世帯割の金額
医療分+支援分+介護分=年間の健康保険料
所得が多い人ほど、健康保険料は増えます。ただし、健康保険料は所得控除の「社会保険料控除」に加算できるため、支払額が多い人ほど節税効果も高くなります。フリーランスの医療保険については、別の記事で詳しく解説しています。
関連記事;フリーランスの医療保険事情とは?制度・種類を解説!
②「会社の保険の任意継続」
会社員時代に加入していた健康保険を継続して利用する方法(健康保険の任意継続)も選択肢の一つです。条件を満たしていれば、この方法で加入できます。退職時の標準報酬月額(給料)に基づいて健康保険料が決定されるため、国民健康保険料よりも低い場合は、この方法を利用することも考えられます。
「会社の保険の任意継続」の手続き方法
健康保険の任意継続の手続き方法は以下の通りです。
「全国健康保険協会」への書類送付
「任意継続被保険者資格取得申出書」に記入し、居住地を管轄している地域の「全国健康保険協会」へ送付します。扶養者がいる場合は、給与証明書や所得証明書などの事実を確認できる書類も同封してください。なお、提出期限は退職日の翌日から20日以内です。
全国健康保険協会から健康保険証が届く
書類が受理されると、申請から約1週間後に健康保険証が届きます。
もし健康保険証が届く前に医療機関を利用し、医療費を全額支払った場合は、「全国健康保険協会」へ「療養費支給申請書」を提出してください。そうすると、健康保険適用分の医療費が返ってきます(任意継続被保険者の対象になっている場合)。
「会社の保険の任意継続」に加入する時の注意点
健康保険の任意継続の特徴は、2年間保険料が変わらないことです(一部例外あり)。国民健康保険の場合、所得が下がれば翌年の保険料も減少します。しかし、健康保険の任意継続では、所得が下がったとしても翌年の保険料は減少しません。
ただし、逆に所得が増えても翌年の保険料は上がらないため、所得が増える見込みのある人にとってはお得な制度と言えます。そのため、独立後の所得を予測してから、任意継続を利用するかどうかを決めることが重要です。
参考:協会けんぽ
③「国民健康保険組合」が運営するもの
各組合(=国民健康保険組合)が運営している健康保険に加入する方法も選択肢の一つです。例えば、以下のような組合が存在します。
文芸美術健康保険組合
東京写真材料国民健康保険組合
東京都情報サービス産業健康保険組合
加入条件は、組合が定める条件や職種によって異なります。国民健康保険組合に加入する際も、任意継続と同様に、国民健康保険に加入した場合と比べて健康保険料が安くなるかどうかを確認してから加入することが重要です。
独立後の健康保険加入で気を付けること
独立後に加入する健康保険は、会社員時代に加入していた健康保険とは利用の仕方が異なります。最後に、その注意点について見ていきましょう。
支払い方
会社員が健康保険料を支払う際は、基本的に給与から自動的に引かれます。しかし、独立した後は自分で支払う必要があります。口座振替を利用する場合もあれば、請求書を提出して支払うこともあります。
支払期限を過ぎると、遅延料が発生することもあります。例えば、国民健康保険の場合、最大で年利14.6%の利息が加算されます。
支払割合
会社員が健康保険料を支払う際は、会社が50%を負担していました。しかし、独立した後は全額自己負担となります。そのため、独立後は支払いの割合が大きくなることを覚悟しておく必要があります。
関連記事:フリーランスの社会保険を解説!会社員との違い・計算方法は?
まとめ
フリーランスの健康保険について紹介しました。今回のポイントはこちらです。
✓独立後に加入できるかもしれない健康保険
①市区町村による「国民健康保険」
②「会社の保険の任意継続」
③「国民健康保険組合」が運営するもの
日本に住んでいる限り、健康保険への未加入は認められていません。さらに、加入しなければ医療費が全額自己負担となり、不利益を被ることになります。余計な出費を増やさないためにも、独立後は速やかに健康保険の切り替えを行いましょう!
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /