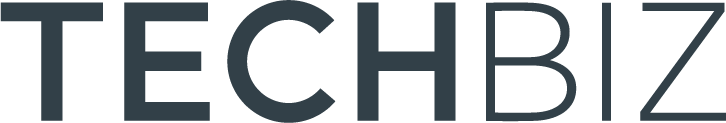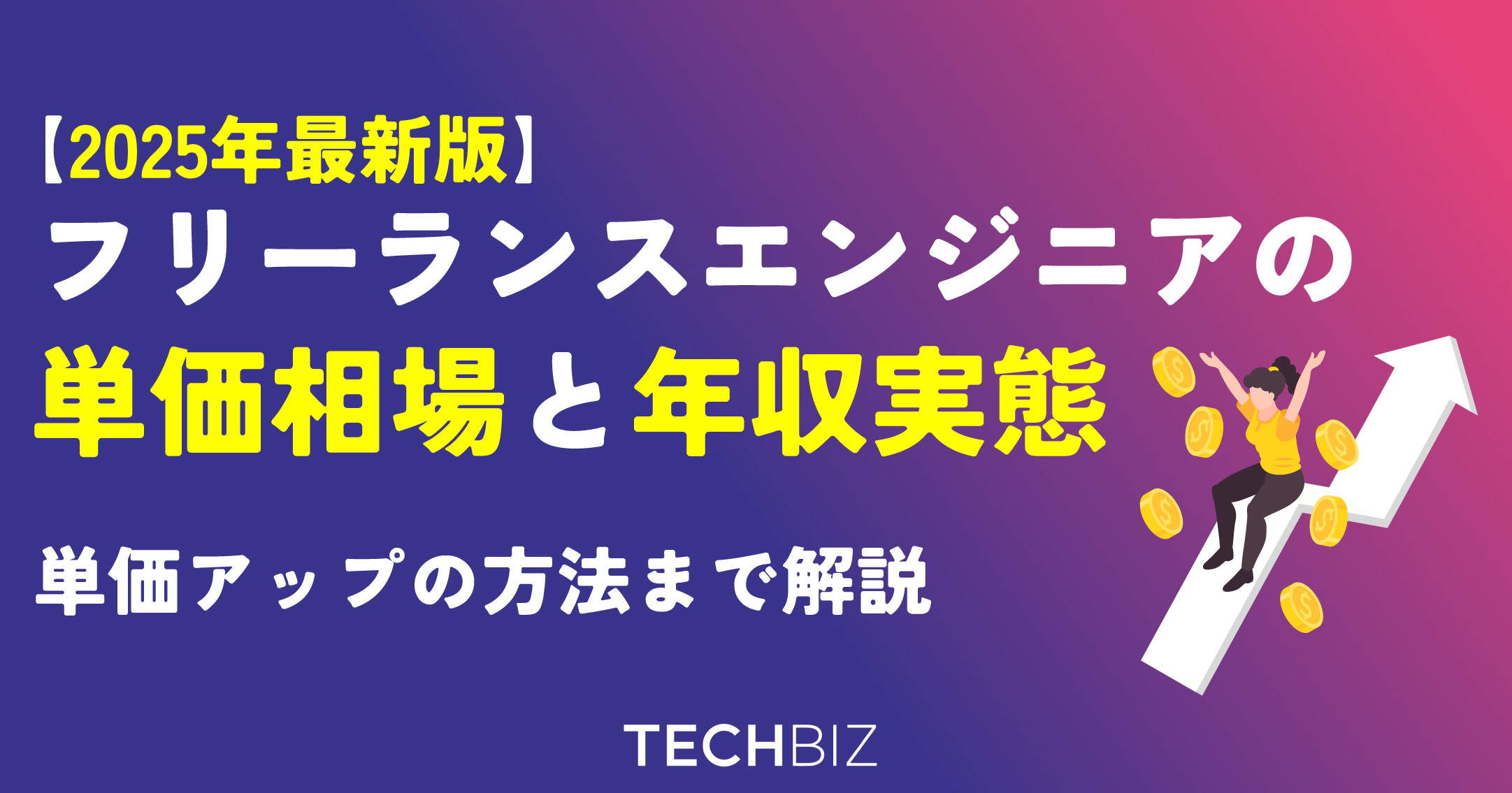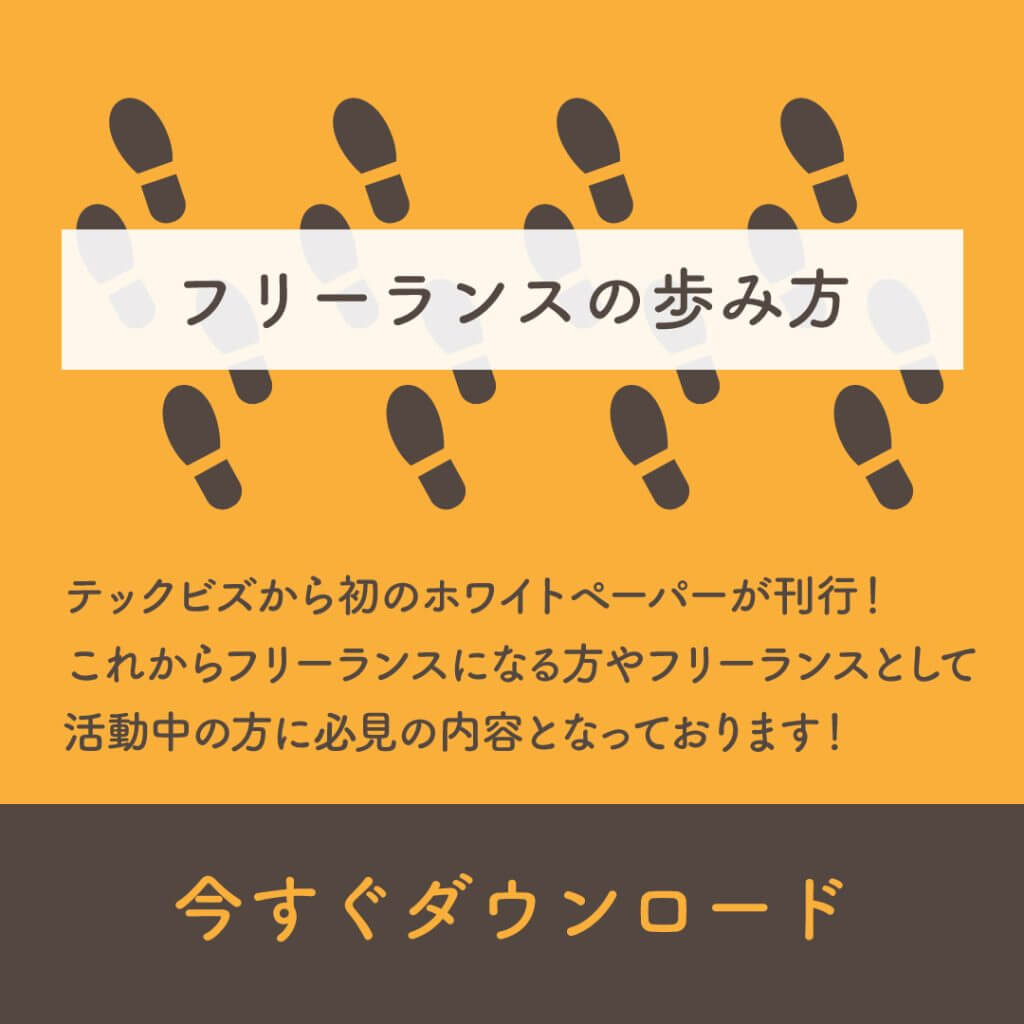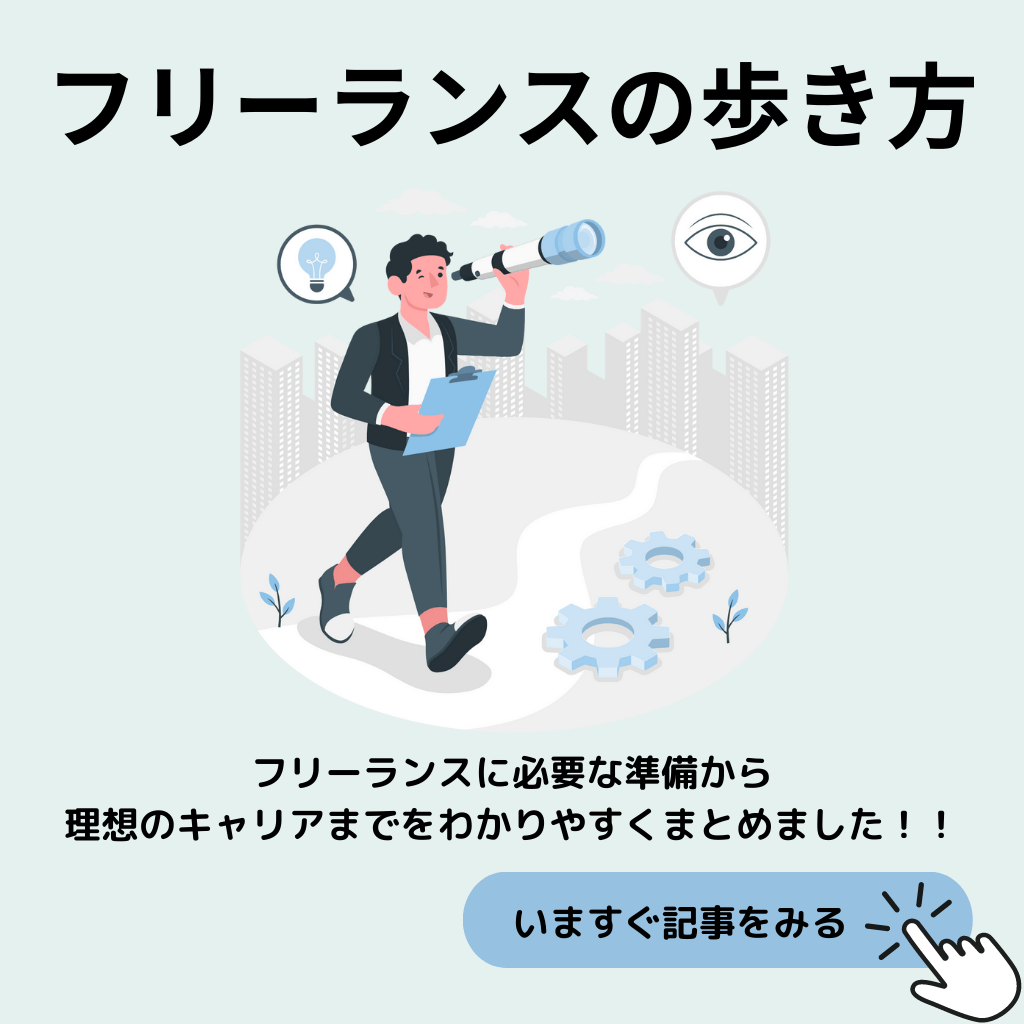これまで会社員として勤務していてフリーランスになろうとしている方や、フリーランスになりたての方など、フリーランスにどのような税金がどれくらいかかるのか?受けられる控除は何がどれくらいあるのか?そこまで理解しきれていない人も多いのでしょうか。会社員の場合、企業が税金の計算や納税を代行してくれていたので無理もありません。
この記事では、そんな方に向けて「フリーランスに掛かる税金や保険料」や「税金の負担額を下げてくれる節税対策」「経費の勘定科目」などを解説します。是非フリーランスとして少しでも手取り額を残せるよう参考にしてください。
・フリーランスが支払う必要のある税金や保険料
・税金の負担額を下げる節税対策
・フリーランスが経費にできる勘定科目
フリーランスが支払う必要がある税金と保険料一覧
まず初めに、フリーランスが支払う必要がある税金と保険料の代表例について解説します。
フリーランスが納税する必要がある税金と保険料は下記になります。
所得税
住民税
個人事業税
消費税
国民健康保険料
国民年金保険料
所得税
フリーランスとして報酬を受け取った所得に対して国に納める税金が所得税になります。会社員の場合も、毎月給与から天引きされているので、給与明細などでよく見かけていると思います。収入から必要経費を差し引いたものを所得とみなし、さらに所得から各種控除を差し引いた金額に税率を掛け合わせると所得税の金額が算出できます。なお、税率は所得の多さによって率が高くなる累進税率が適用されています。1年間の所得が高くなれば高くなるほど税率が上がり、所得税の金額が高くなりますので注意しましょう。
収入額-経費額-各種控除=所得額
所得額×税率-控除額=所得税の税額
所得税の税率
下記が、国税庁が発表している所得税の税率と控除額になりますので参考にしましょう。
なお、ここでいう控除額は無条件で適応されるものとなっております。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:所得税の税率|国税庁
所得税の納付期限と納付先
所得税の納付期限ですが、確定申告と同じ3月15日となっています。所得が大きくなればなるほど、大きな金額を納めなければいけないため、この日までにまとまった金額を用意しておきましょう。なお、所得税は源泉徴収の対象業務の場合、クライアント側に事前に天引きされている、源泉徴収額があります。その額が実際に支払う所得税より多い場合は、確定申告によって還付を受けることができます。
また、2037年までは、「復興特別所得税」として基準所得税額の2.1%が課税されます。
所得税の税額負担を下げることができる各種控除
所得税には様々な控除があります。これは国の政策や、何かしらの理由で税金を支払う経済力がなくなってしまった人のために用意されているものです。もちろん控除は申告しないと適応されないため、忘れないようにしましょう。
種類 | 控除を受けられる場合 |
|---|---|
雑損控除 | 災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた |
医療費控除 | 一定額以上の医療費等の支払がある |
セルフメディケーション税制 | |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払がある |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払がある |
生命保険料控除 | 新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払がある |
地震保険料控除 | 地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある |
寄附金控除 | 国に対する寄附金やふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)、特定の政治献金などがある |
寡婦・寡夫控除 | あなたが寡婦又は寡夫である |
勤労学生控除 | あなたが勤労学生である |
障害者控除 | あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である |
配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる |
配偶者特別控除 | あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である |
扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる |
基礎控除 | 38万円の控除 |
住民税
個人住民税は、その個人が居住している都道府県と市区町村に支払う税金のことで、地域の公的サービス(交通道路や社会福祉、ごみ処理など)に使用されています。住民税は、前年の所得金額に応じて金額が変動する所得割と、定額で課税される均等割の2つで構成されております。所得割は個人の所得に税率を掛け合わせて算出するため、所得が多くなれば支払う住民税は高くなります。
- 合計所得金額-損失の繰越控除=総所得金額
- 総所得金額-所得控除額の合計=課税所得額
- 課税所得額×税率(10%)=税額控除前の所得割額
- 税額控除前の所得割額-税額控除の額=税額控除後の所得割額
- 所得割額+均等割額=税額
参考:https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/49732/
住民税の税率
住民税の税率ですが、所得割は課税所得の10%(内訳は都道府県4%、市区町村6%)、均等割が都道府県1,000円+市区町村3,000円の合計4,000円です。所得割と均等割の合計額が実際に納付する金額になります。なお、2024年まで、東日本大震災の復興特別税として均等割りの金額に追加で年額1,000円(都道府県500円+市区町村500円)かかるため、均等割は合計5,000円になります。
※均等割は住んでいる地域によって異なることがあります。
所得割(税率) | 均等割(年間金額) | ||
一律 | 通常 | 2014年~2023年 | |
都民税・道府県民税 | 6% | 3,000円 | 3,500円 |
区市町村民税 | 4% | 1,000円 | 1,500円 |
合計金額 | 10% | 4,000円 | 5,000円 |
※均等割は2014年~2023年の間、防災施策のための臨時増税をしています。
住民税で適用できる控除の一覧
下記が住民税で適用できる控除の一覧です。
詳細は各地方自治体のホームページなどを見て確認しましょう。
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
障害者控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除
下記が税額控除の種類です。
こちらも確認しましょう。
配当控除
外国税額控除
寄附金税額控除
調整控除
配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
引用:個人住民税|東京都主税局
住民税の納付期限と納付先
住民税の納付期限は、6月末・8月末・10月末・翌1月末の年4回です。期限を忘れてしまう場合には一括で支払うこともできます。
納付先としては、その年の1月1日時点に住んでいる地域に支払うことになります。
住民税の支払い方法としては、自宅に届く納付書をもとに銀行や郵便局、コンビニなどでも支払うことができるので忘れないように納税しましょう。
個人事業税
個人事業主にのみ納税義務が発生する税金が個人事業税です。個人事業主が収益を得るために、様々な行政サービス(公道の利用や、手続きの案内、公共施設など)を利用するために支払うものになるため、地方税として各都道府県に支払うものになります。対象となる業種は絞られているのと、控除されるケースもあります。
{所得(収入-必要経費)-各種控除}×業種ごとに定められた税率=税額
個人事業税の対象となる業種とその税率
個人事業税の対象と税率は下記業種です。
自分の対象となる業種と税率を把握しておきましょう。
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第1種事業 | 5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
|---|---|---|---|---|---|
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 | 4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 | 5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 | 装蹄師業 | |||
引用:個人事業税|東京都主税局
個人事業税が控除されるパターン
個人事業税の控除としては下記があります。
個人事業主が全くかからないケースもあるので把握しておきましょう。
(1)事業主控除
事業を行った月数で異なりますが最大2,900,000円の控除ができます。
事業を行った月数ごとに計算しましょう。実質年間2,900,000以下の所得となった事業の場合は個人事業税の納税はありません。
事業を行った | 事業主控除額 |
|---|---|
1ヶ月 | 242,000 |
2ヶ月 | 484,000 |
3ヶ月 | 725,000 |
4ヶ月 | 967,000 |
5ヶ月 | 1,209,000 |
6ヶ月 | 1,450,000 |
7ヶ月 | 1,692,000 |
8ヶ月 | 1,934,000 |
9ヶ月 | 2,175,000 |
10ヶ月 | 2,417,000 |
11ヶ月 | 2,659,000 |
12ヶ月 | 2,900,000 |
(2)繰越控除
青色申告をしていて事業所得が赤字となった場合などに、翌年以降の事業黒字と相殺できます。
また、その他にも災害時の損失など様々な繰越控除が適用されることがあります。
充分に調べて控除を活用しましょう。
(3)法定業種に当てはまらない場合
前述した「個人事業税の対象となる業種とその税率」でも記載した通り、個人事業税を支払う必要がある業種は法定業種で定められているので、それに該当しない場合支払う必要がありません。主に、スポーツ選手や作家、漫画家、音楽家、芸能人、農業、林業などがあります。
消費税
消費税はフリーランスがクライアントに請求し、まとめて国に納める必要がありますが、下記条件の場合納税が免除されます。
なお、免除された場合でも、クライアントに消費税を請求できます。
・前々年の年間売上が1000万円未満の場合
※1度課税事業者になっている場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出が必須
・開業してから2年以内の場合
なお、消費税を納税する際の税額計算方法は、本則課税と簡易課税の2種類あります。
それぞれ解説していきますので参考にしてください。
本則課税の計算方法
本則課税は、消費税納税の基本的な計算方法で、クライアントから預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて算出する方法です。
課税売上でかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税=消費税納税額
例えば、税率が10%で売上2,200,000円(内200,000円が消費税)、仕入れにかかる原価が1,100,000円(内100,000円が消費税)の場合の計算例は「200,000円-100,000円=100,000円」が税務署へ納税する消費税額になります。
<本則課税の計算例>
200,000円(課税売上でかかる消費税額)-100,000円(課税仕入れにかかる消費税)=100,000円(消費税納税額)
簡易課税の計算方法
簡易課税という計算方法は小規模事業者向に設けられている制度で、課税売上から業種ごとに定められたみなし仕入れ率を掛け合わせて簡易的に計算する方法です。消費税の情報整理ができない場合は簡易課税で算出し納税しましょう。
課税売上にかかる消費税額-課税売上に掛かかる消費税額×みなし仕入れ率=消費税納税額
例えば、第2種事業で課税売上が2,200,000円(内消費税が200,000円)の場合、みなし仕入れ率80%になるため下記の計算式になります。
<簡易課税の計算例>
200,000円(課税売上にかかる消費税額)-200,000円(課税売上にかかる消費税額)×80%=40,000円(消費税納税額)
簡易課税のみなし仕入れ率
下記がみなし仕入れ率なので参考にしましょう。
事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
簡易課税の注意点
簡易課税を適応するためには条件があるため注意しましょう。
前々年の売上が5,000万円以下の事業者であることと、「消費税簡易課税制度選択届出書」を届け出ることで簡易課税での計算が可能になります。
・前々年の売上が5,000万円以下
・「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要
国民健康保険料
会社員をやめてフリーランスになった場合も、個人で国民健康保険には加入する必要があります。
国民健康保険は会社員の場合、会社が折半で負担してくれますが、個人の場合全額自分で支払う必要があるため、会社員時代より金額が上がる傾向があります。各市区町村に支払うものとなり、保険料や納付方法も市区町村によって異なります。
確定申告の際に、納めた金額を全額控除できるので活用しましょう。
国民年金保険料
国民年金保険も会社員と同様にフリーランスも加入しなければいけません。金額は一律で毎年見直しがされるため、確認して納めましょう。なお、令和4年度の金額は16,590円になります。
会社員の場合、厚生年金保険も加入することになりますが、フリーランスの場合は加入できません。
したがって、年金受給者になった際にもらえる金額が少なくなりますので注意しましょう。
国民健康保険料と同様に確定申告の際に、控除として扱えますので忘れないようにしましょう。
税金の負担額を下げて節税する方法
ここまで、フリーランスが納める必要のある税金や保険料について解説しました。
この章では、税金の負担額を下げて節税する方法について解説します。
控除を漏れなく申請する
これまでも解説してきたように、税金にはたくさんの控除が制度として設けられています。
控除を活用することで、課税所得を減らすことができるためもれなく申請しましょう。
控除の内容は、前述した各税金のパートで解説しているので参考にしましょう。
必要経費を漏れなく計上する
フリーランスの税金負担額を下げる方法として経費を漏れなく計上することをおすすめします。
とは言え、必要経費は具体的にどの項目がどれくらい経費として申請できるかについて明記されてはいません。
したがって、基本的な考え方としては、事業に関わる支出だったかどうかと言う視点でしかありません。
私的なものを経費として申請してしまうともちろん脱税になります。
必要経費として認められるラインの基準として、よく使う必要経費をまとめているので参考にしてください。
フリーランスがよく使う必要経費
下記がフリーランスがよく必要経費として使用する項目の例です。
これらは、事業上発生しやすい項目なので参考にしましょう。
租税公課
荷造運賃
水道光熱費
旅費交通費
通信費
広告宣伝費
接待交際費
保険料、支払保険料損害保険料
修繕費
消耗品費
減価償却費
福利厚生費
給料手当
外注工賃
支払利息
地代家賃
貸倒金
雑費
専従者給与
確定申告は白色申告ではなく青色申告で行う
フリーランスの税金負担額を下げる方法として、確定申告は青色申告をすることをおすすめします。
理由としては、控除を受けられる金額の差になり、青色申告の場合、最大65万円の控除を受けることが可能です。
とは言え、白色申告の場合に簡易的にできる確定申告が、青色申告の場合は複雑になります。その対策としては、会計ソフトなどを活用して、日々収支の管理を行いましょう。そうすれば、青色申告の処理が非常に楽になります。
確定申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出することで青色申告ができるようになります。
青色申告を活用したければ、忘れないように対応しましょう。
フリーランスエンジニアになるならテックビズ
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /