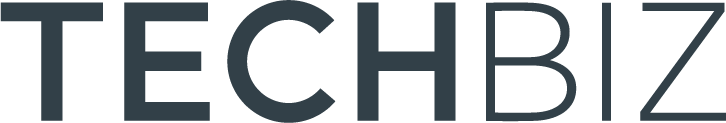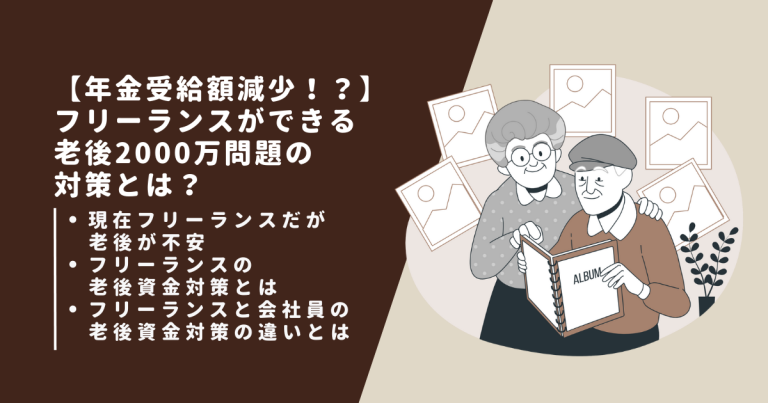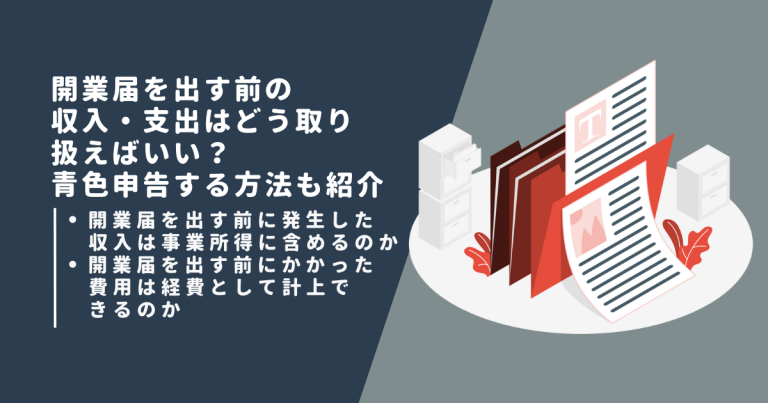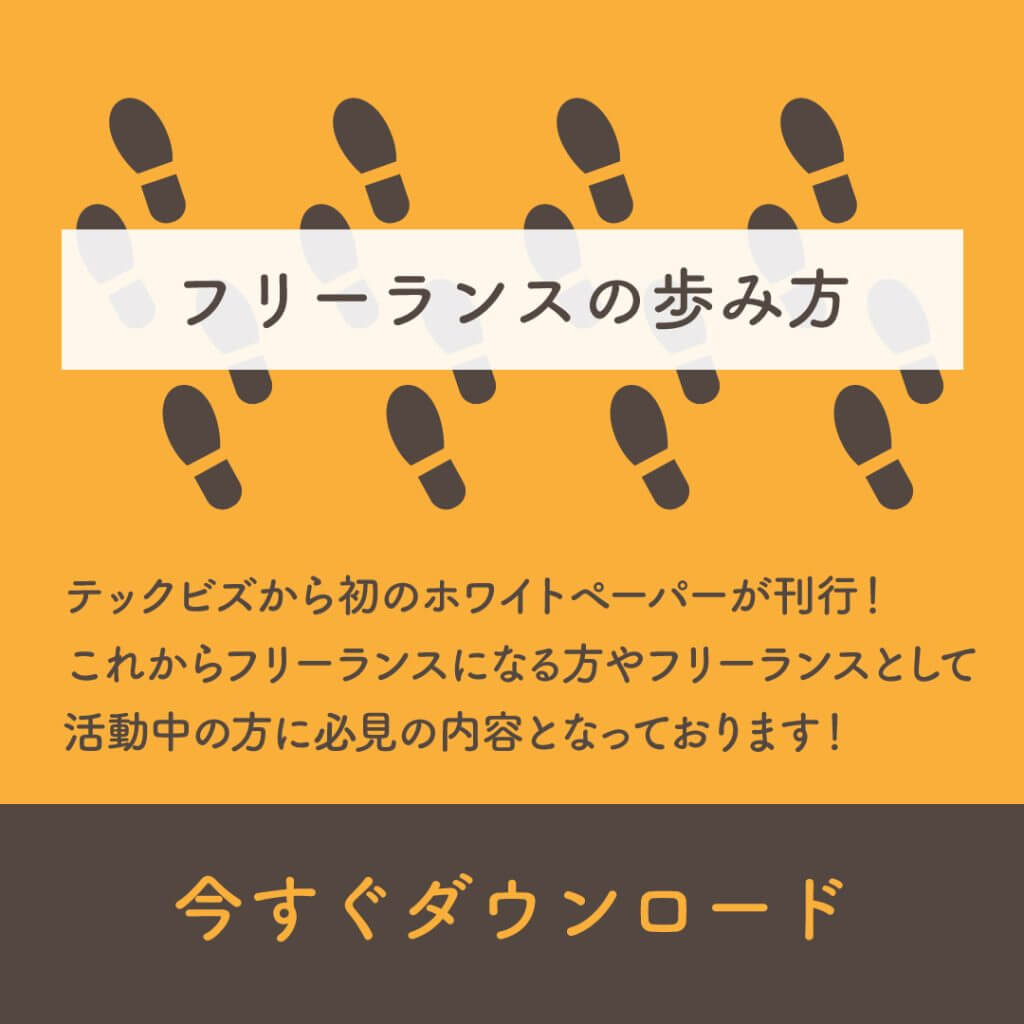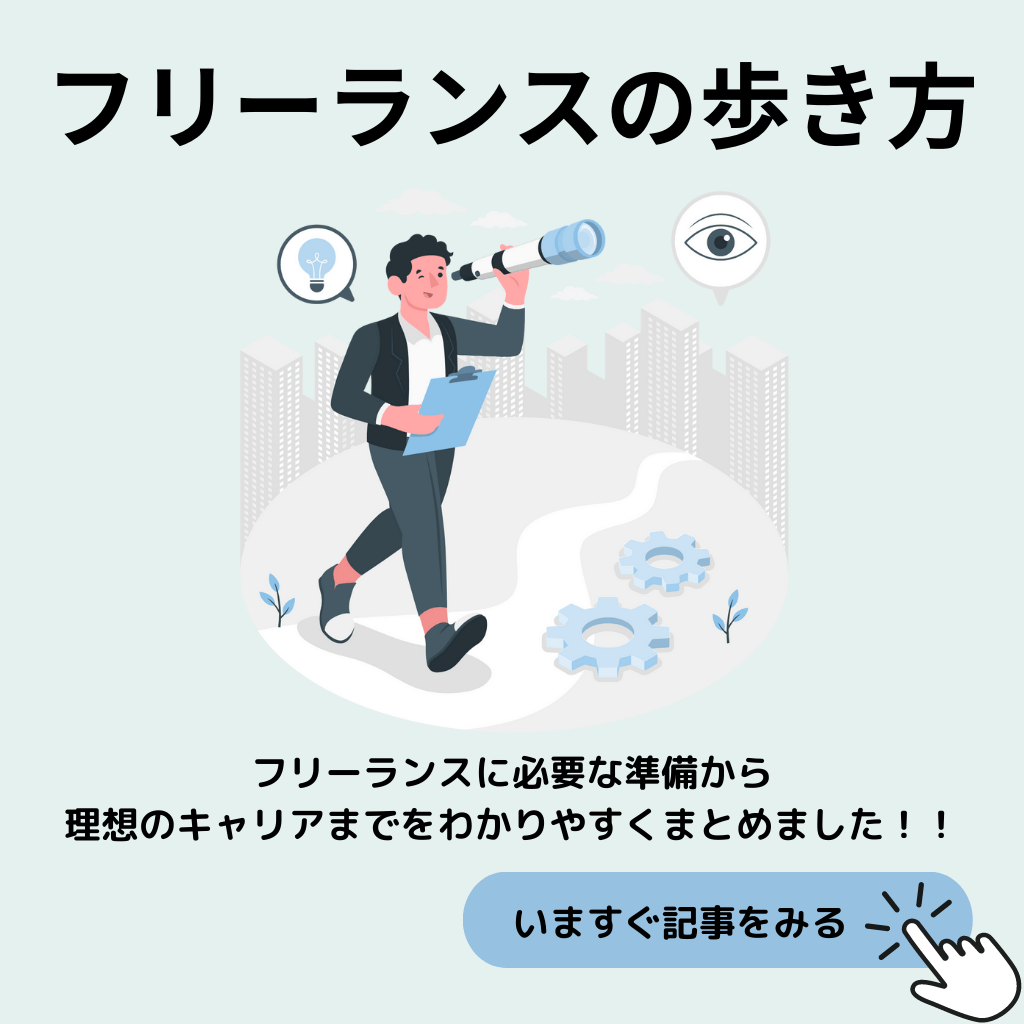・現在フリーランスだが老後が不安
・フリーランスの老後資金対策とは
・フリーランスと会社員の老後資金対策の違いとは
「老後2000万円不足問題」や「年金制度の問題」は、今なお大きな話題となっています。快適な老後生活を送るためには、早期から自身で対策を講じることが重要です。しかし、具体的な老後対策の方法が分からないという方も多いでしょう。
そこで今回は、老後対策が必要な理由と具体的な対策方法について最新の情報をもとに解説します。
老後対策が必要な理由
様々な理由から老後対策は必要です。
はじめに、必要な理由を解説します。
老後に働けなくなる可能性がある
老後になっても現在の仕事が続けられるとは限らないという事実は、誰もが直面する可能性があります。例えば、システムエンジニアの方々は、年齢を重ねるにつれて「体力の衰え」「視力の低下」「新しい技術の学習に時間がかかる」などの問題に直面する可能性があります。また、若い世代であっても、突然の病気や職種の需要の変化などにより、仕事を失うリスクはゼロではありません。
年金受給額が減ってしまうから
日本の人口構成は、高齢者が増え、現役世代が減るという「高齢化社会」が進行しています。これに伴い、将来的に受け取れる年金額が減少する可能性が指摘されています。また、年金の受給開始年齢がさらに遅くなる可能性も十分に考えられます。
これらの事情から、老後対策をしていない人たちは、老後の生活を送ることが困難になる可能性があります。現代の日本では、年金だけでは生活が難しい状況が続いています。そのため、老後対策は必須と言えます。
老後破産を防ぐ
老後破産とは、老後に入ってからの生活が破綻する状況を指します。
これは貯金が少なかったり、年収が低かったりする人のみに起こる現象ではありません。貯金が多かったり、年収が高かったりする人に起こる場合もあります。
老後破産が起こる主な理由はこちらです。
収入と支出のバランスを考えていなかった
多額のローンを組んでしまっていた
貯金をしていなかった
しかし、対策を行えば老後破産は防げます。経済的困窮に陥らないためにも老後対策は必要です。
フリーランスは会社員よりも老後対策に力を入れるべき
フリーランスは会社員と比べると、老後対策に力を入れざるを得ない状況と言えます。ここではその理由を見てみましょう。
収入が不安定
フリーランスは、会社員と比較して収入が不安定になる可能性が高いという特性を持っています。これは、会社員のように毎月一定の給料が保証されていないからです。
会社員の多くは、退職するまで給料が支払われる保証があります。しかし、フリーランスの場合、仕事がなくなれば翌日から収入がゼロになる可能性があります。
このような収入の変動が大きいフリーランスにとって、老後対策は必須と言えます。具体的な対策としては、早期からの資産形成が重要です。
仕事がなくなった時の保障が少ない
会社員の場合、解雇されたとしても「失業手当」が支給されるなどの保証があります。また、病気やケガで働けなくなった場合でも「傷病手当」を受け取ることが可能です。これらは国や自治体が設けている制度で、条件に合致している会社員であれば受け取ることができます。
しかし、フリーランスの場合、これらの制度は利用できません。つまり、仕事がなくなったり、病気やケガで働けなくなったりした場合でも、支援金を受け取ることはできません。そのため、フリーランスは保障が少ない分、老後対策に力を入れるべきと言えます。
年金受給額が少ない
多くのサラリーマンは「厚生年金」の加入者です。厚生年金の魅力は、国民年金と比較して受け取れる金額が多いことにあります。さらに、厚生年金では、企業が半分を負担してくれるため、従業員は半分の負担で済むのです。
給与が上がると負担額も増えますが、それに伴って受け取れる年金額も増えます。
一方、フリーランスの方々は国民年金の対象となります。国民年金は全額自己負担となります。そして、厚生年金と比べて年金受給額も少ないため、老後の生活設計には特に注意が必要です。
過去には、老後に2000万円以上の貯蓄がなければ生活が困難になるという問題(2000万円不足問題)が話題になりました。この問題を聞いて、老後までに2000万円を貯めようと考えた方も多いでしょう。
しかし、この問題で取り上げられた事例は、厚生年金を受け取ることができるサラリーマンです。フリーランスの方々は、サラリーマンと比べて年金受給額が少ないため、2000万円以上の貯蓄が必要となる可能性があります。
関連記事:フリーランスが加入する年金とは?免除申請・老後対策も解説します!
フリーランスができる老後対策を紹介!
老後対策は早いうちから行うに越したことはありません。
ここでは、フリーランスができる老後対策を5つのステップに分けて見てみましょう。
ステップ1:収支の見直し
まず行うのは収支の見直しです。現在の収入と支出の内容を全て書き出しましょう。
たとえば、このような形です。
(毎月の平均)収入
〇〇円
(毎月の平均)支出
家賃 〇〇円
食費 〇〇円
交際費 〇〇円
項目ごとに書いていきます。書き終わったら無駄な支出がないか見てみましょう。「携帯電話代金が高い」「食費がかかりすぎている」など、色々なことが見えてきます。
分析した結果を基に支出を削ると、貯金の増加につながります。
ステップ2:ライフプランの設計
次に、どのような生活を送りたいか、ライフプランを立ててみましょう。例えば、「〇歳で結婚したいから、そのための資金が〇円必要」や「〇歳の時に子供が大学に入学するから、そのために〇円必要」といった具体的な目標を設定することが重要です。何歳までにどれくらいの資金が必要かを考えながらライフプランを立てると、必要な資産形成の目標が明確になります。
もし一人でライフプランを設計するのが難しい場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談するのも一つの方法です。彼らはあなたの目標を達成するための具体的なプランを提案してくれます。
ステップ3:体のメンテナンス(健康維持)
体のメンテナンスも非常に重要です。先ほど述べたように、フリーランスの場合、病気やケガで仕事ができなくなっても、失業手当や傷病手当金のような保障はありません。
年を重ねても働き続けるためには、健康であることが大切です。運動をする、栄養バランスの良い食事を摂るなど、健康を維持するための方法は様々あります。年齢を重ねると、体の衰えは避けられませんが、その衰えをできるだけ遅らせるためにも、健康維持は重要です。
ステップ4:貯金
貯金をする際には、貯金専用の口座を作ることがおすすめです。報酬が入るたびに、その口座に自動で送金される仕組みを作ることで、貯金が苦手な人でもお金を貯めやすくなります。貯金専用の口座を持つことで、設定した目標に向けて迷いなくお金を貯めていくことができます。
また、貯金専用口座を作ることで、収入を把握できるだけでなく、生活費も計算しやすくなり、お金を貯める環境を整えやすくなります。
貯金専用口座には、いくつかの銀行口座を作ることがおすすめです。それぞれの銀行が貯金に有利な特典を用意しているので、自分の貯金スタイルに合ったものを選びましょう。
ある程度の貯金があれば、急な出費が発生しても困ることは減るでしょう。貯金はとにかく自動的に貯まる仕組みをつくることと、目標達成まで継続することが大切です。
ステップ5:積み立て・投資
最後のステップが積み立てや投資です。資産を増やすために大事な工程になります。
なお税金を減らしたい人は、下記のように節税効果が期待できる積み立てや投資を行うといいでしょう。
小規模企業共済
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が加入できる退職金の積み立て制度です1。具体的には、経営者や役員が廃業や退職時の生活資金を積み立てるための共済制度であり、積立金(掛金)は月1,000円から月70,000円(500円単位)まで自由に選択できます。
この制度は、国の機関である中小機構によって運営されています。さらに、税制上のメリットがあり、掛金が全額所得控除可能です。
対象となるのは、建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合で、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員です。
以上のように、小規模企業共済は経営者の退職金制度とも呼ばれ、退職や廃業を見越した安心な生活資金の積立てを支える制度です。
ちなみに積立額は、廃業(もしくは退職)した時に受け取れます。受け取り方は、一括でも分割でも可能です。
NISA
NISA(少額投資非課税制度)は、投資者が少額から投資を行うための非課税制度です。この制度はイギリスのISA (Individual Savings Account)を参考に導入され、NIPPONの頭文字「N」をとってNISAと名付けられました。
NISAの最大のメリットは、一般NISA口座で購入した金融商品(株式や投資信託など)の配当金、譲渡益等が非課税になる点です。少額から投資が可能で、5年間、一般NISA口座で年間120万円の範囲内で購入した金融商品から得た利益が非課税となります。
また、つみたてNISAという制度もあります。これは一定の金額を定期的に投資することを目的とした制度で、対象商品については特定のガイドブックなどで詳しく説明されています。
2023年のNISA投資限度額は一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円です。しかし、これらを使って購入した商品は、2024年からの新しいNISAにおける最大非課税限度額(1,800万円)には含まれません。なお、2023年のうちにNISA口座を開設すると、2024年からの新NISA口座は自動的に開設されます。
IDECO
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金のことを指し、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。iDeCoは加入者自身が申し込みを行い、掛金を拠出し、運用方法を選んで掛金を運用するシステムで、自分のために老後資金を積み立てる制度として設けられています。毎月一定額を積み立てていき、60歳以降に受け取ることができます。また、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金の一つでもあります。
株式投資
株式投資とは、企業が発行する株式を売買することで利益を得る投資方法です。具体的には、「配当金」や「値上がり益」等の利益を狙います。株式投資はリスクがある一方で、大きなリターンが期待できる金融商品の代表格とも言えます。
株式投資の基本的な仕組みは、売買方法や株価の見方などを理解することが重要です。初心者でもこれらの基本的な仕組みを押さえておけば、比較的取り組みやすい商品となります。
また、株式投資を始めるためには、株式の選び方や株式投資に必要な資金、株価の決まり方などを理解することが必要です。これらの知識を身につけることで、株式投資のメリットとリスクを理解し、自分自身の資産運用に活用することが可能となります。
キャピタルゲイン
株価の変動を利用して得る利益を「キャピタルゲイン」と呼びます。
たとえば、1株100円の株を1,000株買ったとします。その後、1株が110円に上がった時に1,000株売ったとします。買った時の価格は10万円、売った時の価格は11万円です。つまり、1万円の利益が発生したことになります(売買手数料・税金は除く)。
株の中には、株価が1日で10%以上変動する場合もあります。
インカムゲイン
インカムゲインとは、その資産を持っておけば継続的に受け取れる利益のことです。
株式投資の場合は「配当金」が該当します。配当金とは、株を持っている人に配るお金のことです。たとえば「1株につき25円の配当」などと載っています。この場合、100株持っていれば2,500円、1,000株持っていれば2万5,000円の配当が受け取れます(税金は除く)。
ただし過去に配当金を出していた企業でも、業績悪化などにより配当金を0にするケースもあるので気を付けましょう。
関連記事:個人事業主が知っておくべき資産形成につながる投資の方法
まとめ
フリーランスの老後対策を中心に紹介しました。
まとめるとこちらです。
✓フリーランスが老後対策に力を入れるべき理由
①収入が不安定
②仕事がなくなった後の保障が少ない
③年金受給額が少ない
✓フリーランスができる老後対策
①収支の見直し
②ライフプランの設計
③体のメンテナンス(健康維持)
④貯金
⑤積み立て・投資
老後対策に力を入れることが、老後を迎えても快適な生活を送るコツです。早いうちから準備しておけば、老後を迎えた時に後悔することが減るかもしれません。今回紹介した内容を参考にしながら、自分の将来を考えてみてください。
※本記事の内容は2021年4月現在の情報です。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /