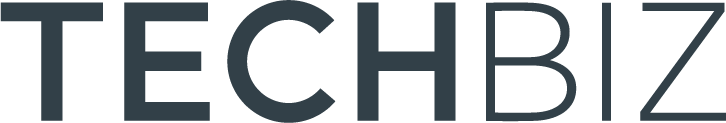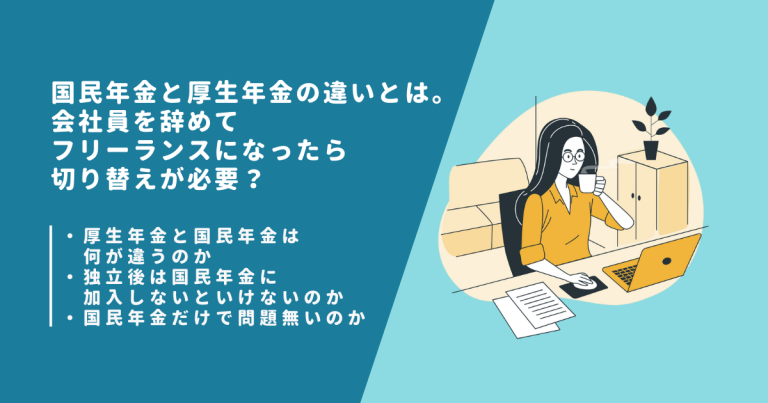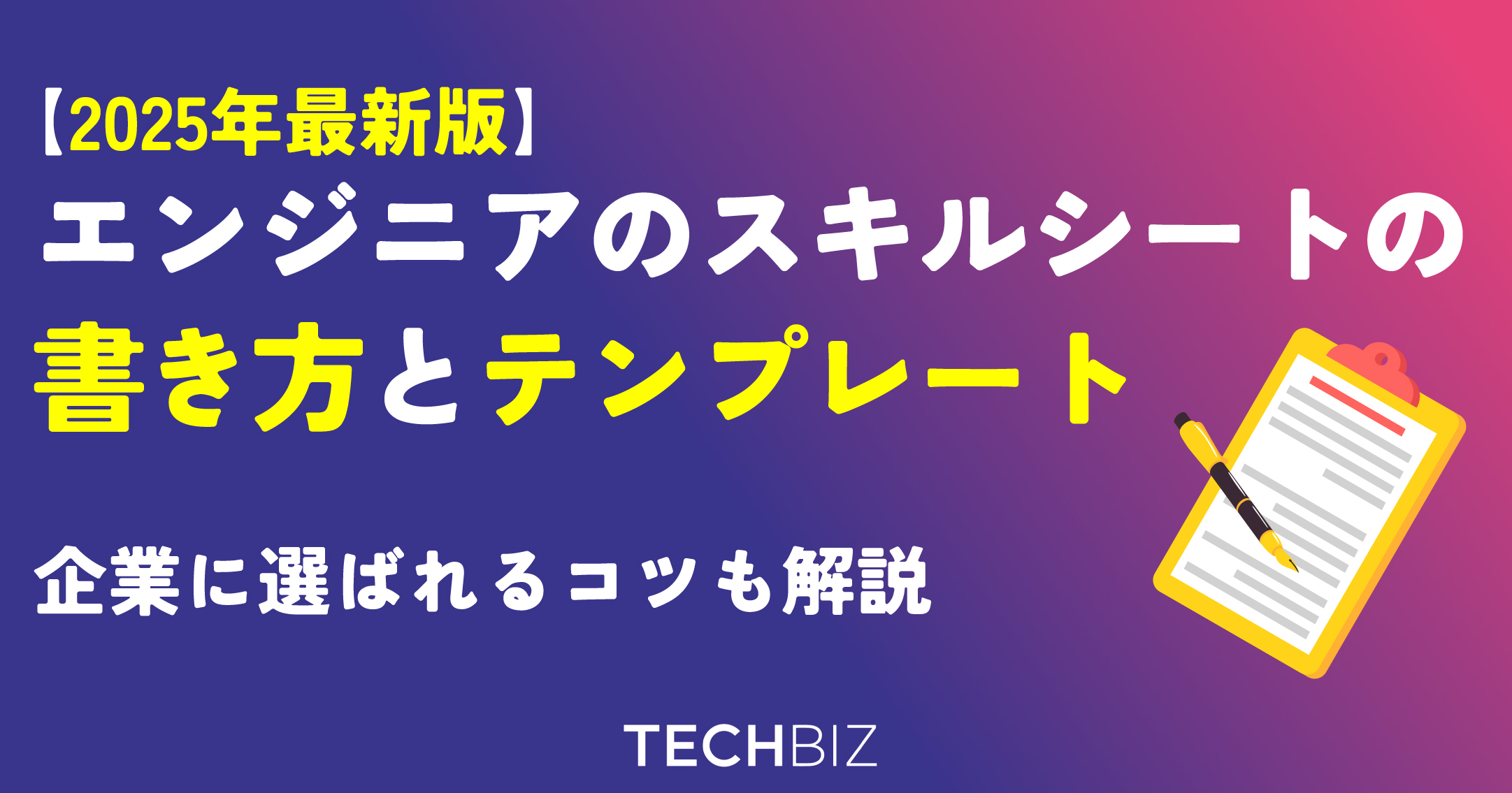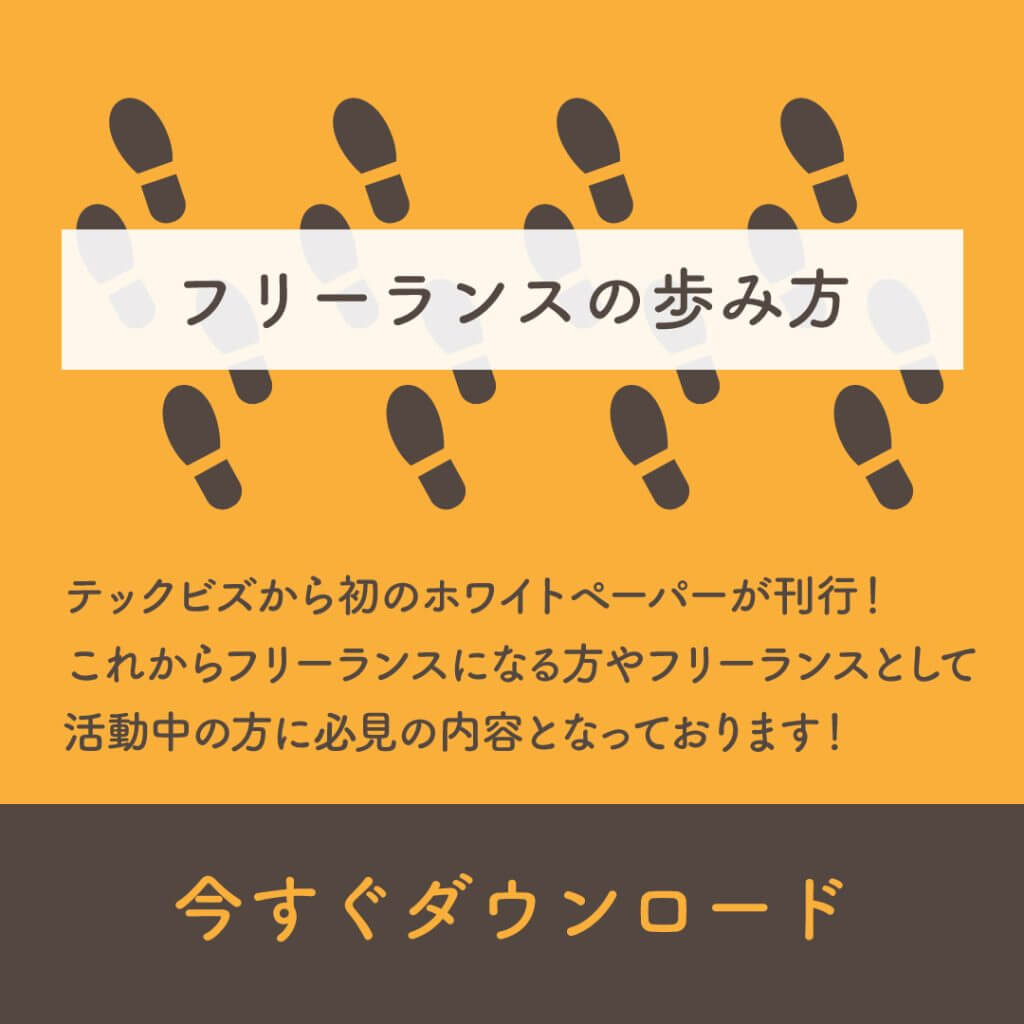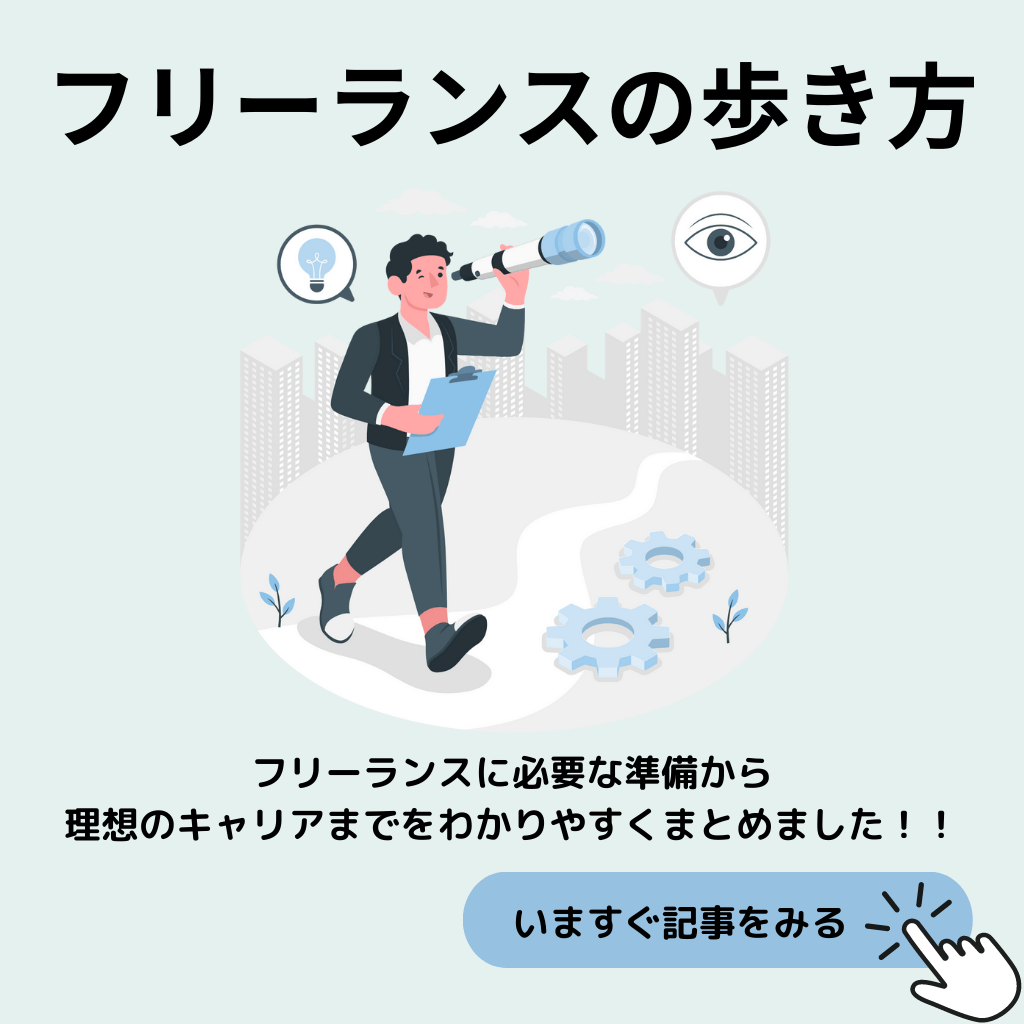・厚生年金と国民年金は何が違うのか
・独立後は国民年金に加入しないといけないのか
・国民年金だけで問題ないのか
年金には、主に国民年金と厚生年金の2つのカテゴリーがあります。フリーランスとして独立する際には、国民年金への加入が求められます。
しかし、国民年金と厚生年金の違いが十分に理解されていない方もいるでしょう。
このため、今回は国民年金と厚生年金の相違点について詳しく説明いたします。国民年金への加入手続きの方法や、将来の不安を解消するための対策も併せてご紹介いたします。この情報を参考にして、お金の将来に対する適切な判断を行ってください。
【前提】厚生年金も国民年金も公的年金制度の一部
国民年金と厚生年金の違いを解説する前に、まず公的年金制度の基本について理解しましょう。どちらも公的年金制度の一環として運営されていることが大前提です。公的年金制度とは、国や地方自治体によって運営される年金制度全般を指します。
この公的年金制度は、20歳以上60歳未満の全ての人が加入の対象であり、大まかに言えば国民年金と厚生年金に二分されます。ただし、公的年金制度には他にも私的年金という形態も存在し、これは個人や勤務先が任意で準備できる年金の一種です。私的年金には様々なタイプがあり、個人の将来のために選択できる幅広い選択肢があることも覚えておきましょう。
国民年金と厚生年金の違い
国民年会と厚生年金は主に以下の5つの点で違いがあります。
国民年金と厚生年金の違い
①加入対象者
②支払額
③負担割合
④年金受給額
⑤免除制度
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①加入対象者
国民年金と厚生年金で加入対象者に違いがあります。
国民年金
対象者は20歳以上60歳未満の全ての人です。国民年金に加入している人は、以下の3種類に分けられます。
| 対象者 | 職業 |
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人 | ・自営業者 |
第2号被保険者 | 原則70歳未満の人 | ・公務員 |
第3号被保険者 | 第二号被保険者に生計を維持されている20〜60歳未満の配偶者 | ・専業主婦・主夫 |
厚生年金は、国民年金に上乗せする年金ですので、厚生年金の人も国民年金に加入していることになります。
厚生年金
厚生年金は、国民年金に上乗せされる形で提供される年金制度であり、厚生年金に加入している人々は同時に国民年金にも加入していることになります。
具体的に言えば、厚生年金の対象者は、第2号被保険者に該当する人々です。このカテゴリーには、公務員や会社員として働いている人々が含まれます。厚生年金は国民年金に追加して支給されるため、国民年金よりも給付額が多いと言えるでしょう。
一方、第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている人々を指しますが、国民年金のみに加入することになります。
このように、厚生年金は国民年金に加えて提供される年金制度であり、公務員や会社員など特定の職業に従事する人々にとっては、より充実した年金制度と言えるでしょう。
②支払額
国民年金と厚生年金で支払額も違ってきます。
国民年金
国民年金は、収入に関係なく支払額が決まっています。2023年度の支払額は16,520円/月でした。
月々の支払額は年度によって変わってきます。
厚生年金
標準報酬月額によって違います。保険料は毎年4〜6月に受け取った毎月の給与額の平均額(標準報酬月額)に保険料率をかけて算出します。
一般企業の会社員であれば、保険料率は18.3%です。仮に標準報酬月額が20万円である場合は、20万円×18.3%となるので1カ月間の保険料は3万6,600円です。
また、給与だけではなく賞与にも厚生年金保険料はかかってきます。1回の税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、それに保険料率をかけて算出します。150万円を超える場合は、標準賞与額は一律で150万円です。こちらも頭に入れておきましょう。
③負担割合
国民年金と厚生年金で負担割合も変わってきます。
国民年金
国民年金の場合は全額自己負担です。2020年度で言うと年間で198,480円の支払いが必要でした。
毎年支払額が変動しますが、それほど大きくは変動しませんので、大体年間20万円はかかることを覚悟しておきましょう。
厚生年金
厚生年金の場合は、企業と従業員で折半します。さきほどの3万6,600円を例にすると、実質自己負担額は1万8,300円です。
実際自分がどれくらいの年金額を負担しているのか気になる人は、給料明細を確認してみると良いでしょう。
④年金受給額
公的年金で受け取れるのは、以下の3つです。
| 受給者 | 条件 |
老齢年金 | 被保険者本人 | 65歳に達した場合 |
障害年金 | 被保険者本人 | 病気や怪我が原因で、障害認定を受けた場合 |
遺族年金 | 被保険者の遺族 | 生計維持関係にある被保険者が死亡した場合 |
この3つの年金それぞれで国民年金と厚生年金で違いがあります。ここでは一般的に年金と認識されやすい、老齢年金に焦点を絞って解説していきます。
国民年金
国民年金加入者は、老齢基礎年金を65歳になると受け取れます。ただし、受給資格があるのは、10年(120ヵ月)以上の納付をしていた人のみです。
受給額は、「物価スライド方式」と言って、毎年物価の変動に応じて変化します。令和3年度の受給額は、40年間支払いを全てした人で月額65,075円です。
未納期間がある人は、その期間に応じて受給額も減額されますので、注意しましょう。
厚生年金
厚生年金加入者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを65歳になると受け取れます。受給資格があるのは、老齢基礎年金の受給条件を満たしていて、かつ厚生年金の被保険者期間が最低1ヶ月でもある人です。
受給額は、支払った保険料に応じて変わってきます。給料が多く、厚生年金保険料を多く支払っていればいるほど、受給できる金額も多くなります。
具体的にいくらになるか算出しようと思うと、計算式は非常にややこしくなります。しかし日本年金機構が運営する「ねんきんネット」を利用すれば、受給できる予定金額を算出できます。
ねんきんネットで計算するためには、登録が必要になりますので、気になる人は登録しておきましょう。
⑤免除制度
公的年金の支払額を免除する制度も、国民年金と厚生年金で異なってきます。
国民年金
国民年金加入者には所得額が一定基準を下回った人向けの免除制度があります。具体的な制度は以下のとおりです。
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
出典:日本年金機構
仮に1人暮らしであれば、年間の所得が57万円を下回ると全額免除の条件をクリアできます。免除をすれば年金保険料が減るので、金銭的負担は減ります。しかし年金受給額も減ることは覚えておきましょう。
その他に出産予定月(出産した月)から4カ月間、免除される制度(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)もあります。
厚生年金
厚生年金加入者には、出産前後の休業・育休を取得している人向けの免除制度(産前産後休業期間中の保険料免除、育児休業等期間中の保険料免除)があります。事業者が日本年金機構へ申請することで認められます。
免除した期間も年金保険料を納めた月としてカウントされるのが特徴です。そのため、免除制度を利用したとしても受給額が減額されることはありません。
会社員からフリーランスになるときは厚生年金から国民年金へ切り替える
会社員からフリーランスになるときには、厚生年金の加入資格を失うため、国民年金への切り替えが必要です。会社員時代とは違って、会社がやってくれるわけではなく、自分で手続きをしなければなりません。
ここでは、国民年金への切り替え方を見てみましょう。
手続き場所
国民年金保険料の手続きは、居住地の役所(役場)に設けられた窓口で行います。また、一部の自治体では、手続きを郵送でも行うことができます。
もし郵送で手続きを行う場合は、各自治体の公式ホームページから申出書をダウンロードして用意し、それを送る必要があります。必要な情報を正確に記入して、手続きを進めましょう。
手続きの方法や詳細については、各自治体の公式情報を確認することが大切です。自分の居住地の役所や自治体の要領に従って、スムーズな手続きを行いましょう。
必要な書類
国民年金への切り替えの際は以下の資料が必要です。
・年金手帳
・退職時に会社から発行される「離職票」「健康保険資格喪失証明書」「退職証明書」
・運転免許証やパスポートなどの身分証明書
・印鑑
・銀行口座がわかるもの
・クレジットカード
年金手帳がない場合は、最寄りの年金事務所へ申請すると後日、郵送で送られてきます。国民年金は、納付書か口座振替、クレジットカード払いのいずれかになります。
口座振替やクレジットカード払いを希望する場合は、銀行口座がわかるものやクレジットカードを持っていくようにしましょう。
提出期限
退職日の翌日から、最大2週間(14日)以内に手続きを行うよう心がけましょう。ただし、2週間を超えてしまった場合でも、国民年金への加入が完全に不可能となるわけではありません。
退職後、別の会社で厚生年金に加入する場合や、配偶者の扶養者になる場合を除いて、全ての人は国民年金に加入する必要があります。ただし、手続きを怠ると国民年金保険料の支払いが遅延し、未納期間が生じる可能性もある点に留意しましょう。
将来の年金受給額を減少させたくない方は、提出期限内に手続きを行うことをお勧めします。国民年金への適切な加入と保険料の支払いを通じて、将来の年金受給に備えることが重要です。
まとめ
厚生年金と国民年金の違い
①加入対象者
②支払額
③負担割合
④年金受給額
⑤免除制度
会社を退職し、フリーランスになった場合は国民年金に加入するのが義務です。手続きを忘れてしまうと、国民年金保険料の未納期間が発生し、将来もらえる年金が減ってしまうので注意しましょう。
会社員からフリーランスになると、社会保険の点でも違いがあります。以下の記事で、社会保険と国民健康保険の違いについて説明していますので、参考にしてください。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /