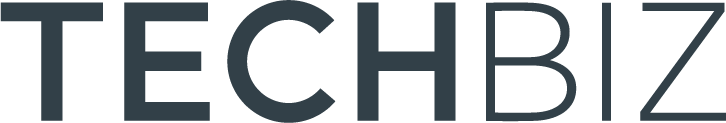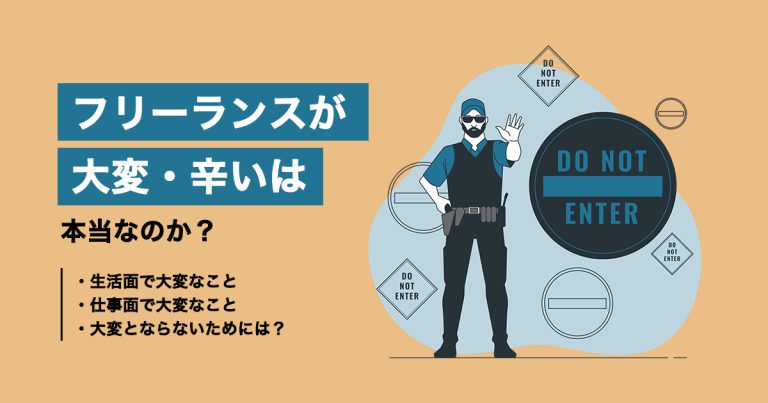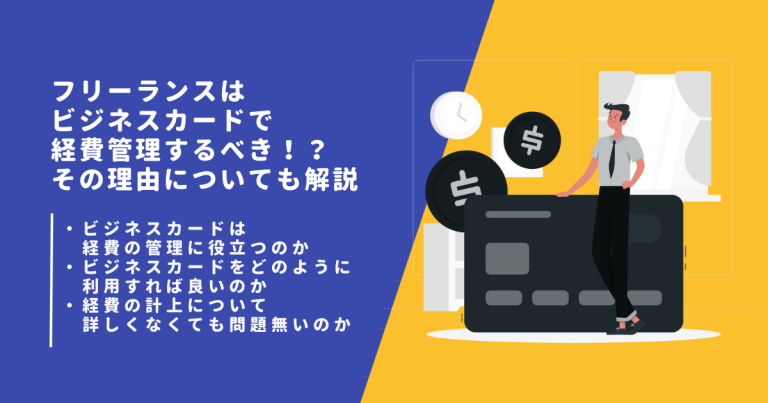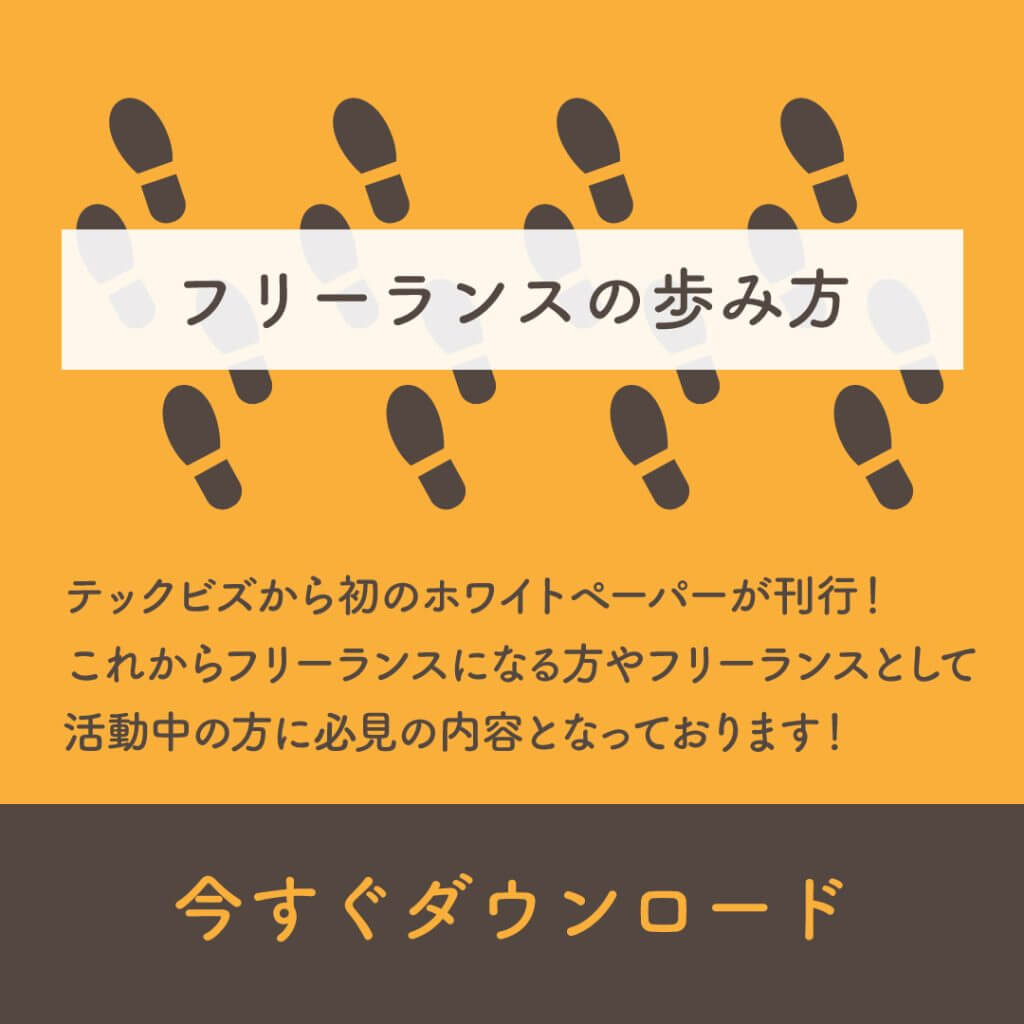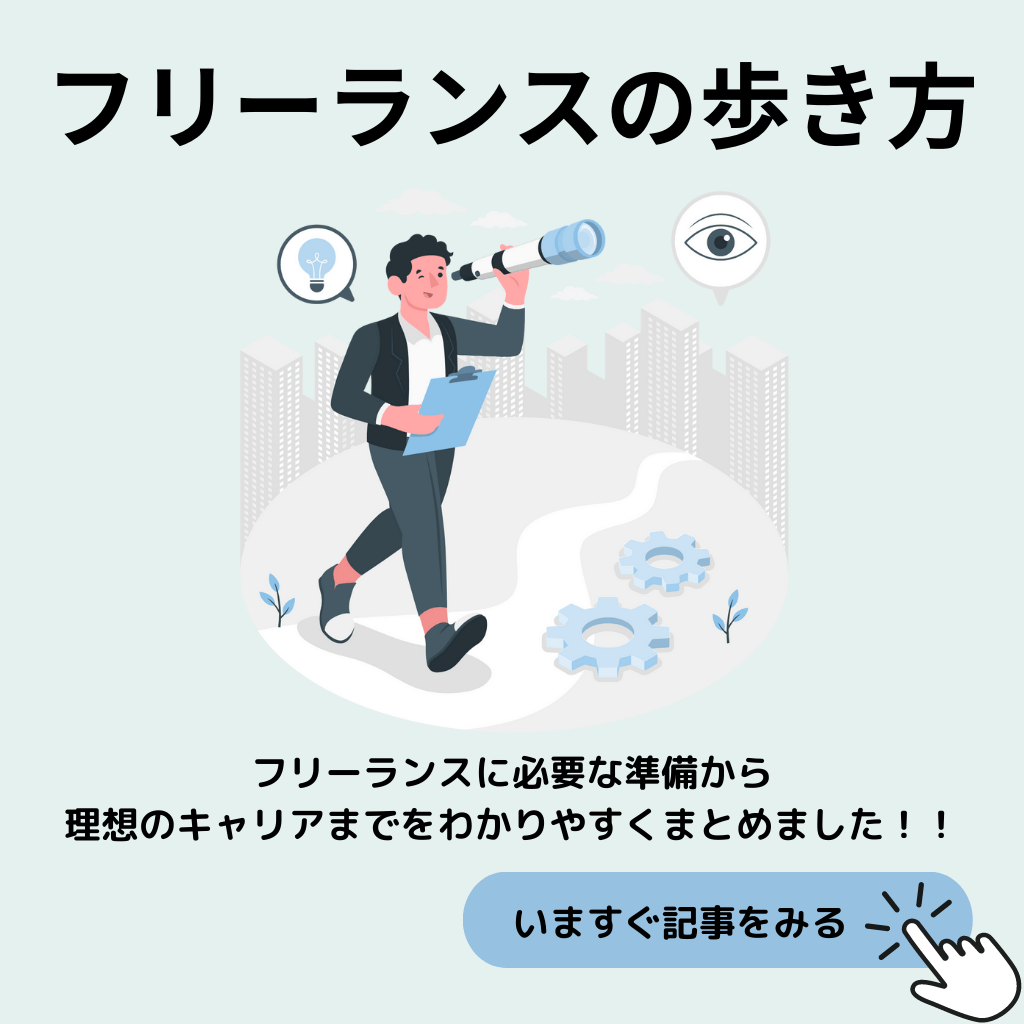・フリーランスは産休や育休が取得できるのか
・フリーランス向けの産休や育休を支援してくれる制度は
・フリーランスが産休や育休を取る場合どんな準備が必要か
フリーランスとして働くと、産休や育休を取る計画について、その間の収入をどのように保証するかについて深く悩むことがあると思います。事実、正社員とは異なり、フリーランスとして産休や育休を取るのは一筋縄ではいきません。
しかし、その一方で、実際に産休や育休を利用しているフリーランスの方々も存在しています。では、彼らはどのようにしてこれを実現しているのでしょうか。
本記事では、フリーランスが産休や育休を取得する際に活用可能な支援制度を解説します。さらに、産休や育休を取る予定のフリーランスが事前に準備しておくべき点もご紹介します。
この記事を活用して、安心して産休や育休を取得できるような計画を立てていきましょう。
フリーランスは産休や育休が取得できないのか
正社員の場合、育児・介護休業法により、特定の期間、産休や育休を取得できます。例えば、産休は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から開始でき、出産の日から翌日の8週間(6週間後に医師が就業を許可した場合は、申請により就業が可能)は働くことが制限されます。また、育休は条件がいくつかありますが、通常は子どもが1歳になるまで取得できます。
一方、フリーランスの場合、このような法律による保証はなく、産休や育休をどの程度取るかは自身で決定しなければなりません。産休や育休を長期に渡って取得すると、「全く収入が得られない」「長期の案件を途中で終了させなければならず、再就業時には新たな仕事を見つけなければならない」といった問題が生じることがあります。
その結果、出産後1ヶ月以内に働き始めるフリーランスも多いと言えます。
フリーランスは「育児休業給付金」や「出産手当金」がもらえないのか
正社員の場合、産休や育休期間中は給料の約5~7割に相当する給付金や手当金を受け取ることができます。これらは「育児休業給付金」や「出産手当金」と呼ばれるものです。
しかし、フリーランスの場合は、育児休業給付金や出産手当金の対象外であるため、これらを受け取ることはできません。
フリーランスが利用できる出産・育児支援制度
フリーランス専用の制度はないものの、出産や育児に関する支援制度はいくつか用意されています。
フリーランスが利用できる出産・育児支援制度
①出産・育児一時金
②児童手当
③子ども医療費助成
④幼児教育・保育の無償化
⑤妊婦健診費用助成
⑥国民年金保険料の免除
それぞれ具体的にどのような制度なのか、見ていきましょう。
①出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険や国民健康保険の被保険者、あるいはその扶養家族が出産した際に支払われる一時金のことを指します。出産した子ども1人あたり、42万円が支給されます。
ただし、妊娠期間が22週に満たない等、産科医療補償制度加算の対象とならない出産の場合は、出産育児一時金は39万円となります。基本的に、この一時金の申請や受取は医療機関が代行してくれます。
しかし、規模の小さい医療機関では、自分で手続きをする必要がある場合もあります。そのため、医療機関に事前に確認しておくことをおすすめします。
②児童手当
児童手当とは、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当てのことです。支給される金額は子どもの年齢や子どもの数によって変わってきます。
年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
0〜3歳未満 | 月額15,000円/人 | 月額15,000円/人 |
3歳〜小学校修了まで | 月額10,000円/人 | 月額15,000円/人 |
中学生 | 月額10,000円/人 | 月額10,000円/人 |
ただし、この制度には所得制限が設けられています。世帯主の年収が約960万円(2人の子どもを持つ専業主婦の世帯を例に)を超えると、支給額は子ども1人あたり月額5,000円になります。さらに、2022年10月からは、世帯主の年収が約1,200万円を超えると、給付対象から除外されることになります。
③子ども医療費助成
子ども医療費助成とは、医療機関で受診した際に必要となる自己負担分を補助する制度のことを指します。対象者は自治体により異なりますが、基本的には0歳から中学生、あるいは18歳までの子どもが対象となることが一般的です。
また、助成額も自治体により異なります。中には自己負担金全額を助成金として支給する自治体も存在します。詳細については、自身が居住する自治体に問い合わせてみてください。
④幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化とは、幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育などの施設において、3歳から5歳までのすべての子どもの保育料が無料になる制度のことを指します。また、0歳から2歳までの子どもでも、住民税が非課税の世帯であれば、この制度の対象となります。
ただし、各施設には保育料の上限が設定されており、この金額を超える部分は自己負担となります。また、「保育料」には通園送迎費、食材料費、行事費などは含まれていないので、その点は注意が必要です。
具体的に通園したい幼稚園や保育園が決まっている場合は、事前に施設に問い合わせてみると良いでしょう。
⑤妊婦健診費用助成
妊婦健診とは、妊娠期間中の胎児と母親の健康状態を確認するための検診です。妊娠週数の経過と共に、受診する間隔や回数が変わってきます。
妊娠週数 | 受信間隔や回数 |
妊娠~24週 | 4週間に1回 |
25週〜35週 | 2週間に1回 |
36週〜 | 1週間に1回 |
妊娠期間中、平均的に約14回の受診が必要となります。これらの受診費用の一部を補助するのが、妊娠健診費用助成制度です。
詳細な申請方法については、各自治体のホームページで確認しましょう。
⑥国民年金保険料の免除
国民年金保険料を免除してもらえる制度もフリーランスは利用できます。出産前後の一定期間は国民年金保険料が免除されます。
子ども数 | 免除期間 |
1人 | 出産予定日or出産月の1ヶ月前〜2ヶ月後までの4ヶ月間 |
2人以上(双子など) | 出産予定日or出産月の3ヶ月前〜3ヶ月後までの6ヶ月間 |
対象期間における国民年金保険料がすでに支払われていた場合でも、申請を行えば還付されます。しかし、この制度は自己申告制であり、自ら申請しなければ適用されません。
フリーランスで国民年金に加入している方は、年金事務所に申出書を提出することで申請が可能です。また、出産予定日を確認できる母子健康手帳なども必要となるため、併せて提出しましょう。
フリーランスが産休・育休によって苦しまないための対策
利用できる出産・育児支援制度があると言っても、会社員よりも負担が減るわけではありません。そのためフリーランスの場合は、自分でも対策を練っておく必要があります。
例えば以下の5つのような対策が考えられます。
フリーランスが産休・育休によって苦しまないための対策
①産休・育休中の生活設計を立てる
②出産前までに貯金をしておく
③パートナーに育休を取ってもらえないか相談する
④子どもを預けられる場所を見つける
⑤リモートワーク案件を見つける
それぞれ見ていきましょう。
①産休・育休中の生活設計を立てる
まず産休・育休を取るのであれば、その期間の生活設計を立てることが大事です。家族と話し合いの場を設け、以下のような話をしておくといいでしょう。
・子どもが生まれた場合、どれくらい出費が増えそうか
・産休・育休を取った場合、パートナーだけの収入で生活できるか
・子どもの世話はどちらがどれだけするのか
・家事はどのように割り振るか
・etc……
子どもが生まれてみたいとわからないことも多々あると思いますが、想定外のことが起きた場合どうするのかも話し合えておけると、対応に困ることを減らせるはずです。
②出産前までに貯金をしておく
出産に向けての貯蓄を心がけましょう。産休や育休中は収入が減少し、出産後は出費が増えることが予想されるためです。
まずは生活設計を立て、必要となりそうな金額を見積もります。その見積もりよりも少し多めに貯蓄しておくと、安心感を得ることができます。早期からの貯蓄は、産休や育休中の経済的な負担を軽減する助けとなります。
③パートナーに育休を取ってもらえないか相談する
パートナーが会社員である場合、育休を取得してもらうという選択肢も検討することができます。パートナーが育休を利用できれば、ある程度子育てをパートナーに任せ、自身は仕事に復帰することも可能です。
また、会社員のパートナーは「育児休業給付金」を受け取ることができる場合がありますので、パートナーと相談してみると良いでしょう。
④子どもを預けられる場所を見つける
フリーランスとして育児しながら働く予定であるなら、子どもを預けられる場所を事前に探しておくことが重要です。家族や親類、あるいは保育園などの施設を利用することを検討しましょう。
地域によっては待機児童が多く、即座に施設を利用できない場合もありますので、早めにリサーチを開始し、自身が住む地域で利用可能な施設を見つけておくことをお勧めします。
⑤リモートワーク案件を見つける
リモートワークの案件を探すことは、子育てと仕事を両立させる一つの手段となります。自宅で働くことができるので、子育てや家事と並行して働くことも可能です。
しかし、子育てと仕事の両立は容易なことではありません。出産前と同じ業務量を続けるのは厳しいかもしれません。より現実的なアプローチとしては、最初は業務量を減らし、徐々に子育てとのバランスをとる方法に慣れてから、仕事の量を増やしていくことを検討してみてください。
まとめ
フリーランスが利用できる出産・育児支援制度
①出産・育児一時金
②児童手当
③子ども医療費助成
④幼児教育・保育の無償化
⑤妊婦健診費用助成
⑥国民年金保険料の免除
フリーランスの方は、正社員のように産休・育休を取得することが難しい面があります。そうした状況を考慮に入れつつ、経済的、仕事上の安定を見つける方法をパートナーと共に話し合い、計画を立てることが大切です。
一方、フリーランスでも利用できる出産・育児に関する支援制度も存在します。全てを利用するわけではなくても、子育ての負担を少しでも軽減できる手続きは活用してみてください。そのために、自分が申請可能な制度を調査し、必要な手続きを進めることをお勧めします。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /