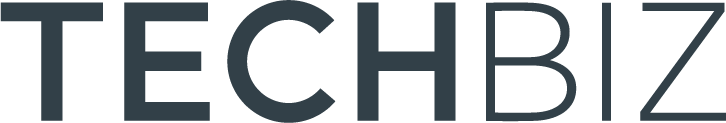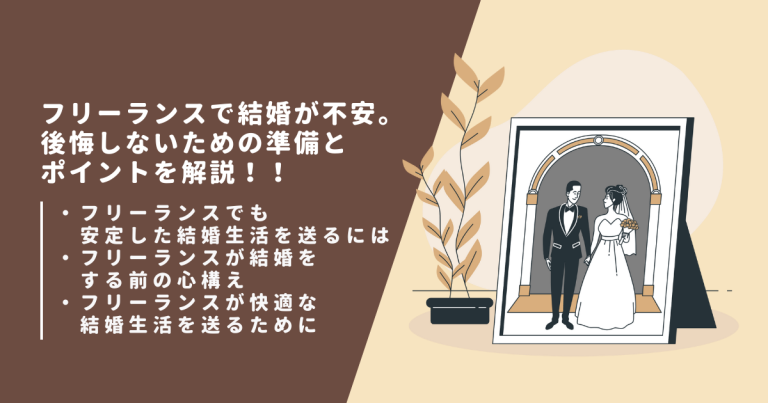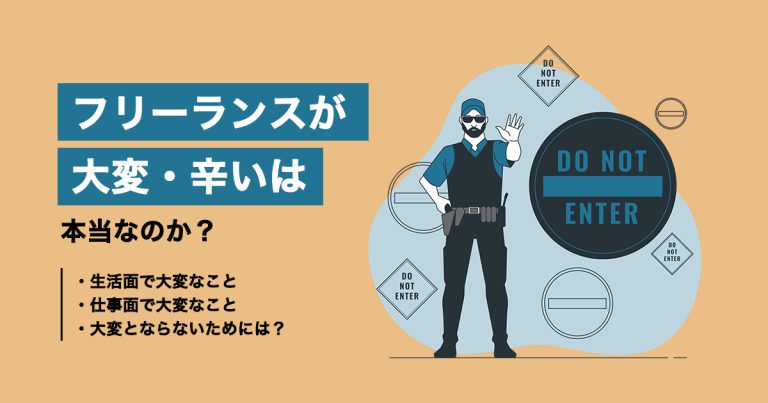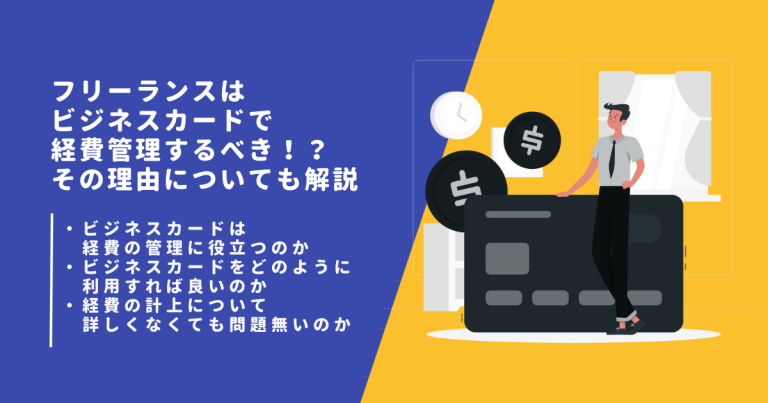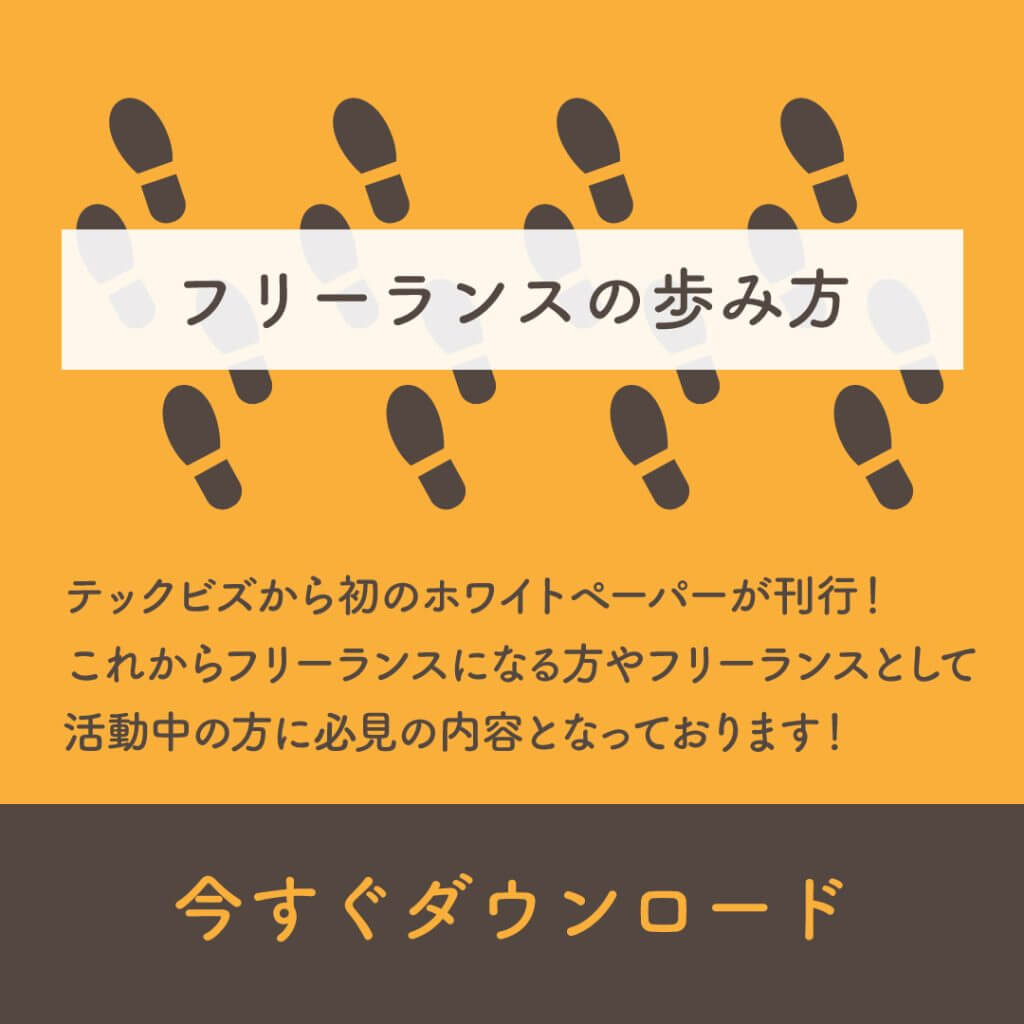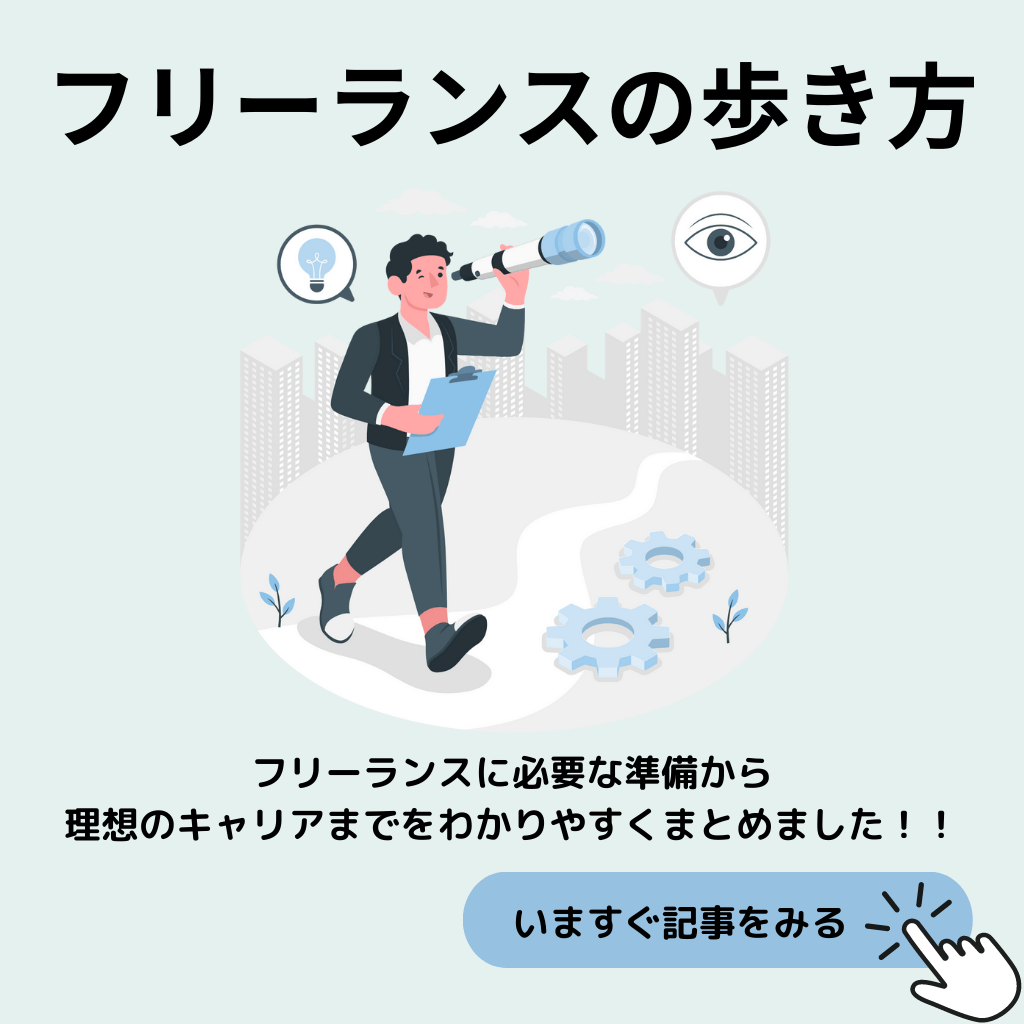・フリーランスでも安定した結婚生活を送るには
・フリーランスが結婚をする前の心構え
・フリーランスが快適な結婚生活を送るために
フリーランスとして働くことによる結婚への不安を感じていませんか?フリーランスの仕事は自由度が高い一方で、不安定さも伴います。そのため、「この状況で本当に結婚が可能なのか」と疑問を抱くこともあるでしょう。
しかし、結婚をあきらめるのはまだ早いです。フリーランスでも結婚している人はたくさんいますし、結婚に向けて適切な準備をすれば、幸せな結婚生活を送ることができます。
そこで、今回はフリーランスが結婚に向けて準備すべき事項や結婚するためのポイントについてご紹介します。この記事を参考に、幸せな結婚生活への一歩を踏み出してみてください。
フリーランスでも安定した結婚はできる
フリーランスでも一定数の方は結婚しています。
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会が2020年の「フリーランス白書」の調査結果によると、フリーランスで配偶者がいる人は61.8%で半数を超えていました。
参照:フリーランス白書 https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2020/06/2020_0612_hakusho.pdf
このことから、フリーランスでも結婚できないわけではないことがわかります。とはいえ、フリーランスで本当に結婚できるのか不安に思われる人もいますよね。
具体的にどのような不安があるのか、次章で紹介していきます。
フリーランスが結婚に対して不安になること
ここからフリーランスが結婚に対して具体的にどのような不安を抱いているのか見ていきましょう。フリーランスは主に以下のような不安を抱えていると言えます。
フリーランスが結婚に抱く不安
①収入が不安定になりがち
②社会的信用を得るのが難しい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
収入が不安定になりがち
収入の不安定さが、フリーランスが結婚に抱く最大の不安と言えます。「フリーランス白書2020」の調査結果によると、フリーランスが抱える課題は?という質問の回答で一番多かったのは、「収入がなかなか安定しない(55.1%)」でした。
参照:フリーランス白書https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2020/06/2020_0612_hakusho.pdf
フリーランスとして働く人々の大部分は、毎月一定の給与を得ることは少なく、仕事の量や成果によって報酬が変動します。クライアントの事情により、発注される仕事が突然減ったり、なくなったりすることもあり、安定性は保証されません。会社員時代よりも収入が多い場合でも、いつ収入が減るかわからないという不安を抱えている人も多く、結婚を考える際にも不安を感じる人が多いようです。
フリーランスとして働く人々の大部分は、毎月一定の給与を得ることは少なく、仕事の量や成果によって報酬が変動します。クライアントの事情により、発注される仕事が突然減ったり、なくなったりすることもあり、安定性は保証されません。会社員時代よりも収入が多い場合でも、いつ収入が減るかわからないという不安を抱えている人も多く、結婚を考える際にも不安を感じる人が多いようです。
社会的信用を得るのが難しい
フリーランスの結婚における不安の一つは、社会的な信用を得ることが難しいという点です。社会的な信用が得られないと、子供の教育費や家の購入の際にローンが組めない可能性が高くなります。たとえ家が賃貸でも、フリーランスの経歴が短いか、年収が極端に低い場合は審査に通らないこともあります。結婚相手が会社員であれば、この問題はあまり心配する必要はありません。フリーランス同士や専業主婦(主夫)を考える場合には、この課題は見逃せません。このような背景から、結婚に踏み出せないフリーランスも存在するようです。
フリーランスが安定した結婚するために意識しておきたいポイント
フリーランスが収入や社会的信用といった面で結婚に対する懸念を持つ場合、その要素は結婚を望む人々にどの程度重要視されるのでしょうか。
リクルートブライダル総研による2020年7月の調査、「婚活実態調査2020(3次調査)」によれば、全国の20~49歳の男女を対象に現在独身者を調査した結果、新型コロナウイルスの影響を受けて注目されるようになった結婚の条件として、経済面を除く部分では、「パートナーとの距離感」、「健康状態」、「価値観の一致」という項目が上位に位置していました。
これにより、経済的安定を望む人々もいる一方で、「パートナーとの関係性」にも配慮している人が多いことが明らかになります。フリーランスとして活動する人々は、サラリーマンと比べて、パートナーと過ごす時間が増える傾向にあります。
したがって、仕事とパートナーとの時間のバランスをしっかり保つ、自分だけの都合に基づいたスケジュール設定ではなくパートナーの都合も考慮に入れる、といったことを考えながらパートナーとの共有時間を過ごすことが重要でしょう。
フリーランスが結婚前に準備しておきたいこと
上記のデータから、フリーランスが結婚前に準備しておきたいことをここでまとめておきたいと思います。主には以下のような点が挙げられるでしょう。
フリーランスが結婚前に準備しておきたいこと
①安定した案件の確保
②結婚にかかる費用の把握
③結婚後の生活費の把握
④パトーナーと合算した収入の把握
⑤お互いのライフスタイルの共有
⑥将来についての話し合い
順番に見ていきましょう。
安定した案件の確保
フリーランスとして活動する際には、単発の仕事だけでなく、長期間にわたる案件を確保することが重要です。特に、結婚を考える際には安定した仕事があることで、より安心して新たな生活に進むことが可能となります。
そんなフリーランスの方々にお勧めしたいのが、「テックビズフリーランス」です。ここでは独立経験を持つコンサルタントが、あなたのキャリアプランや希望する条件に合った案件を紹介してくれます。
また、「テックビズフリーランス」は案件の紹介だけでなく、仕事が決まった後のサポートも充実しています。フリーランス向けのサービスや税務面での相談にも応じてくれるため、結婚後も安心して働くことが可能です。
安定した仕事を確保することは、フリーランスとしての生活をより豊かにし、安心して結婚生活に進むことをサポートします。是非、「テックビズフリーランス」を活用し、フリーランスとしてのキャリアを築き上げてください。
結婚にかかる費用の把握
結婚式や披露宴など、結婚にかかる費用の全体像を理解しておくことが重要です。フリーランスの方は収入が一定でないため、適切な予算計画と余裕を持った費用見積もりが求められます。
お祝い金で全てをまかなうつもりかもしれませんが、新型コロナウイルスの影響で予想以上に参列者が少なくなる可能性もあります。結婚後の生活を圧迫しないよう、結婚にかかる費用は前もってしっかりと検討しましょう。
結婚後の生活費の把握
結婚して生活を共有すると、一人暮らしのときと比べて出費は増大します。新居への移転費用、新たな家具の代金、食費、水道・光熱費など、予想以上に出費が増えることもあります。
二人で生活をする際に毎月どれくらいの費用が必要なのかを事前に把握しておきましょう。また、家族が増えた場合や収入が減少した場合を考慮に入れて、どの程度の金額を貯蓄に回すことができるのかも理解しておくと、より安心できるでしょう。
パトーナーと合算した収入の把握
結婚後の収入総額を把握するためには、パートナーの収入も合わせて考慮する必要があります。結婚後の生活費を見越して、現在の収入がそれに見合っているか、足りない場合にはどう対処するかなど、事前にパートナーと話し合っておくと、生活におけるトラブルを防げます。
「収入が足りないなら仕事を増やそう」、「パートナーにも協力してもらおう」などと考えることも大切ですが、新しい仕事を見つけるまでには時間が必要な場合もあります。後々のトラブルを避けるためにも、結婚前にこのような話し合いをすることをお勧めします。
お互いのライフスタイルの共有
パートナーとのライフスタイルの共有も大切な要素です。すでに同棲している場合は、お互いの生活習慣を大まかに理解しているでしょう。しかし、同棲せずに結婚を考えている場合は、事前に話し合っておくことをお勧めします。
フリーランスの方々は仕事のスケジュールや休日を自由に決めることができ、それが自分たちのライフスタイルに適しているかもしれません。だからと言って、それがパートナーにとっても最適なライフスタイルであるとは限りません。
結婚前にこのような話し合いを行い、両者にとって快適なライフスタイルを見つけるよう調整しておくことで、共同生活が始まった後のトラブルを避けられます。既に同棲している場合でも、再度、何か不満な点がないかなどを確認し、共有しておくことで、より良い関係を築けます。
将来についての話し合い
子供の出産や収入減少、病気など、未来の様々な事情についても、パートナーとの話し合いを持つことが大切です。もともと収入が不安定なフリーランスの立場からすれば、ライフイベントが起きるとさらに不安定さが増す可能性があります。
子どもが生まれると、金銭的な負担も時間的な負担も増大します。また、病気により働けなくなると、収入がまったく得られなくなる可能性もあります。そうした状況に備えてどう対応するか、事前にパートナーと話し合い、対策を立てておくことをおすすめします。
結婚後のフリーランスの節税について
一人暮らしの時と結婚後では、節税方法も変わってきます。なぜなら、結婚後の方が活用できる節税の種類が増えるからです。なかでも、下記の知識は身に付けておきましょう。
結婚後のフリーランスの節税方法
①青色事業専従者給与
②扶養控除
③パート収入に対する節税
順番に解説していきます。
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与とは、配偶者(パートナーなどの親族)に事業を手伝ってもらった時に支払う給与のことです。家族に支払う予算ではありますが、必要経費に計上できますので節税になります。
ただし青色事業専従者給与として計上する時は、以下のようないくつかの条件があります。
青色申告者と生計を共に送っている配偶者・親族にしか適用されない
事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している
労働の対価として支払われた金額のみ認められる(過大計上はNG)
確定申告の時だけではなく、事前に必要な手続きもありますので、早めに考えておくようにしましょう。
扶養控除
扶養控除とは、扶養者と一緒に生活を送っている納税者が利用できる所得控除です。最大で63万円の控除が認められています。ここでの扶養者とは下記の条件に全て当てはまっている人を指します。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)。または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁
パートナーの他に子どもや親なども扶養控除に該当する場合があります。
パート収入に対する節税
パートナーがアルバイトやパートとして働く場合もあります。その場合、基準となっている収入に満たなければ課税されません。
仮に配偶者の収入がパートの収入のみで年間103万円未満であれば所得税は0円です。また、配偶者の年間所得が38万円以下であれば「配偶者控除」の対象となります。
パートナーの収入・所得に応じて利用できる節税が変わるため、覚えておきましょう。
まとめ
フリーランスの結婚事情
①結婚している人は半分以上いる
②収入面と社会的信用が結婚に対して抱える不安
③経済面以外ではパートナーとの距離感も重要
フリーランスでも結婚している人はたくさんいますし、会社員と同じぐらい幸せに暮らしている人もいます。収入面、社会的信用など不安要素もあるかもしれませんが、うまく対策を立てていけば問題なく結婚することはできるでしょう。
ひとりで考えるのは不安、誰かに相談したいという人は、「テックビズフリーランス」の利用を検討してみてください。独立経験のあるコンサルタントがあなたのライフスタイルに合わせて仕事やフリーランス向けのサービスなどを提案してくれます。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /