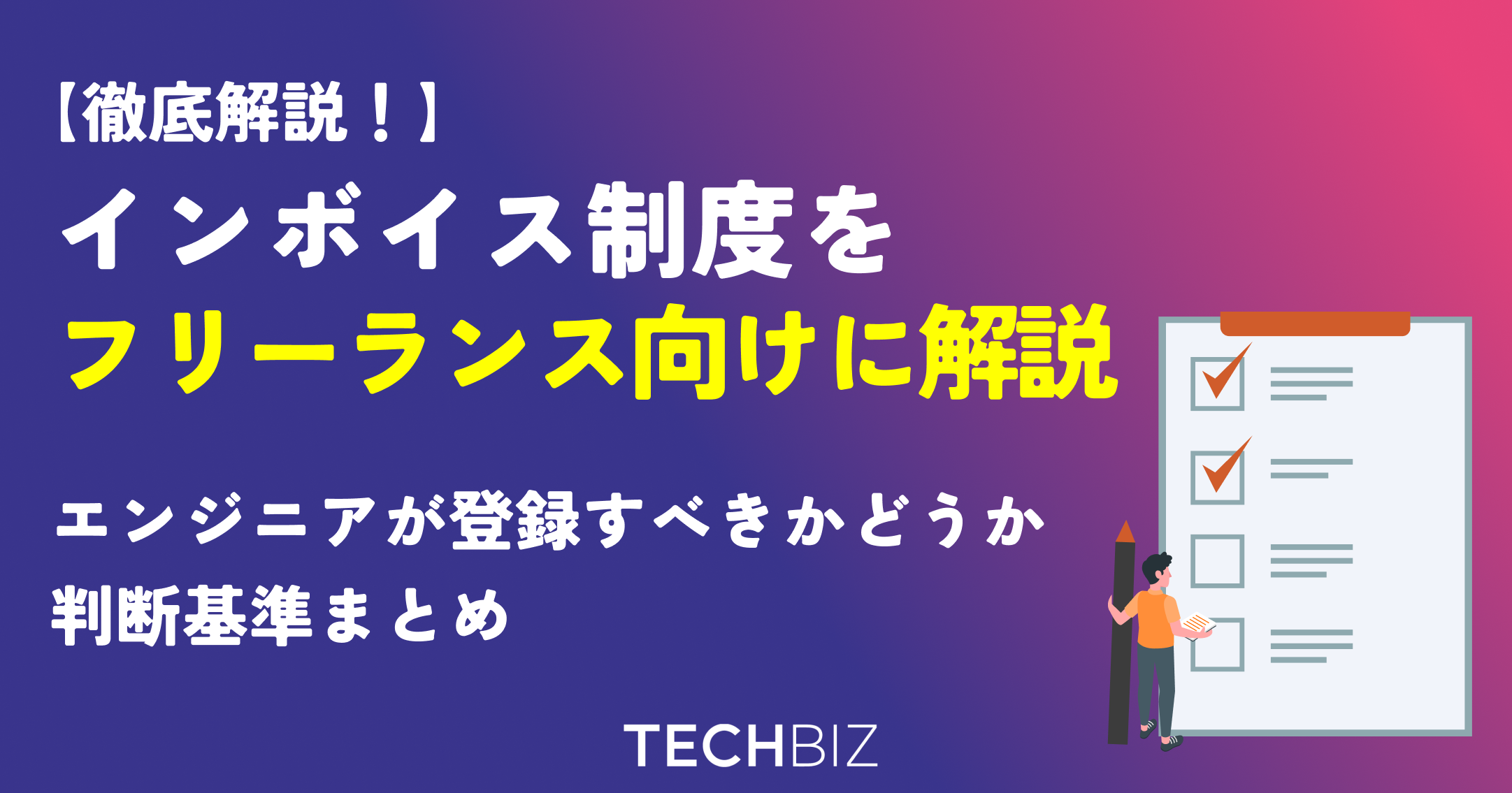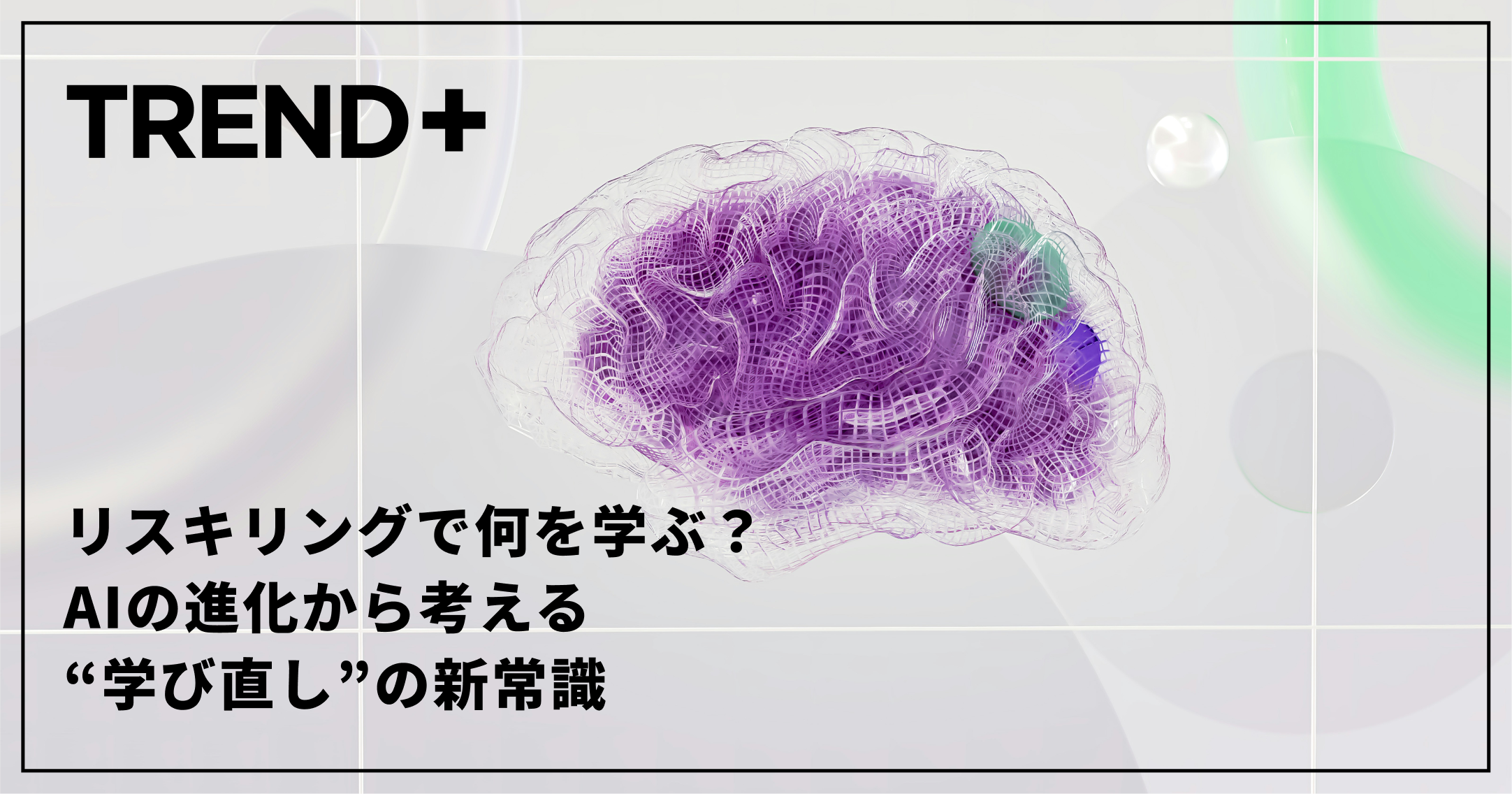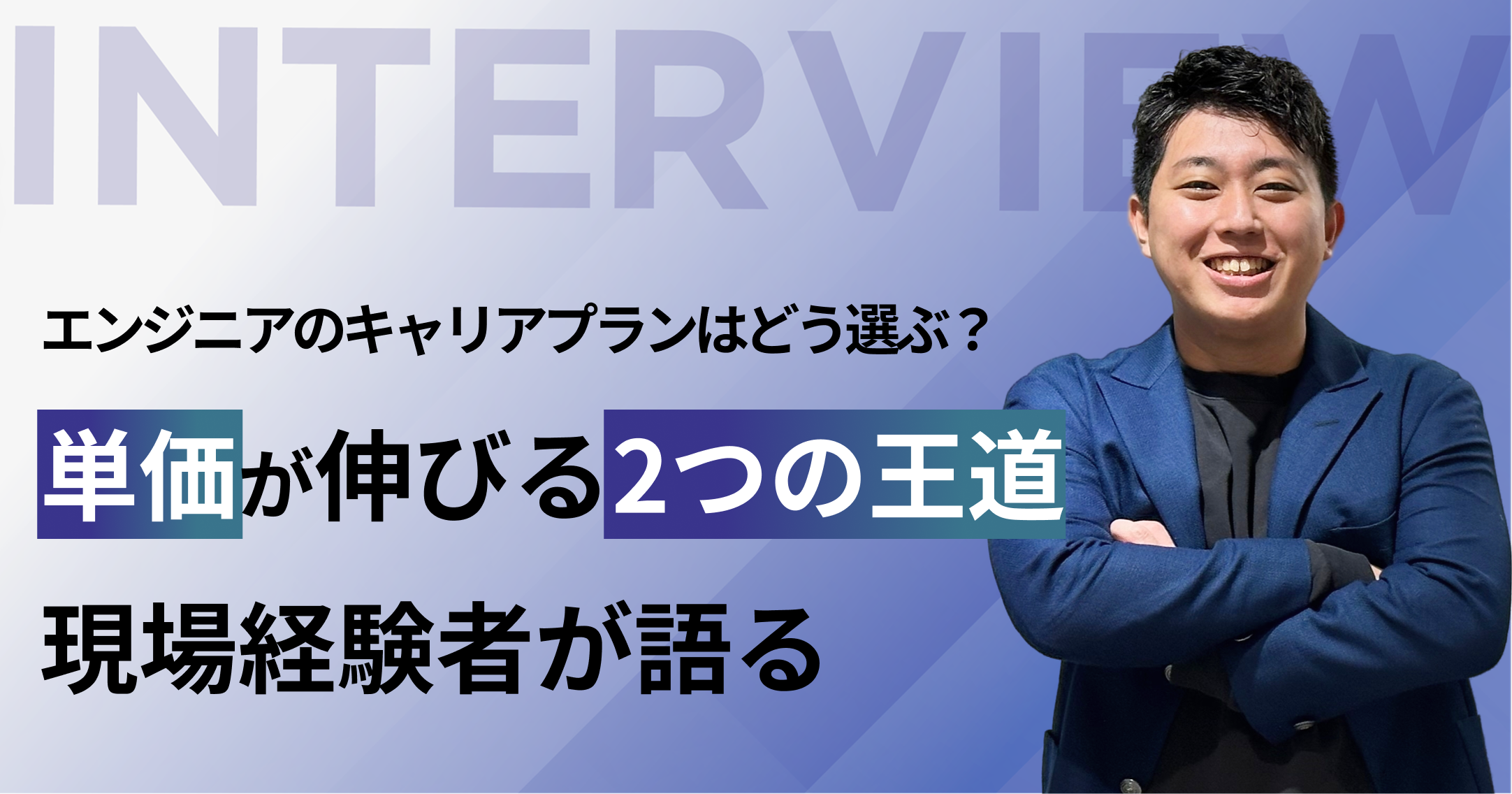「HUMAN CAPITAL+」とのコラボ第二弾として、同メディアのインタビュー記事をご紹介します。
兄弟メディアであるHUMAN CAPITAL+の記事を通して、今回は企業がSES・SIer・フリーランスをどのように見ているのか、そしてなぜ「SESやめとけ」と言われるのかというテーマに注目。
採用・契約の裏側を知ることで、フリーランスとして“選ばれる人材”になるために必要な視点が見えてきます。
本記事では、テックビズ営業本部のエグゼクティブコンサルタント・栗林亮佑さんへのインタビューをもとに、SES・SIer・フリーランスそれぞれの“構造的な違い”を解説。
営業のプロだからこそ語れる、“現場のリアル”と“キャリアの選択軸”をお届けします。
ITフリーランスのキャリア相談・案件探しはTECHBIZ
マッチする案件を見つけるために必要なものは?
「TECHBIZメディア」の兄弟メディアである「HUMAN CAPITAL+」は、“「人的資本の社会的共有」を通して企業に新しい価値をプラスする”情報発信サイトです。
同メディアでは、法人目線から「フリーランス人材をどう評価し、どう活用しているか」をテーマにした記事が掲載され、企業とフリーランス双方が“良い関係”を築くためのヒントが紹介されています。
今回はコラボ企画第二弾として、HUMAN CAPITAL+に掲載されたインタビュー記事
「SESとSIerの違いで、エンジニアのスキル面に差はあるの?営業のプロに聞いてみた」
をもとに、“SESやめとけ”という言葉の背景にある構造的な問題と、フリーランスが選ばれるための考え方を解説していきます。
「SESやめとけ」と言われる理由は?

「SESはやめとけ」「SIerは古い」──
SNSや掲示板で、そんな言葉を目にしたことがある人は少なくありません。
働く環境や案件の種類が多様化する中で、
なぜSESやSIerといった働き方がここまで誤解されやすいのか。
テックビズ営業本部でエグゼクティブコンサルタントを務める栗林亮佑さんは、
その背景に「個人の能力ではなく、業界の“構造的な問題”がある」と語ります。
栗林さん:SES・SIer・フリーランスの仕組みに共通しているのが、“案件ガチャ”のような側面があるところです。言ってしまえば、温厚でホワイトな案件に入れるのか、それとは真逆のような厳しい案件に入るのかどうかも、働くエンジニアの“運”です。とくにSESやSIerの社員の場合だと、どれだけ自分に合わない業務や条件だとしても、一度配属された案件を変えてもらうのはなかなか難しいところがあります。
SESとは、クライアント企業のプロジェクトに常駐して働くスタイルです。配属先や業務内容は、所属企業の契約状況や営業戦略によって決まることが多く、エンジニア本人の希望とは異なる現場にアサインされるケースも珍しくありません。
また、案件の契約期間が長期に及ぶこともあり、途中で環境を変えたいと思っても、柔軟に動けない構造を持っています。
そのため、働き方に“閉塞感”を覚える人が一定数出てしまうのです。
こうした構造的な課題が重なり、SESやSIerという働き方が“ネガティブに見えやすい”状況をつくり出しています。
ただし、これは「働く側が悪い」わけでも「企業が悪い」わけでもありません。
両者の関係性をどう設計するかという、業界全体の仕組みの話なのです。
次のセクションでは、同じIT業界におけるSES・SIer・フリーランスの立ち位置を整理し、スキルや評価の実態を見ていきます。
SES・SIer・フリーランス──スキルの差はほとんどない。
「SES出身だとスキルが低く見られる」
「フリーランスは実力がある」
──そんな言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
現場で働くエンジニアの間でも、SES・SIer・フリーランスの“スキル格差”を語る声は少なくありません。
しかし実際には、技術力そのものに大きな差はないといいます。
栗林さん:結論から言うと、そんなに変わらないと思います。SESとSIer……そしてフリーランスを比較したとき、スキル面にそこまで大きなバラつきはないかなと。とくにSESとフリーランスに関しては働き方が違うだけで、表面的な部分や“人”を見ると、類似する部分が多い気がします。
SESは、クライアント企業のプロジェクトに常駐して開発支援を行う。SIerは上流工程を担い、設計やマネジメントを中心に動く。フリーランスは特定の領域に特化し、必要な技術をピンポイントで提供する。
それぞれの立ち位置は違っても、日々の業務で使う技術・ツール・開発言語はほとんど変わりません。
では、企業はなぜそれぞれを使い分けるのでしょうか。
栗林さんは、その違いをとても分かりやすい比喩で説明してくれました。
栗林さん:個人的には、SIerが“百貨店”、SESが“コンビニエンスストア”、フリーランスが“専門店(メーカー)”のような印象です。
企業がまだ課題を明確にできていない段階では、“なんでも揃う百貨店”のようなSIerに依頼してプロジェクト全体を設計してもらう。
一方、必要な機能やスキルが明確な場合は、
スピードとコストのバランスが取れる“コンビニ的”なSESを選ぶことが多いといいます。
そして、「この領域の専門知識が必要」と明確に分かっているときには、“専門店”であるフリーランスを指名する。
つまり、求められているのはスキルそのものではなく、
そのスキルをどんな場面で、どんな価値として提供できるかという“立ち位置の違い”なのです。
働き方 | 企業から見た特徴 | 求められる役割 |
|---|---|---|
SIer(百貨店) | 全体設計・管理を任せられる | プロジェクト全体の把握力と調整力 |
SES(コンビニ) | 迅速でコスト効率が良い | スピードと柔軟性 |
フリーランス(専門店) | 特定分野に強みを持つ | 専門性と即戦力性 |
栗林さん:構造的な部分に異なるところがあるだけで、働いてる人自体を見ると、そんなに変わらない印象があります。(中略)現在はそれぞれ立ち位置が異なる状態ですが、今後はSES・SIer・フリーランスが横一直線(の同じ立ち位置)で見られるようにもなっていくのではないかと思います。
スキルの差ではなく、“役割”の違い。
どの立場で働くとしても、エンジニアとしての価値は変わりません。
だからこそ、自分の強みをどこで発揮したいのか──
その軸を持つことが、キャリアを伸ばす第一歩なのです。
今回「TECHBIZメディア」とのコラボでご紹介したインタビュー記事は以下になります。
“選ばれる働き方”が変わりつつある
SES・SIer・フリーランス。
この3つの働き方は、いま改めて“再定義”の時期を迎えています。
近年のデータを見ると、日本国内のIT人材市場は大きく変化しています。
経済産業省の調査によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると試算されています。
(出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査」2023年)
この人材不足を補う手段として、企業が「多様な働き方の人材」を活用する流れが加速しています。
正社員だけでなく、契約社員、業務委託、フリーランスなど、
“プロジェクト単位で専門スキルを持つ人材”の活用が当たり前になりつつあります。
また、グローバル調査会社の Grand View Research によると、日本のフリーランス・プラットフォーム市場は2024年時点で約1億3,760万米ドル(約190億円)、
2030年までに約5億4,450万米ドル(約750億円)規模に拡大すると予測されています。
(出典:Grand View Research「Japan Freelance Platforms Market Size Report, 2030」)
この数値は、フリーランスが急増しているというよりも、
企業が“柔軟に働ける人材”を必要としているという時代の変化を示しています。
一方で、SESやSIerのような組織的な働き方も依然として重要な役割を担っています。
特に大規模プロジェクトでは、安定したチーム体制や統制力を維持できる強みがあります。
つまり、市場が求めているのは「どの働き方か」ではなく、
その人がどの立ち位置で価値を発揮できるかという観点なのです。
働き方が細分化され、キャリアの選択肢が広がった今、大切なのは「どの形で働くか」を選ぶことではなく、
「自分はどんな環境で力を出したいのか」を考えること。
“選ばれる働き方”とは、流行を追うことではなく、自分のスキルを理解し、それを最適な形で社会に提供できるスタイルを見つけること。その姿勢こそが、時代の変化に左右されないキャリアの軸を作ります。
最近停滞を感じたり、今のままで大丈夫かなと働き方に不安を感じる方は、TECHBIZのコンサルタントに相談してみてください。

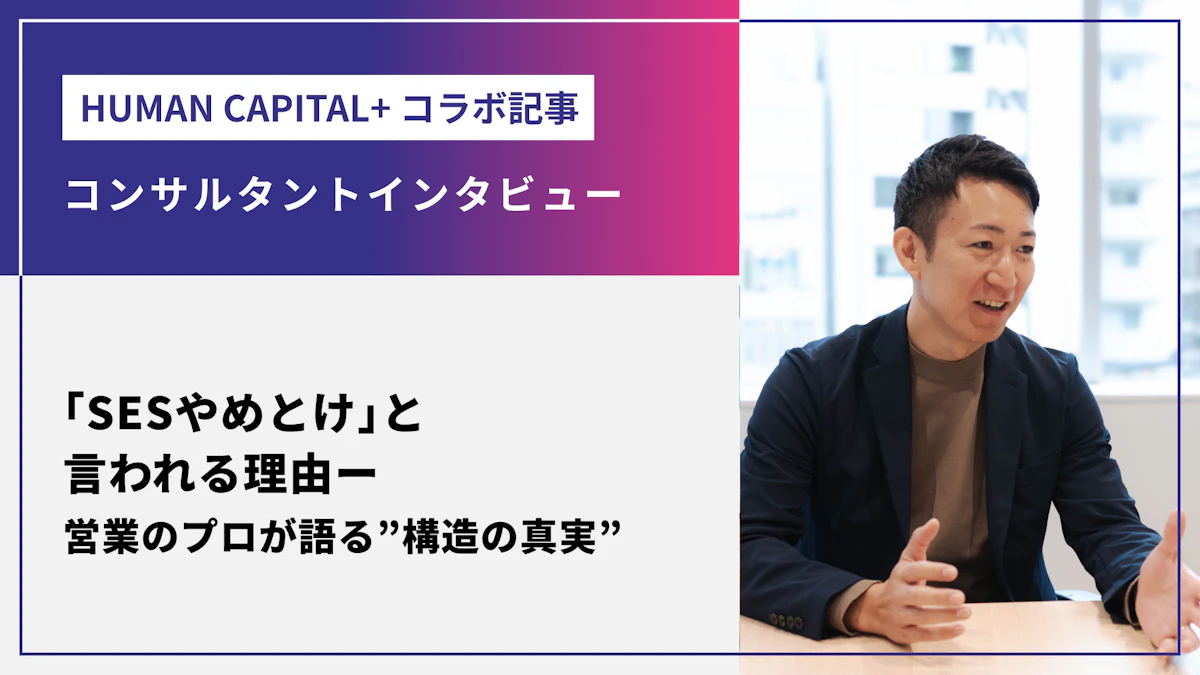
.png)