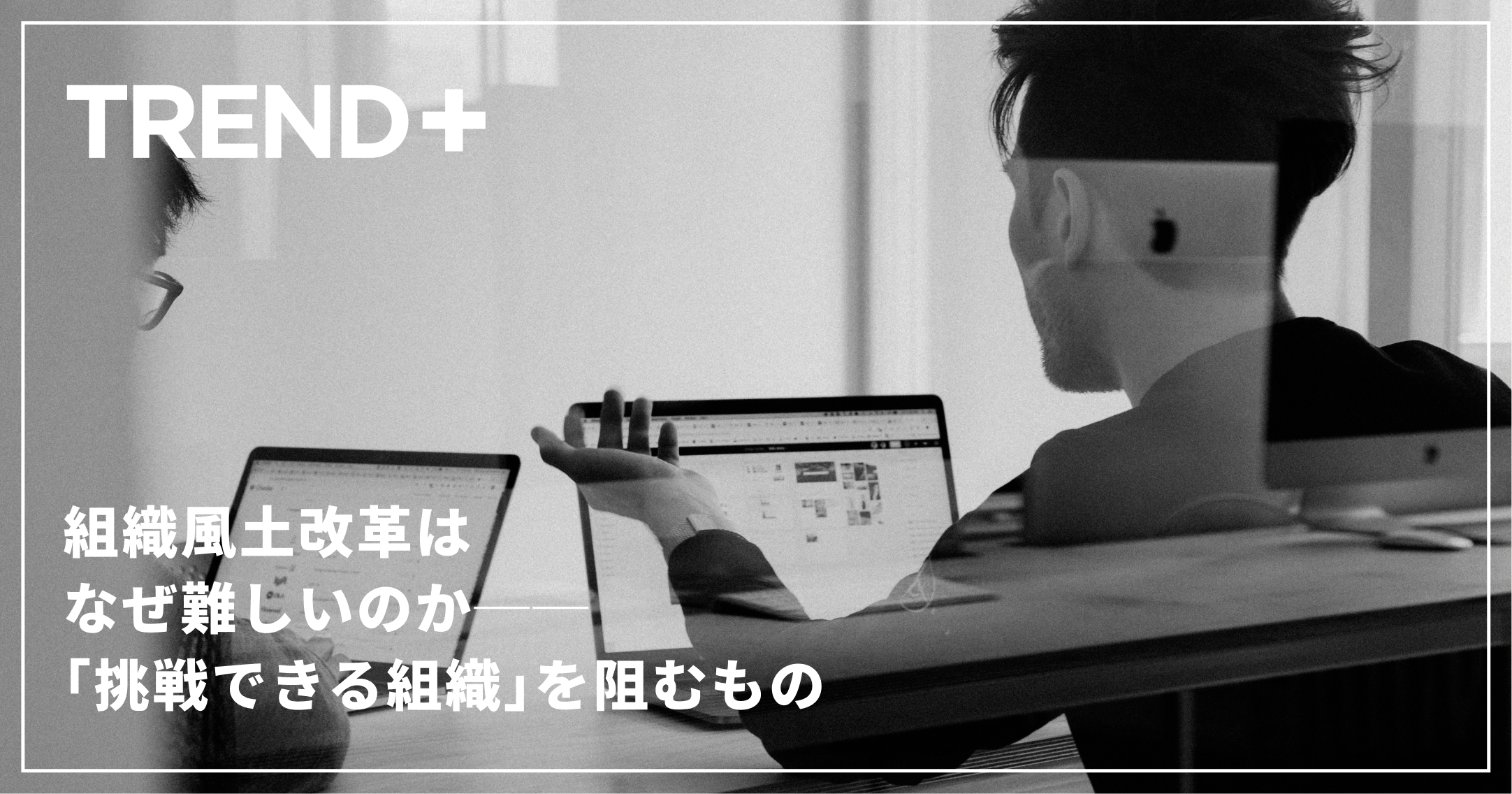「フリーランスって法人化すると何が変わるの?」
「個人事業主から法人化するタイミングは?」
「法人化の手続きや費用は?」
このような疑問を持つフリーランスの方は多いでしょう。
実際、フリーランス(個人事業主)にとって法人化は必須ではありません。
しかし、事業の拡大や節税、社会的信用の向上など、法人化によって得られるメリットは大きいです。
一方で、税金や社会保険の負担増など、デメリットや注意点も存在します。
本記事では、フリーランスが法人化する際のメリット・デメリット・最適なタイミング・手続きの流れをわかりやすく解説します。
将来的に法人化を検討している方は、判断材料としてぜひ参考にしてください。
〜税務や生活サポートも充実〜
ITフリーランスの総合パートナーTECHBIZ
フリーランスの法人化とは
フリーランスの法人化とは、現在の個人事業を廃業し、会社を設立して法人として事業を行うことです。
つまり、「一人社長」として株式会社や合同会社を設立することを指します。
法人を設立することで、事業の信用度や税制面の扱いが変わり、
所得税・法人税・社会保険などの制度が適用されるようになります。
この変化こそが「法人化の最大の分岐点」です。
フリーランスが法人化するメリット6選
「法人化=節税」というイメージを持つ方も多いですが、
実際にはそれだけでなく、信用・税制・リスク分散など多方面にメリットがあります。
社会的信用を得ることができる
フリーランス(個人事業主)の場合、契約先からの信用は「個人の実績」に依存します。
一方、法人化を行うと、会社としての実在性が登記簿や法人番号によって明確になり、
社会的信用が大きく向上します。
具体的には、以下のような場面で信頼度の差が生まれます。
- 銀行や金融機関での融資審査が通りやすくなる
- 大手企業との契約・取引がしやすくなる
- 事務所や設備などの賃貸契約がスムーズになる
- 法人名義のクレジットカードを作成できる
法人化によって「経営の安定性」が可視化されるため、事業拡大や資金調達を目指すフリーランスにとっては大きなメリットとなります。
消費税の納税が最長2年間免除される
フリーランスが法人化する大きなメリットの一つが、消費税の免税制度です。
資本金1,000万円未満の法人として設立すると、原則として設立初年度の消費税が免除されます。
さらに条件を満たせば、最大2年間免除となるケースもあります。
免除対象となる主な条件は以下の通りです。
- 設立初年度の課税売上高が1,000万円以下
- 設立2期目の特定期間(6ヶ月)の売上・給与支払額がそれぞれ1,000万円以下
- 設立1期目が7ヶ月以下の場合
これにより、フリーランス時代に比べて手元資金を確保しやすくなるのが大きな利点です。
ただし、近年導入されたインボイス制度との関係で免税の扱いが変わる可能性もあるため、
法人化を検討する際には税理士に相談しておくと安心です。
決算期を自由に選べる
個人事業主は、1月から12月までを会計期間とするため、確定申告の時期が常に固定されています。
しかし、法人化すると、決算期を自由に設定できるようになります。
たとえば、繁忙期を避けて決算を設定したり、
売上や経費の見通しに合わせて決算月を変更することが可能です。
これにより、会計処理や納税のスケジュールを事業計画に合わせて最適化できます。
また、決算期を柔軟に設定できることで、節税対策や資金繰りの調整も行いやすくなります。
経営のコントロールを高めたいフリーランスにとって、非常に大きな自由度といえるでしょう。
退職金や役員報酬を経費として計上できる
法人化すると、自分への報酬を「役員報酬」として支払う形になります。
これは法人の経費(損金)として計上できるため、節税効果が期待できます。
さらに、将来的には「退職金」を支給することも可能です。
退職金は個人の所得税が優遇されており、長期的に見ると税負担の軽減につながる仕組みです。
このように、法人化によって所得税と法人税を分離し、
経営判断で報酬設計を行える点は、個人事業主にはない大きな利点です。
ただし、役員報酬の設定には注意が必要です。
報酬額を高くしすぎると社会保険料の負担が増え、
低くしすぎると所得控除の恩恵が減る可能性もあるため、
税理士などの専門家と相談しながら最適な水準を決めましょう。
リスクの分散ができる(有限責任)
フリーランス(個人事業主)の場合、事業で発生した債務や損害について、個人の資産で無限に責任を負う必要があります。
そのため、万が一トラブルや損失が発生した場合、自己資産を失うリスクがあります。
一方で、法人化すると責任範囲が有限(有限責任)になります。
つまり、法人が負う損失は「会社の資産」までに限定され、個人の財産は保護されます。
この「有限責任」という仕組みは、事業を継続的に行ううえでのリスクヘッジとなり、
精神的にも経営の安定感を得られるポイントです。
経費計上の幅が広い
フリーランス時代にも、青色申告を活用すればある程度の経費計上は可能でした。
しかし、法人化することで経費として認められる範囲が大幅に広がるのが大きな特徴です。
法人は、交際費や通信費、車両費、福利厚生費など、
事業運営に関連する幅広い支出を経費にすることができます。
たとえば、資本金1億円以下の法人であれば、
交際費を年間800万円まで全額損金算入することが可能です。
このように、法人化によって経費の自由度が上がり、結果的に税率を抑える効果が得られます。
しっかりと経理管理を行うことで、手元資金を増やし、より効率的な資金運用ができるでしょう。
フリーランスが法人化するデメリット4選
メリットの裏には、当然ながらデメリットも存在します。「法人化すればすべて解決」と思い込むのは危険です。
設立費用と維持コストがかかる
フリーランス(個人事業主)として開業する際は、開業届を提出するだけでほとんど費用がかかりません。
しかし、法人化の場合は会社を設立するために一定の初期コストが発生します。
株式会社を設立する場合、登記費用や定款認証料、印紙代などを合わせて約20〜25万円前後が必要です。
たとえば、定款認証手数料5万円、登録免許税15万円、収入印紙代4万円が一般的な目安です。
さらに、設立手続きを専門家(司法書士・行政書士・税理士など)に依頼する場合は、+10万円前後の報酬が発生します。
自分で手続きを行うことも可能ですが、書類の準備や法的知識が求められるため、時間的負担も少なくありません。
また、法人設立後も税理士顧問料、会計ソフト費、決算申告料などの維持コストが毎月・毎年かかります。
これらを考慮すると、法人化によって節税効果が得られるかどうかは、売上や利益規模とのバランスで判断することが重要です。
給与(役員報酬)を自由に変えられない
個人事業主は、売上から経費を引いた残りを自由に使うことができます。
しかし、法人化すると自分の収入は「役員報酬」として定める必要があり、毎月の給与を自由に変動させることができなくなります。
役員報酬は会社設立から3ヶ月以内に決定し、その後は基本的に1年間変更できません。
年度途中で売上が減少した場合でも、報酬額を自由に下げることはできず、税務上の扱いに注意が必要です。
また、会社の資金を私的に使用すると「横領」や「利益流用」と見なされるリスクもあります。
つまり、法人化後はお金の使い方に対する自由度が下がるということです。
フリーランス時代のように柔軟に資金を動かしたい人にとっては、法人化によって資金管理が煩雑になり、心理的な制約を感じる場合もあります。
赤字でも法人住民税を支払う必要がある
フリーランス(個人事業主)は、年間の所得がマイナス(赤字)の場合、所得税を支払う必要がありません。
しかし、法人の場合は赤字でも「法人住民税(均等割)」の支払い義務があります。
たとえば、資本金1,000万円以下の小規模法人でも、毎年約7万円前後の法人住民税を納める必要があります。
東京都や大阪府など自治体によって金額は異なりますが、利益が出ていなくても一定の税金が発生する点は注意が必要です。
事業が安定して利益を生み出せる段階であれば問題ありませんが、
立ち上げ初期や業績が不安定な時期には、この固定的な税負担が経営を圧迫するリスクもあります。
「赤字でも税金がかかる」という点は、法人化を検討する際に見落とされがちな要素です。
社会保険の負担が増える
法人になると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務化されます。
これは従業員が1人でもいる法人に適用され、一人会社であっても例外ではありません。
社会保険料は、従業員と会社で折半する仕組みですが、代表者一人の法人の場合、実質的には全額を自分で負担することになります。
さらに、役員報酬を高く設定すればするほど、社会保険料も増加します。
たとえば、月報酬50万円の場合、社会保険料の負担は月額約7〜8万円前後になるケースもあります。
年間で考えると、個人事業主時代の国民年金・国民健康保険よりもかなり高い負担となります。
もちろん、社会保険に加入することで
- 家族を扶養に入れられる
- 将来の年金受給額が増える
- 傷病手当金・出産手当金などの保障を受けられる
といったメリットもあります。
しかし、毎月のキャッシュフローに大きく影響するため、法人化を検討する際は保険料負担と節税効果を比較してシミュレーションすることが重要です。
フリーランスが法人化するメリット・デメリット一覧
観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
信用・取引 | 社会的信用が向上し、大手企業や金融機関との取引がしやすくなる | ― |
税金・節税効果 | 所得税と法人税を分離でき、役員報酬や退職金を経費計上することで節税が可能 | 赤字でも法人住民税(均等割)の支払いが必要 |
消費税 | 資本金1,000万円未満の法人は、最長2年間の消費税免除を受けられる | ― |
経費 | 経費計上の幅が広がり、事業に関連する支出を柔軟に損金算入できる | 設立費用や税理士顧問料など、固定コストが増える |
リスク管理 | 責任が有限になり、個人の資産を守ることができる | ― |
決算・経営管理 | 決算期を自由に設定でき、事業サイクルに合わせた柔軟な経営が可能 | 経理・税務・社会保険などの手続きが複雑化する |
収入管理 | 役員報酬を設定し、将来的に退職金も支給可能 | 給与(役員報酬)を途中で自由に変更できない |
社会保険 | 厚生年金・健康保険に加入でき、将来の年金額や保障が充実する | 社会保険料の負担が大きく、キャッシュフローに影響 |
資金調達 | 法人名義での融資や補助金申請が可能になる | ― |
総合評価 | 信用・節税・リスク管理の面で事業拡大を後押しする仕組み | 費用・手続き・維持の負担を見越した経営判断が必要 |
フリーランスが法人化するタイミング
フリーランスがいつ法人化すべきかは、事業規模・売上・所得・将来の方向性によって異なります。
「法人化=節税」と考える人も多いですが、実際には社会的信用や資金調達のしやすさ、税金の仕組みなど、
複数の要素を総合的に判断することが重要です。
ここでは、フリーランスが法人化を検討すべき代表的な3つのタイミングを紹介します。
事業の拡大を検討しているとき
法人化を検討すべき最初のタイミングは、事業を拡大したいと考えているときです。
取引先の増加や新サービスの展開に伴い、設備投資や採用などで融資(資金調達)が必要になる場面も増えていくでしょう。
しかし、個人事業主のままでは社会的信用が低く、銀行や公的機関からの融資審査が通りにくい傾向があります。
一方で、法人化すると登記簿謄本や決算書といった客観的な信用情報を提示できるようになるため、
金融機関からの評価が高まり、融資を受けやすくなります。
また、法人化することで大手企業との取引や外部パートナーとの契約もスムーズになります。
「取引先からの信頼を得たい」「事業を次のステージに進めたい」と考えるタイミングが、
まさに法人化の第一の転機です。
売上高が1000万円を超えた時
次に検討すべきタイミングは、年間の売上高が1,000万円を超えたときです。
個人事業主は、売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者となります。
つまり、2年後から消費税の納税義務が発生します。
一方、法人を設立すると、設立初年度(原則1期目)は消費税が免除されます。
また、特定の条件を満たせば最長で2年間の免税が可能です。
個人事業主時代と合わせれば、最大で4年間消費税を支払わずに済むケースもあります。
これはキャッシュフロー面で非常に大きな差を生みます。
たとえば、年間売上が1,500万円・消費税率10%の場合、年間で約150万円の納税負担を回避できる計算になります。
売上が増加し、今後も安定的に事業を続ける見込みがあるなら、
このタイミングで法人化を検討することで、節税効果と資金余力の確保が期待できるでしょう。
課税所得が900万円を超えた時
3つ目のタイミングは、課税所得が900万円を超えたときです。
このラインを超えると、法人化によって税率を抑えられる可能性が高くなります。
個人事業主の場合、所得に応じて「5%〜45%」の累進課税制度が適用されます。
一方で、法人税は原則として「15%〜23.2%」の一定税率です。
つまり、所得が増えるほど税率が上がる個人課税と異なり、
法人化すれば高所得帯でも税負担を一定水準に抑えることができます。
具体例で見ると:
所得区分 | 個人事業主(所得税+住民税) | 法人(法人税+地方法人税など) |
|---|---|---|
〜900万円 | 約23% | 約23.2%(ほぼ同等) |
900万円〜 | 約33%〜45% | 約23.2%(固定) |
このように、課税所得が900万円を超えると、法人の方が税金面で有利になります。
ただし、一時的な売上増や単発の高収益で判断すると、翌年以降の所得減少で逆に負担が増えることもあるため、
安定した利益が見込める段階での法人化が望ましいです。
フリーランスが法人化する流れ【6ステップで解説】
フリーランス(個人事業主)が法人化する際には、
会社の設立登記から税務・社会保険の届出まで、複数の手続きを段階的に進める必要があります。
ここでは、法人設立までの流れを6つのステップに分けてわかりやすく解説します。
実際に法人化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
① 設立の手続きを行う
最初のステップは、会社を設立するための基本事項の決定と定款の作成です。
主な流れは以下の通りです。
- 会社名(商号)を決める
- 事業目的・所在地・資本金・決算期を決定
- 代表者を選任
- 定款(会社のルール)を作成
株式会社の場合、定款は公証役場での認証が必要です(手数料約5万円+印紙代4万円)。
合同会社の場合は認証不要ですが、いずれにせよ発起人が出資金を払い込み、口座に入金した証明書が必要です。
この段階で法人としての骨格が固まり、次の「登記申請」へ進みます。
② 設立登記の申請を行う
定款の認証と出資金の払い込みが終わったら、
本店所在地を管轄する法務局で設立登記の申請を行います。
申請時に必要な主な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 定款の写し
- 代表取締役の印鑑証明書
- 資本金の払い込み証明(通帳コピー)
また、登録免許税として出資金の0.7%(最低15万円)が必要です。
この手続きが完了すると、晴れて「法人」として登記が成立します。
登記完了後には、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)と会社印鑑証明書を取得しておきましょう。
これらは銀行口座開設や各種届出で必ず必要になります。
③ 法人口座を開設する
登記が完了したら、次に法人名義の銀行口座を開設します。
取引先からの入金や経費支出をすべて個人口座で行うのは、会計上も税務上も好ましくありません。
銀行によって必要書類や審査基準が異なりますが、一般的には以下の書類が求められます。
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 会社印鑑証明書
- 定款の写し
- 代表者の本人確認書類
- 事業内容が分かる資料(ホームページ・契約書など)
近年は、法人を悪用した不正送金対策のため、審査が厳しくなっています。
特に新設法人は審査に時間がかかるため、早めに申請するのがポイントです。
④ 役員報酬を設定する
法人口座ができたら、次に自分(代表者)の役員報酬を設定します。
役員報酬は、設立から3カ月以内に決定し、
原則として事業年度の途中では変更できません。
報酬額は、以下の点を考慮して決めることが重要です。
- 現実的な売上・利益の見込み
- 社会保険料の負担額
- 節税バランス(法人税・所得税の最適化)
役員報酬は会社の経費(損金)として計上できる一方で、
高く設定しすぎると社会保険料が大幅に増えるリスクがあります。
迷った場合は、税理士にシミュレーションを依頼するとよいでしょう。
⑤ 諸官庁への届出を行う
登記と報酬設定が終わったら、次は税務署や自治体などへの届出手続きです。
主な提出先と書類は以下の通りです。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所開設届出書 など | 設立から2〜3カ月以内 |
都道府県税事務所/市区町村役場 | 法人設立届出書 | 設立から2カ月以内 |
(個人事業主だった場合) | 個人事業の廃業届出書 | 事業廃止後1カ月以内 |
期限を過ぎると青色申告の適用を受けられないこともあるため、
設立後1〜2カ月以内にすべての書類をまとめて提出するのが理想です。
⑥ 年金・健康保険の手続きを行う
最後に、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きを行います。
法人は、従業員が1人でもいる場合は社会保険の加入が義務です。
代表者1人の法人であっても、原則として加入対象となります。
手続きは、会社所在地を管轄する年金事務所で行い、「新規適用届」「被保険者資格取得届」などを提出します。
社会保険料は会社と個人で折半しますが、実質的には全額を自分で負担する形になります。
負担は増えるものの、将来的な年金額の増加や医療保障の拡充というメリットもあります。
まとめ:法人化は“目的”ではなく“手段”として考える
フリーランスの法人化には、社会的信用の向上・節税効果・リスク分散・経営の自由度など、確かなメリットがあります。
一方で、社会保険料や設立費用の負担、事務作業の煩雑化、資金の自由度の低下といったデメリットも存在します。
つまり、法人化は「すれば得をする」という単純なものではなく、
事業規模・収益構造・将来の方向性によって“最適なタイミング”が変わる経営判断です。
ポイントは、
- 売上・所得・支出を数値化して「法人化後のキャッシュフロー」を試算すること
- 節税目的だけでなく、信用・拡張性・持続性といった中長期の観点から判断すること
- 専門家(税理士・社労士)と相談しながら、制度的なメリットを最大限活かすこと
です。
もしあなたが、
「事業を本格的に成長させたい」「取引先の信頼を得たい」「安定的に資産を積み上げたい」
と感じているなら、法人化はそのための有効なステップになるでしょう。
一方で、「まだ収益が不安定」「手続きやコストに時間を割けない」段階であれば、
焦らず個人事業主として基盤を固める選択も十分に合理的です。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。