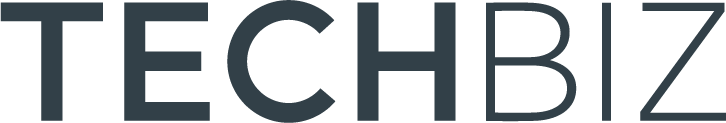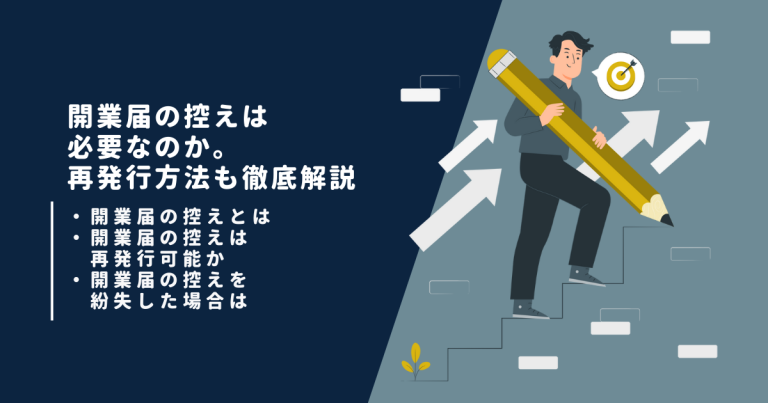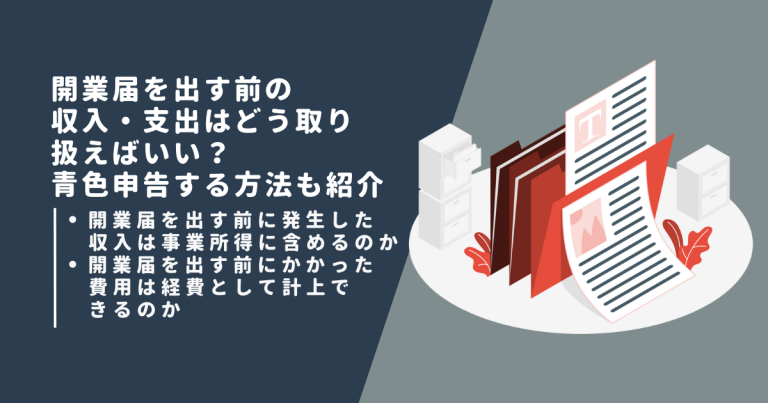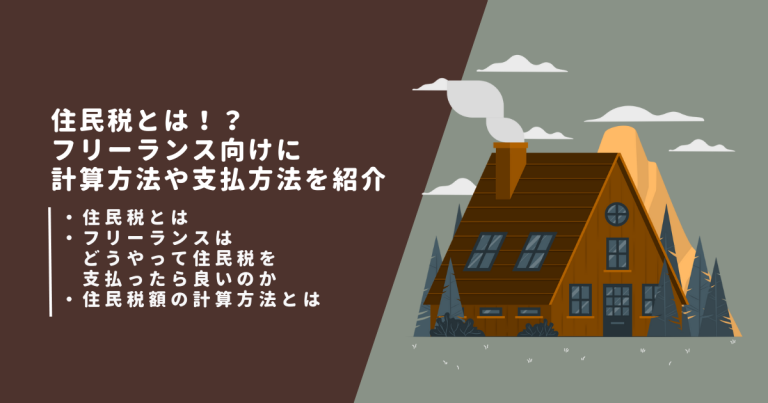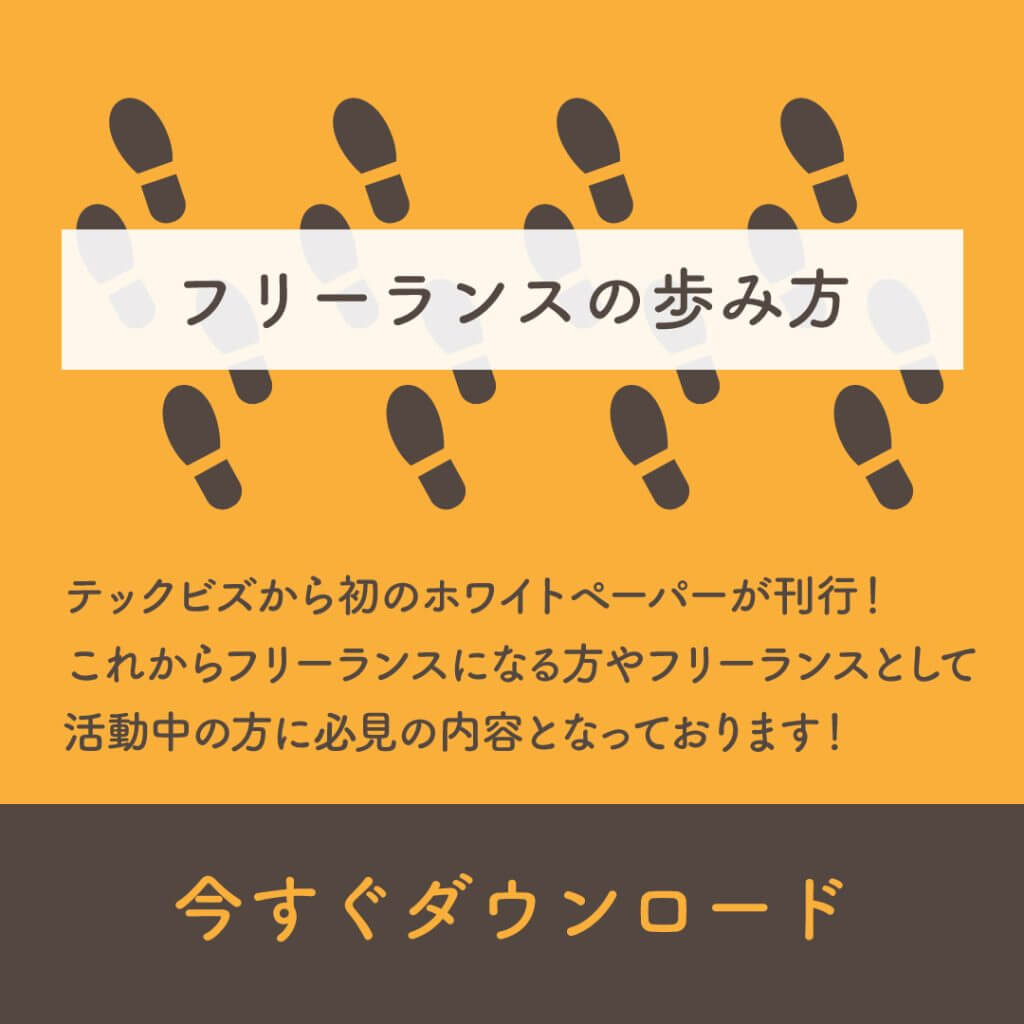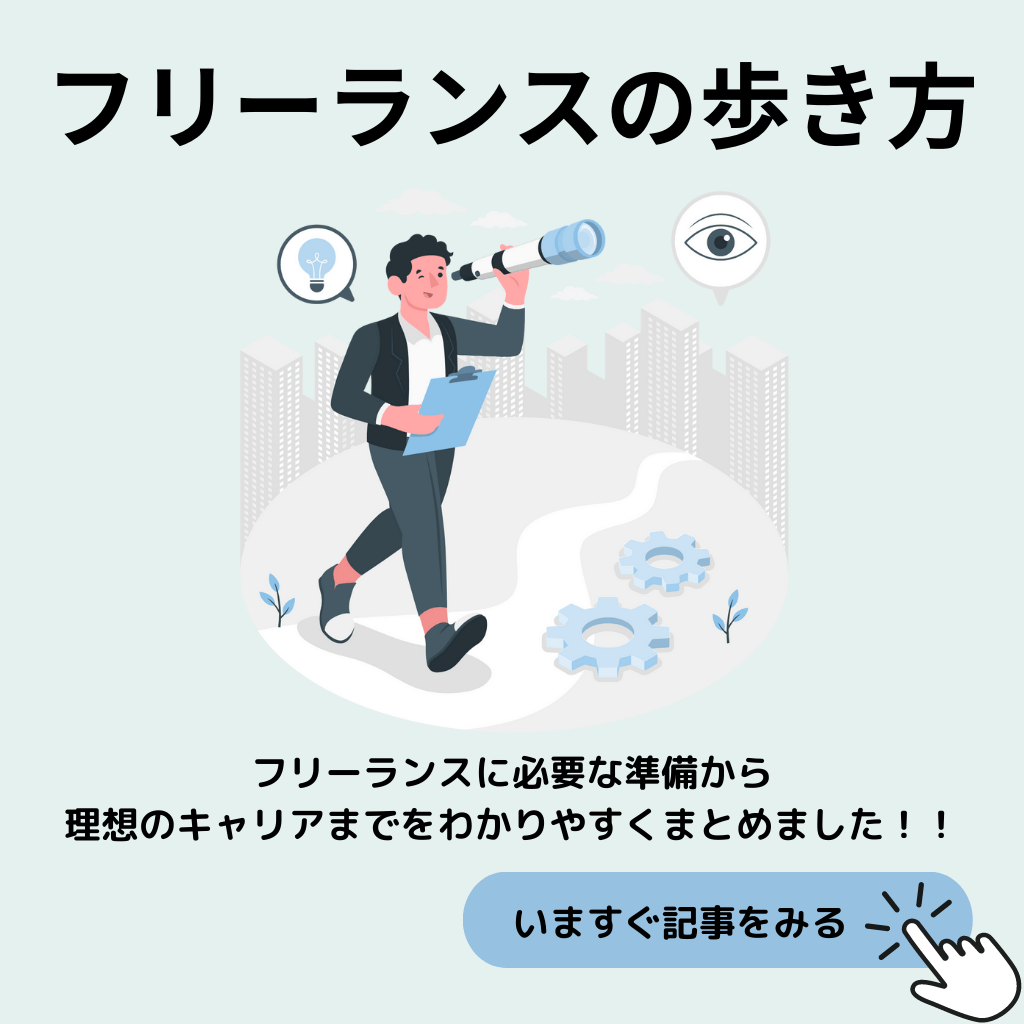・開業届の控えとは
・開業届の控えは再発行可能か
・開業届の控えを紛失した場合は
フリーランスの皆さんの中には、開業届の控えに関する上記の問いについて不明確な方もいらっしゃるかもしれません。その内容が何だったのかさえ、思い出せない方もいるかもしれませんね。
しかし、自立した後では、開業届の控えが必要となる状況も出てきます。そこで、今回は開業届の基本的な内容を再確認し、同時に開業届の控えの再発行方法についても見ていきましょう。
開業届とは何か?
開業届とは、事業を開始したことを公に宣言するために提出する書類で、これを税務署に提出します。この書類の正式な名称は「開業届」ではなく、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。必要な部分を記入して提出するのです。
ここで、記入する際に注意が必要なポイントについても見ていきましょう。
納税地
納税地は、住所地、居所地、または事業所等から選択しますが、基本的には住所地が選ばれます。しかし、特例として居所地や事業所等での納税が認められる場合もあります。
個人番号
個人番号とは、マイナンバーカードや通知カードに記載されている12桁の番号のことを指します。数年前から、この個人番号の記載が必須となりました。
職業・屋号
職業とは、どのような業務に従事しているかを指します。エンジニアやライターなど、さまざまな職業が存在します。記入した職業によって、経費として計上できる費用が変わることもあります。
また、複数の職業で事業を行っている場合は、主要な職業を記入してください(例:エンジニアなど)。
開業日
開業日とは、事業を開始した日を指します。つまり、開業届を提出した日とは異なる日付を記入することも可能です。ただし、事業を開始してから1ヶ月以内に提出するというルールがあるので、これは覚えておく必要があります。
事業の概要
あなたが行う事業の概要を詳細に記入します。例えば、エンジニアの場合、「プログラミングに関する業務、セキュリティサポート業務」などと記入します。自分が関与する可能性のある業務は、できるだけ全て記載することが推奨されます。
開業届を出さずに事業をしても問題ないがマイナスな面も
法律上は、開業届を提出せずに事業を行うことも許されています。しかし、開業届を提出した人と比べて不利益を被る可能性があります。例えば、確定申告において、青色申告が認められないといった事態があります。その結果、節税の効果が低下する可能性があります。
さらに、事業を継続している年数を証明しようと思っても、開業届を提出していないため、その年数を示す公的な書類が存在しません。
開業届の控えを保管しておくべき理由
開業届の控えを保管すべき理由は、以下の2点です。
開業した日を確認するため
取引先から開業日を尋ねられることがあります。その際、開業届の控えがあれば、正確な開業日を確認できるので、誤った情報を伝えることを避けることができます。
開業届の控えが必要になるかもしれない
書類を送付する際に、開業届の控えが必要となることもあります。取引先が事業を開始してからの年数が正確であるかを確認するために、開業届の控えを提出させる場合もあるため、これは保管しておくべきです。
開業届の控えが必要となる具体的な状況については、次の章で紹介します。
いつ開業届の控えが必要になるのか
ここでは開業届の控えが必要になる場面を、具体的に見てみましょう。
金融機関から融資を受ける時
金融機関から融資を受ける際には、開業届が必要となります。申し込み時に開業届の控えを提出を求める金融機関が大半で、これは事業を実際に行っているかを確認するために、多くの金融機関で義務付けられています。
税理士と顧問契約を結ぶ時
税理士と顧問契約を結ぶ際も、開業届の控えを提出する可能性が高いです。個人事業主の中には、経理業務を税理士に任せて、青色申告を依頼する方もいます。しかし、前述の通り、青色申告を行うためには、開業届を提出しておく必要があります。
もし開業届を提出していない状態で、税理士が代わりに青色申告を行った場合、税務署から連絡が来ることになります。さらに、確定申告書には作業を行った税理士の名前が記載されているため、税務署との信頼関係にも影響します。税理士が信用を損なわないためにも、顧問契約を結ぶ際に開業届の控えを提出するケースは多いと考えて良いでしょう。
法人(個人事業主)のクレジットカードを申し込む時
法人のクレジットカードを申し込む際も、開業届の控えを提示することが多いです。その理由は、カードの審査で事業の継続年数がチェックされるからです。一般的には、事業の継続年数が長いほど審査にプラスとなり、短いとマイナスとなります(ただし、カード会社によって審査条件は異なります)。
また、開業届の控えに記載されている事業の継続年数と、カードの申込書に記入した年数が一致しているかを確認する意味もあります。
小規模企業共済に加入する時
開業初年度に、小規模企業共済に加入する際も、開業届の控えが求められます。
通常、小規模企業共済に申し込む際は確定申告書の提出で問題ありません。しかし、開業初年度はまだ確定申告を行っていないため、確定申告書の控えが手元にありません。そのため、確定申告を提出していない状況で加入する際には、開業届の控えが必要となります。
QRコード決済を始める時
QRコード決済の導入を行う際も、開業届の控えが求められることがあります。物品の販売だけでなく、セミナーやイベントの参加料をQRコードで支払いたい方にとっても便利です。硬貨や紙幣のやり取りがないため、お金の管理が容易になります。
開業届の控えの特徴・受け取り方
開業届の控えは、開業届を提出した後に税務署の印鑑が押された状態で受け取ります。
ただし、開業届を提出した際に控えが不要と答えた場合は、控えは発行されません。つまり、事業を行っている全ての人が必ずしも開業届の控えを受け取っているわけではないのです。
開業届の控えを再発行手続きする方法
開業届の控えを紛失しても、再発行できます。ここでは再発行手続きの方法を、3つのステップに分けて見てみましょう。
1.保有個人情報開示請求書に記入する
保有個人情報開示請求書とは、自分の個人情報を確認したいときに提出する書類のことを指します。氏名や住所、連絡先の他に、開業届の写しを交付してほしい旨を記入します。本人が記入できない場合でも、法定代理人が請求することも可能です。
国税庁:保有個人情報開示請求書
2.記入後、必要書類と手数料とともに提出する
保有個人情報開示請求書への記入が完了したら、身分証明書のコピーと手数料(1件あたり300円)を一緒に提出します(法定代理人の場合は提出する書類が異なります)。また、郵送の場合は住民票の写しも必要となります。
身分証明書として個人番号(マイナンバー)カードの写しを提出する場合は、表面のみを印刷します。さらに、住民票の写しを提出する際は、マイナンバー部分を黒塗りにすることを忘れないでください。
3.2週間~1カ月程度で控えを受け取れる
提出後は、2週間~1カ月程度で控えを受け取れます。保有個人情報開示請求書を提出した当日には控えを受け取れないため、余裕を持って申請しましょう。
新しく開業届を出して控えをもらうのは止めた方が良い
開業届の控えを再発行せずに、新たに開業届を作成して控えを受け取る人もいますが、それは避けた方が良いでしょう。その理由は、税務署から疑念を持たれる可能性があるからです。
新たに開業届を提出した場合、「なぜ新たに開業届を出したのか?」と税務署から疑われる恐れがあります。その結果、税務調査が行われる可能性があります。税務調査では、最大で7年分の税務申告状況を調査します。中には、数千万円もの追徴金を命じられた人もいます。
税務調査の対象にならないためには、目立つ行動を避け、税務署から疑われないようにすることが重要です。
廃業後、再度事業を立ち上げる場合は大丈夫
個人事業主の中には一度廃業した後、再度事業を立ち上げる場合もあります。その際は、新たに開業届を出すことは問題ありません。
しかし、廃業した直後に開業届を出した人の中には、「計画倒産を行ったのではないか?」と税務署から疑われ、税務調査の対象になる人もいます。そのような状況にならないためにも、日ごろからルールを守り、確定申告を適切に行うことが重要です。
開業届の保存の仕方
開業届の保存が大事なことが分かったものの、保存をしても失くすのが心配な人もいるでしょう。
ここでは、開業届の保存の仕方を3つのポイントに分けて紹介します。
1.透明のクリアファイルに入れて保管しておく
透明のクリアファイルに入れておくと、外から見てどのような書類が入っているかが分かるため、紛失するリスクを減らし、開業届を探す時間も短縮できます。
開業届の控えをすぐに見つけたい場合は、クリアファイルに付箋を貼っておき、外から見てすぐに分かるようにするのも一つの方法です。大きな付箋を貼り、目立つようにしておけば、探す際に見つけやすくなるでしょう。
2.他の書類と同じクリアファイルに挟まない
他の書類と一緒にクリアファイルに挟まないことも、紛失を防ぐコツの一つです。他の書類が一緒に入っているクリアファイルに挟むと、探す際に手間がかかります。
もし、他の書類も同じファイルに入れたい場合は、アルバム式のファイルを使用すると良いでしょう。アルバムならば、書類を入れる場所を分けることができるので便利です。
また、端に穴が開いたクリアファイルをリング式のアルバムにとじて保管することも、紛失リスクを減らす方法の一つです。
3.確定申告関係の書類とまとめておく
確定申告関連の書類と一緒に保管することも重要です。用途ごとに書類を置く場所を決めておくと、開業届の控えがどこに保管されているかが分かりやすくなります。
具体的には、開業届と確定申告書、青色申告の承認依頼書の控えを一緒の場所に保管します。保管場所を決めておけば、開業届の控えを一時的に移動させたとしても、元の場所に戻すだけで、どこに置いたか分からなくなるリスクが低減します。
しかし、書類を保管する場所が限られていて、一箇所に多くの書類が集まり、取り出しにくくなる場合もあるでしょう。その際は、書類の整理整頓をこまめに行うことが重要です。不要な書類を捨てることで、保管する書類の量が減り、開業届の控えを見つけやすくなります。しかし、全てを捨てることができない場合もあります。
そのような場合は、以下の方法を活用すると良いでしょう。
PDF化する
PDF化して、コンピューター上で書類を保存する方法です。書類の中には、現物がなくても閲覧できれば問題ないものもあります。現物を保管する必要がない書類は、PDF化することで保管スペースが空き、便利です。自宅にスキャナーがない場合は、コピーサービスを提供している「キンコーズ」などを利用すると良いでしょう。
別の場所に保管する
どうしても現物で保管する必要がある書類は、別の場所に保管することも考えられます。保管先としては、以下の場所が考えられます。
実家
トランクボックス
専用の書類保管倉庫
段ボールに入れた書類を倉庫に保管してくれる業者も存在します。ただし、トランクボックスや業者の倉庫に保管する場合、毎月の保管料が発生します。そのため、コストを抑えたい人は、実家に預けるか、PDF化して保管する方法を選ぶと良いでしょう。
まとめ
今回は、開業届の控えを再発行する時の方法などを紹介しました。
まとめると、こちらになります。
✓開業届の控えを保管しておくべき理由
①開業した日を確認するため
②開業届の控えが必要になる可能性がある
✓開業届の控えを再発行手続きする方法
①保有個人情報開示請求書に記入する
②記入後、身分証明書の写しと手数料を提出する(郵送の場合は住民票の写しも提出)
③2週間~1カ月程度で控えを受け取れる
開業届の控えがないと、独立後に困る状況が生じることがあります。それが事業に悪影響を及ぼす可能性もあります。必要になったときにすぐに開業届の控えを見つけられるよう、日頃から見つけやすい場所に保管しておくことが重要です。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /