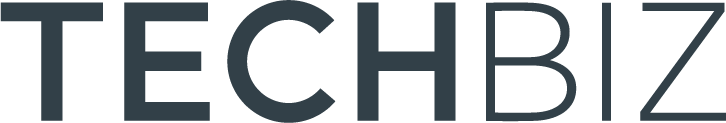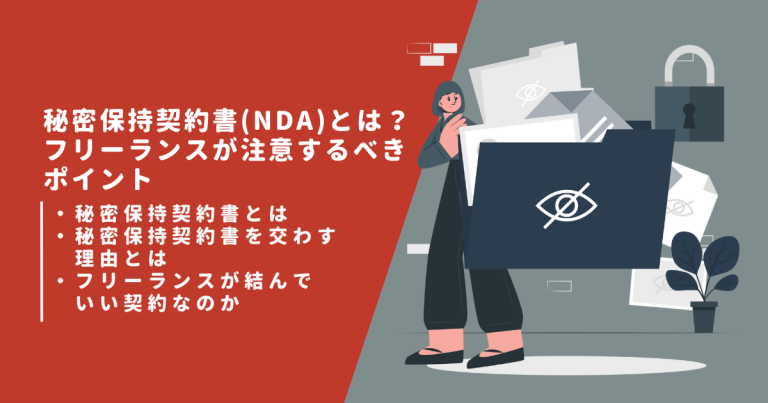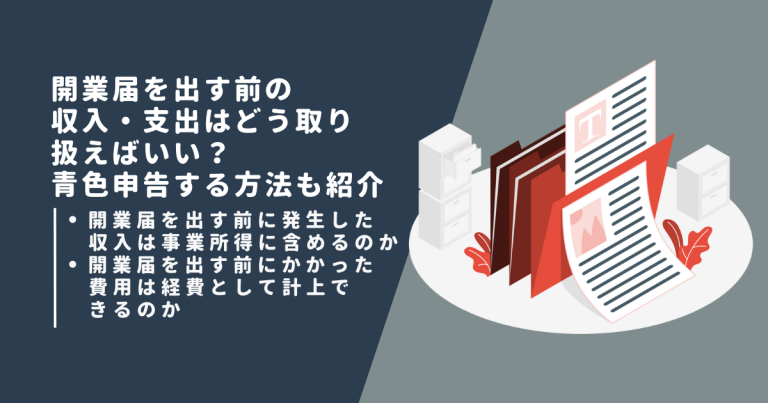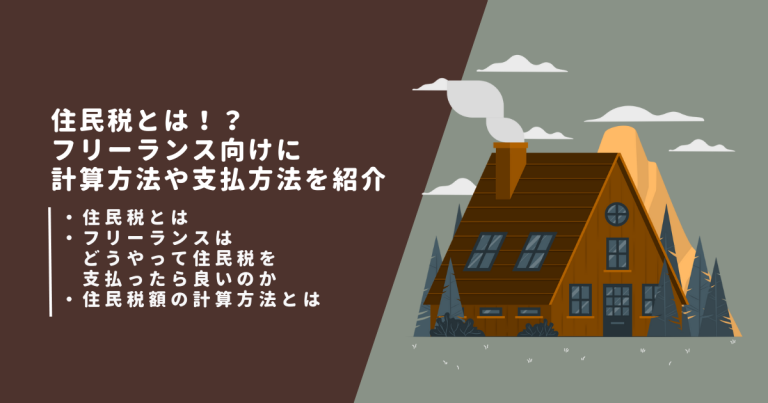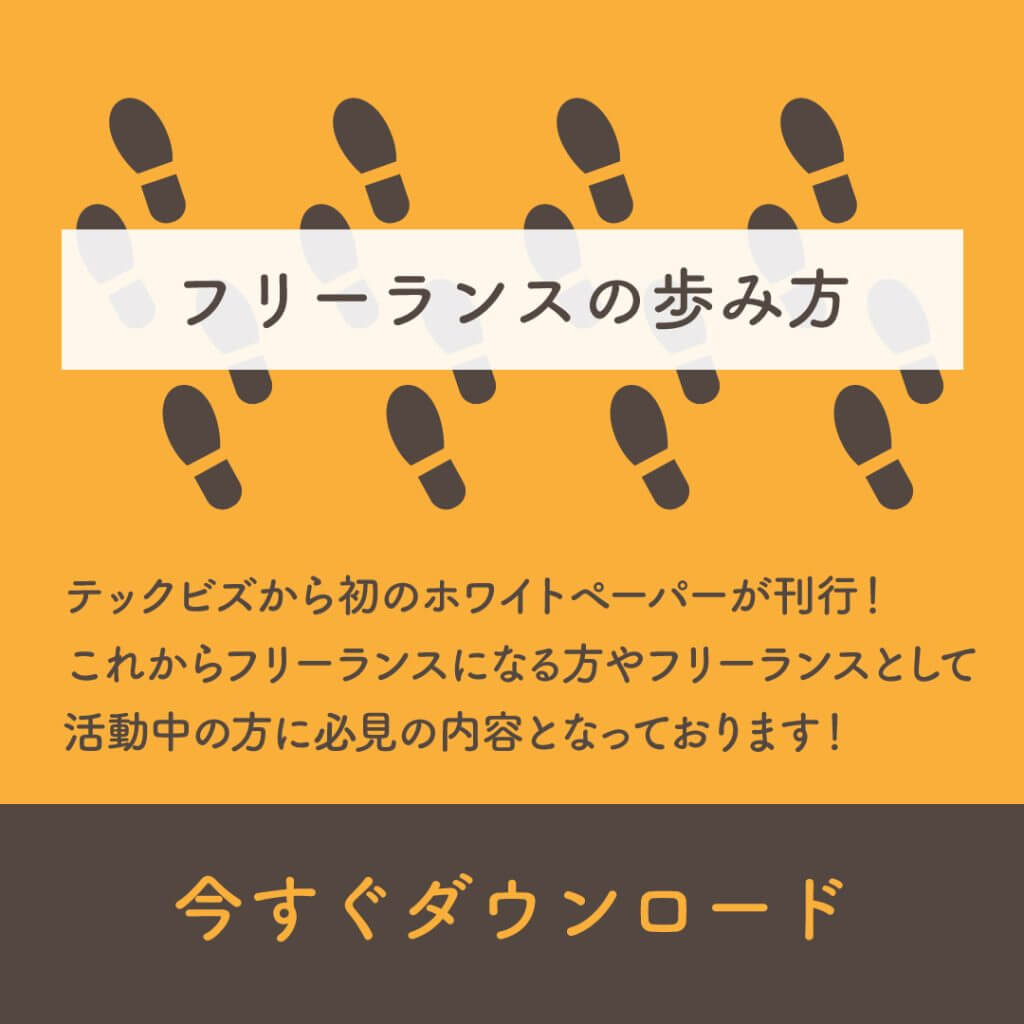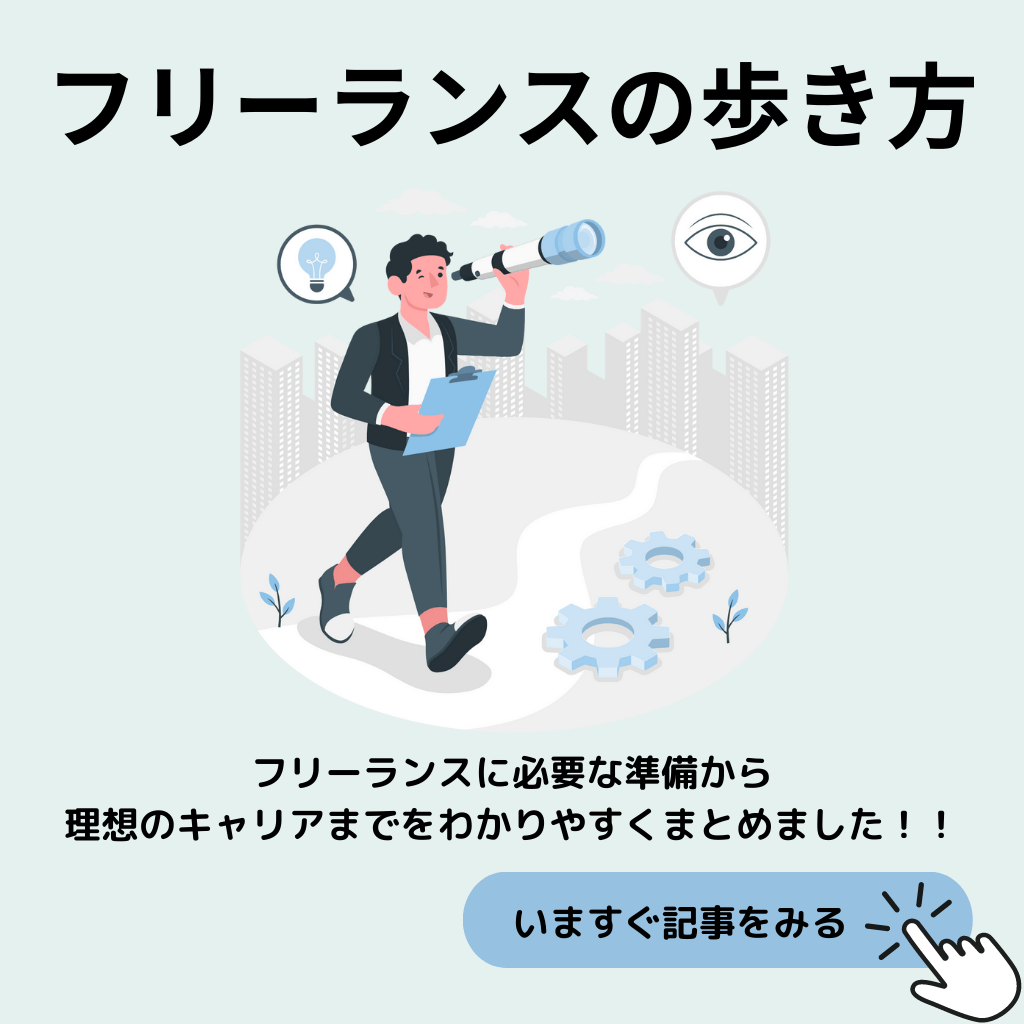・秘密保持契約書とは
・秘密保持契約書を交わす理由とは
・フリーランスが結んでいい契約なのか
「秘密保持契約書」、または「NDA」という名前で知られているものについて、皆さんはどれほど知っていますか?全てのクライアントがこれを用意しているわけではありませんが、ビジネス契約を結ぶ際にはしばしば交わされます。だからこそ、この契約について理解しておくことは重要です。ただし、考えずにこの契約を結んでしまうと、あなたのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
今回の記事では、秘密保持契約書の基本的な内容、交わす目的、そして契約を結ぶ際の注意点について詳しく見ていきましょう。
秘密保持契約書とは
「秘密保持契約書」は、クライアントがワーカーに提供する情報が外部に漏れたり、不適切に利用されることを防ぐための契約書です。クライアントがワーカーに業務を委託する際、自社の情報を共有しなければならない状況がしばしば生じます。例えば、「自社製品の開発」や「自社の業務進行方法」など、多種多様な情報が該当します。しかし、これらの情報の中には、他社に漏れると問題となるものも含まれています。企業情報が外部に漏れると、競合他社に市場を奪われるリスクや、自社の売上が減少する可能性があり、企業にとって大きな損失となります。
このようなリスクを防ぐために、「秘密保持契約書」が活用されます。もし受注側が企業の内部情報を漏らし、発注側に損害を与える場合、損害賠償請求や契約解除の対象となる可能性があります。そのため、秘密保持契約書を結んだ場合、情報の漏洩は厳禁です。
なお、フリーランスが秘密保持契約書を交わす際には、「業務委託契約書」の提出もしばしば必要となります。
秘密保持契約書を結ぶ時のチェックポイント
ここでは秘密保持契約書を結ぶ時のチェックポイントを3つ見てみましょう。
秘密保持の対象内容
「自社の製品やサービスに関する情報」など、秘密保持契約書には秘密として保持すべき内容が具体的に記載されています。これは、企業内部の情報の中でも、秘密保持の対象となる情報とそうでない情報が存在することを示しています。
しかし、秘密保持の対象外である情報であっても、その情報が漏れることでクライアントに迷惑をかける可能性があります。したがって、対象外の情報であっても、それが漏れないように注意することが重要です。
秘密保持の対象期間
秘密保持契約には、秘密情報を保持しなければならない期間が明記されています。例えば、「契約締結日から2年間」といった具体的な期間が設定されることが一般的です。この期間は「2、3年」程度に設定されることが多いとされています。この期間を遵守することは、秘密保持契約の重要な部分であり、違反すると法的な問題を引き起こす可能性があります。
秘密保持契約書を結んでトラブルになることもある
秘密保持契約書を結んで、フリーランスがトラブルに巻き込まれる場合もあります。
ここでは、どのようなトラブルに発展する恐れがあるか見てみましょう。
他のクライアントへ実績を紹介できない
フリーランスが新たな案件を探す際に、過去の実績を示すことは一般的な営業手法です。しかし、秘密保持契約書により保護されている情報については、自分が関与したプロジェクトであっても、許可なく外部に公開することは許されません。
秘密保持契約書は、基本的にクライアントの情報を漏らさないことを約束する契約です。クライアントによっては、関与したプロジェクトの存在自体を公にすることすら許可しない場合もあります。これが営業活動に制約をもたらし、新たな案件獲得の障害となることもあります。
賠償金を請求される可能性がある
外部に情報を漏らした結果、クライアントに多大な被害を与えてしまい損害賠償請求されるケースです。被害の規模によっては、何千万円・何億円単位の損害額を請求されます。
フリーランスの中には、損害賠償請求によって廃業に追い込まれる人がいます。したがって、業務上知り得た情報は喋らないようにしましょう。
秘密保持契約書を結ぶ際の注意点
秘密保持契約(NDA)を結ぶ際の注意点として、以下の要素が挙げられます。
- 秘密情報を明確にする:契約書で秘密情報を明確にすることは、秘密情報ではない商売や創作活動を自由に行うために重要です。
- 有効期間をケースに応じて決める: 契約の有効期間は、情報の性質や取引の内容によって適切に設定する必要があります。
- 損害賠償条項をつける:契約違反が発生した場合の損害賠償条項を設けることで、契約の遵守を確保します。
印紙の貼付は不要: 秘密保持契約書には収入印紙を貼付する必要はありません。
また、秘密保持契約を結ぶ際には、自身の事業に支障をきたさない内容であることを確認することが重要です。過去の成果物を実績として公表できない場合、自身の営業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、目先の利益だけでなく、1、2年先のことも考慮に入れて契約を結ぶことが推奨されます。
まとめ
秘密保持契約書について紹介しました。
まとめると、こちらです。
✓秘密保持契約書を結ぶ時のチェックポイント
①秘密保持の対象内容
②秘密保持の対象期間
✓秘密保持契約書を結んで起こる恐れがあるトラブル
①他のクライアントへ実績を紹介できなくなる
②賠償金の請求
秘密保持契約書はただ結べば良いわけではありません。秘密保持を契約した結果、事業に支障をきたす恐れがあるため慎重に契約を結んだ方が良いです。
経済産業省のホームページには、秘密保持契約書のひな型が載っています(参考:経済産業省)。内容が不安な人は、そちらの情報も参考にしながら契約を交わしてみてください。
※本記事の情報などは2020年9月現在の内容です。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /