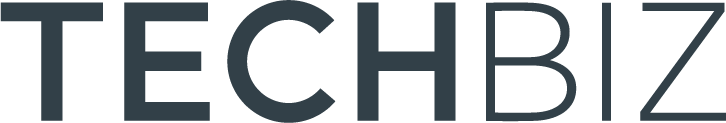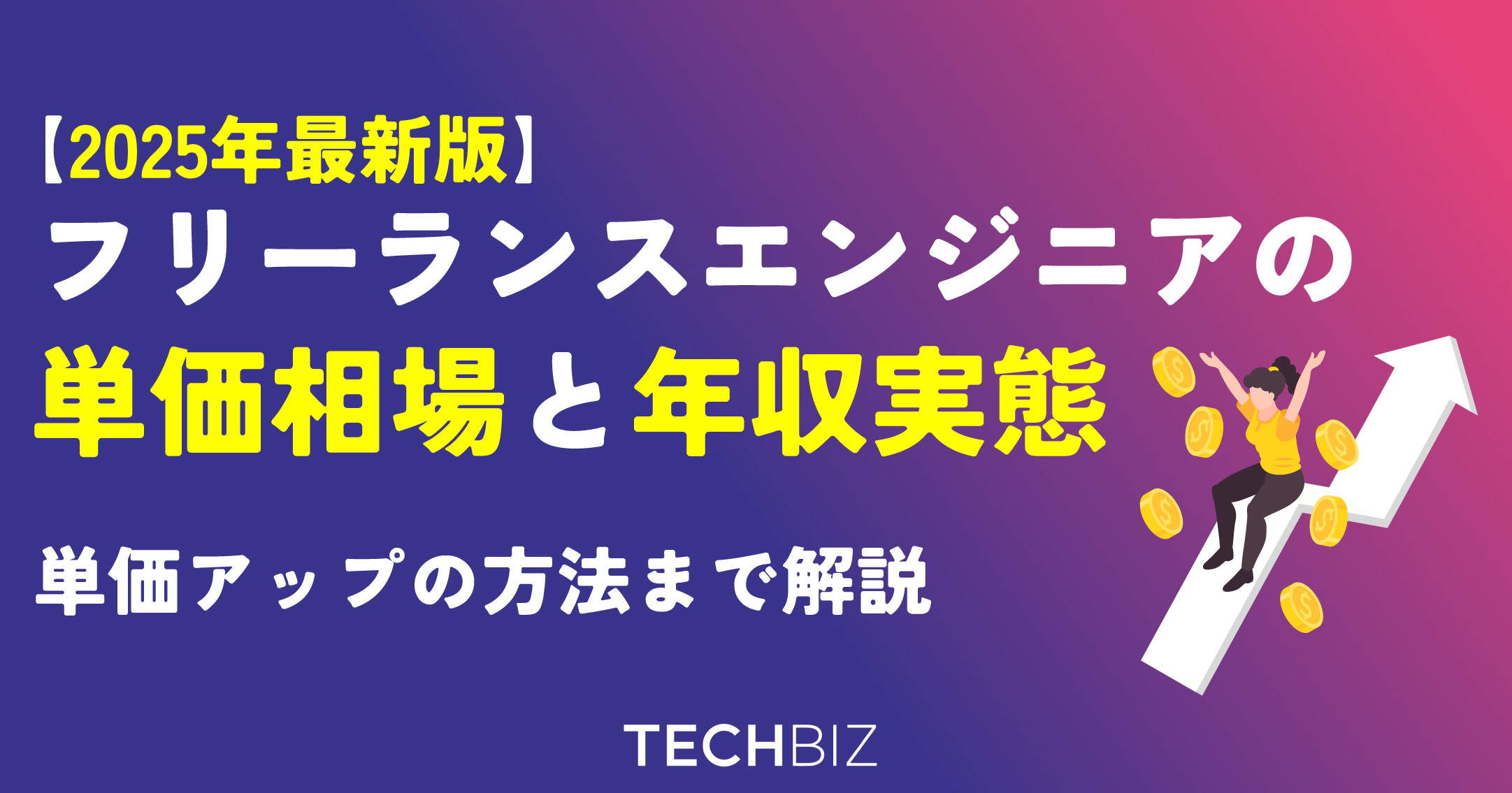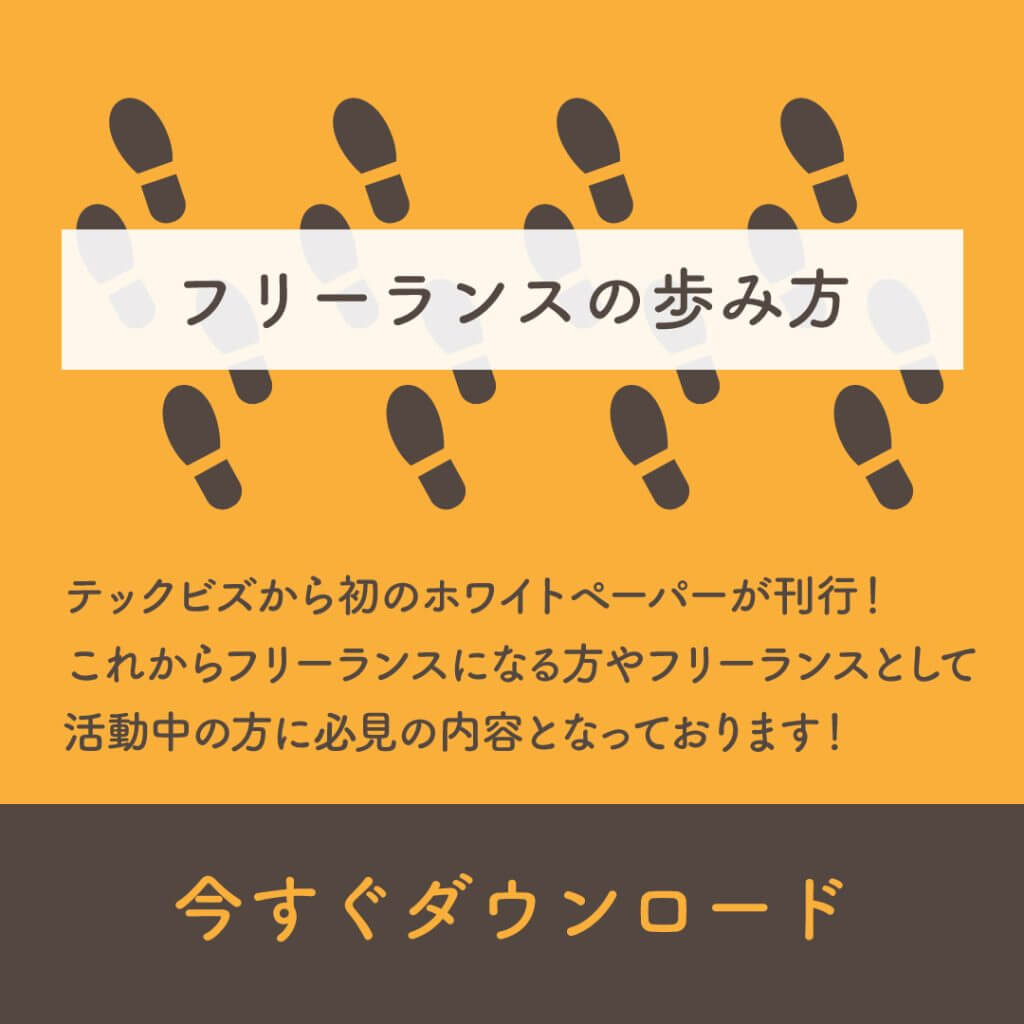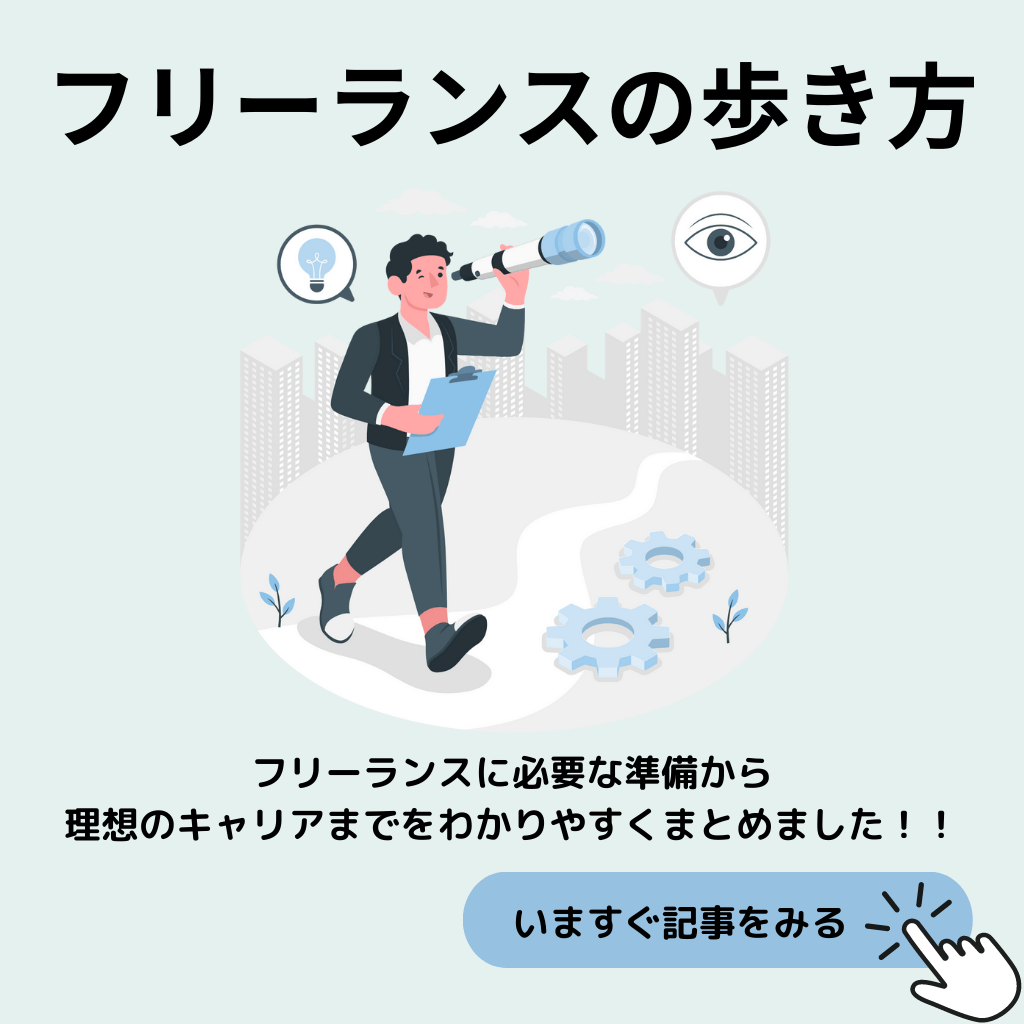「年収500万円って、実際どれくらい手元に残るの?」
「会社員と違って、フリーランスは税金も保険も自分で払うけど…結局“手取り”ってどのくらいなの?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
フリーランスは、売上=手取りではありません。所得税や住民税、国民健康保険、年金などを自分で負担し、さらに経費も考慮する必要があります。加えて、働き方や契約形態によっても実際の収入の感じ方は大きく変わります。
この記事では、年収別に「フリーランスの手取り額」がどの程度になるのかを具体的にシミュレーションしながら解説いたします。さらに、手取りを増やすための考え方や節税のヒントも紹介します。
これからフリーランスを目指す方も、すでに独立している方も、リアルなお金事情を知ることで、より現実的なキャリア設計ができるはずです。
そもそも「手取り」とは?フリーランスと会社員の違い
フリーランスと会社員の「年収=手取り」にならない理由
まず、「手取り」とは、税金や社会保険料などの支払いを差し引いた後、実際に自分の口座に残るお金を指します。
会社員の場合、月々の給与から「所得税」「住民税」「厚生年金保険料」「健康保険料」などが自動的に引かれており、受け取る金額はすでに“手取り”に近い状態です。さらに、年末調整などにより納税処理も会社側がサポートしてくれます。
一方、フリーランス(個人事業主)は、自分で収入と経費を管理し、確定申告で税金を計算・納付する必要があります。以下のような費用をすべて自己負担します:
- 所得税・住民税
- 国民健康保険
- 国民年金保険料
- 経費(業務に必要な支出)
つまり、「年収(売上)」が同じでも、手取り額はフリーランスの方が大きく差が出ます。
フリーランスの所得計算の基本(売上−経費=所得)
フリーランスの手取りを考える上で、まず押さえておくべきは所得の計算方法です。
所得 = 売上(収入)- 経費
この「所得」に対して、所得税・住民税・国民健康保険・国民年金が課されます。これらを支払った後に手元に残る金額が、「手取り」となります。
なお、売上から必要経費をしっかりと計上することで課税対象が減り、節税につながるという特徴もあります。
つまり、フリーランスにとって「手取り」を増やすには、正しい経費管理と節税の知識がとても重要になります。
フリーランスの手取りをシミュレーションしてみよう
年収ごとのざっくり手取り目安(300万/500万/700万)
フリーランスとして働く際、「実際にどれくらいの金額が手元に残るのか?」は非常に気になるポイントです。
以下は、年収=売上のケースで、必要経費を収入の30%、各種税金・保険を一般的な条件で試算したざっくりとした手取り目安です。
年収(売上) | 経費(30%想定) | 所得 | 税金・保険 | 手取り目安 |
|---|---|---|---|---|
300万円 | 90万円 | 210万円 | 約65万円 | 約135万円 |
500万円 | 150万円 | 350万円 | 約110万円 | 約240万円 |
700万円 | 210万円 | 490万円 | 約160万円 | 約330万円 |
※上記は以下を元にした簡易シミュレーションです
- 所得税・住民税・国民健康保険・国民年金を考慮
- 青色申告特別控除(65万円)を適用
- 扶養なし・独身のモデルケース
実際の金額は、家族構成・居住地域・扶養の有無や、経費割合・控除の種類によって大きく変わりますので、あくまで参考値としてご覧ください。
手取りを増やすには?節税・経費活用のコツ
フリーランスとして収入を最大化するには、売上を増やすだけでなく「いかに手元に残すか」=節税・経費管理が極めて重要です。適切な知識と工夫で、同じ年収でも手取り額に大きな差が出ることもあります。以下に、実践すべき節税&経費活用のポイントを詳しく紹介します。
- 青色申告を活用する
- 正式に開業届を提出し、青色申告を選択すると最大65万円の特別控除が受けられます。
- さらに、家族への給与(専従者給与)も事業経費として計上可能になり、課税対象所得の圧縮に効果的。
- 万が一赤字になっても、最大3年間の繰越控除が使えるため、翌年以降の節税に役立ちます。
ポイント:会計ソフト(freee/マネーフォワードなど)を使えば、青色申告も手軽に対応可能です。
- 経費を正しく・戦略的に計上する
- 事業に関係する支出(パソコン・スマホ・通信費・家賃の一部など)は、すべて「経費」として計上可能。
- 曖昧な支出も「プライベート」との按分を工夫することで、経費対象になりうるケースが多いです。
- 経費の記録・分類を日頃から徹底しておくと、申告時の作業効率が格段に上がります。
例:自宅兼事務所なら、家賃や光熱費の一部を「家事按分」で経費にできる
- 所得控除制度をフル活用する
- 社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除・小規模企業共済・iDeCo・ふるさと納税など、控除枠をフル活用することで所得税・住民税の負担を圧縮可能です。
- 特に小規模企業共済は、退職金のような役割も果たしつつ、年間最大84万円まで全額控除できる有力な制度。
ポイント:早めに仕組みを知って準備することで、年間数十万円の節税効果につながる場合もあります。
- 扶養控除・配偶者控除を意識する
- 配偶者・子ども・親を扶養に入れられるケースでは、扶養控除/配偶者控除が適用でき、年間数万〜十数万円の税軽減になることも。
- 自分が扶養に入れない代わりに、家族の扶養設定を工夫することで、世帯全体の可処分所得を最適化できます。
扶養の考え方は年齢・収入・同居条件などに左右されるため、ケースバイケースでの判断が重要です。
フリーランスは「自由で稼げる」反面、税金や社会保険を自ら設計・管理する責任があります。
しかし見方を変えれば、それは「仕組みを理解すればコントロール可能」ということです。
- 節税対策を知っているかどうかで、年100万円単位の差が出ることも
- 月々の経費と税金を意識するだけで、実質的な手取りが大きく変わる
- 売上と同じくらい「支出の設計」が重要
「もっと手取りを増やしたいけど、具体的に何から始めたらいいかわからない…」という方は、税理士やフリーランス向けのエージェントに相談してみるのも有効な選択肢です。
節税や契約のアドバイスも含めて、専門家のサポートを受けることで、収入の最大化と安心感の両立が実現できます。
テックビズでは、フリーランス向けに特化した専属の税理士が在籍しており、確定申告や経費計上、節税対策なども一貫してサポートしています。
「確定申告に毎年悩んでいる…」
「節税って何をすればいいの?」
「本業に集中したいから、税務はプロに任せたい」
そんな方は、ぜひ一度テックビズにご相談ください。
収入アップだけでなく、“手元に残るお金を増やす”サポートも充実しています。
フリーランスの「手取り」に関するよくある質問
年収が同じでも、会社員よりフリーランスは手取りが少ないの?
一見すると、同じ年収でも会社員のほうが手取りは多く見えるケースが多いのは事実です。
その理由として、以下のような制度上の違いが挙げられます。
比較項目 | 会社員 | フリーランス |
|---|---|---|
社会保険 | 会社が一部負担(厚生年金・健康保険) | 全額自己負担(国民年金・国保) |
税金 | 源泉徴収・年末調整あり | 自分で確定申告 |
福利厚生 | 有給・育休・退職金などあり | 基本的になし(自分で準備) |
こうした背景から、単純に「年収が同じ=手取りも同じ」にはなりません。
ですが、フリーランスは“すべて自己負担”である分、「すべて自分で設計できる」という自由さも持ち合わせています。
たとえばフリーランスなら
- 経費計上できる支出が増える(仕事に関する支出を税金上差し引ける)
- 住む場所・働く時間・仕事の量を自分で決められる
- 控除・節税・共済など、手取りを増やす選択肢を自分で設計可能
つまり、会社員と違って「制度に守られる安心感」は薄れる一方で、「自由と裁量の幅」が大きくなるのがフリーランスの特徴です。
「損か得か」ではなく、自分に合った働き方かどうかという視点で判断するとよいでしょう。
フリーランスの手取りはどこまで自分でコントロールできる?
フリーランスの手取りは、ある意味「会社員よりもコントロールしやすい」とも言えます。自分の働き方次第で、以下のように可処分所得に影響を与えられます。
- 収入を増やす:高単価案件に参画/スキルアップで単価交渉/副業・複数案件で稼働増など
- 経費を活用する:業務に関連する出費をしっかり記帳・計上(通信費、ツール、勉強代など)
- 節税を意識する:青色申告、控除、扶養、ふるさと納税、小規模企業共済などを活用
- 固定費を抑える:生活コストや設備投資などの見直しで支出を管理
特に「所得=売上−経費」なので、経費管理と節税対策は大きな影響力を持ちます。
毎月の手取りはどうやって管理すればいい?
フリーランスは「毎月の手取りが一定ではない」ため、収入の波が大きな不安要素になります。安定した生活のためには、月単位でのキャッシュフロー管理が不可欠です。
- 月ごとの「実質手取り額」を算出する
- 売上 − 経費 − 予定納税分 − 社保・年金 = 可処分所得
- 定額の生活費を設定する
- 固定支出(家賃、通信費など)+変動費の上限を明確に
- 別口座で税金・保険をプールしておく
- 納税や国保支払いに備えた「税金用口座」管理が重要
- 家計簿アプリ・クラウド会計を活用
- Moneytree、マネーフォワードなどで一元管理が可能
「今月は黒字だ!」と思っていたら、翌月に税金で資金不足…という事態を防ぐためにも、可視化とルール化がカギです。
どのくらい稼げば生活できる?(手取り基準の生活目安)
「どのくらいの手取りがあれば生活できるか?」という問いには、正解は一つではありません。
生活費は居住地・ライフスタイル・扶養家族の有無などによって大きく異なるためです。
ただ、フリーランスとして独立を考える際には、自分が「最低限必要な手取り額」を把握しておくことがとても重要です。ここでは、ひとつの参考例として、以下のようなペルソナをもとにシミュレーションしてみましょう。
💡 例:都市部で一人暮らしをしている30代・独身フリーランス
費目 | 月額目安(円) | 備考 |
|---|---|---|
家賃 | 90,000 | 東京23区の1K〜1LDKを想定 |
食費 | 40,000 | 自炊+外食を適度に併用 |
光熱費・通信費 | 15,000 | 電気・水道・スマホ・Wi-Fi |
保険・年金 | 40,000 | 国保・国民年金(概算) |
日用品・交際費 | 20,000 | 交際費・雑費など含む |
趣味・娯楽 | 15,000 | サブスク・外出・自己投資 |
貯蓄・投資 | 30,000 | 将来や非常時に備えて |
合計 | 250,000 | 月々の最低手取り目安 |
- 年間必要な手取り額:約300万円
- 必要な年収(概算):約400〜420万円
※控除・税金・経費などを考慮
このように、「どれだけ使うか」を先に整理することで、逆算して必要な年収や案件単価の目安を把握できます。
もし家族がいる、地方在住、副業スタイルなど条件が違えば、必要額も変動します。
まずはご自身の生活イメージを具体化し、毎月どのくらいの手取りが必要かを明確にしておくと安心です。
「最低限の生活費は分かったけど、実際どれくらい稼げるのか不安…」
「自分のスキルで本当にやっていけるのかな?」
そんな不安を感じたときは、プロの視点からのアドバイスを受けてみるのもひとつの方法です。
テックビズでは、フリーランスエンジニア専門のキャリアコンサルタントが、あなたのスキルや希望に合わせて案件提案・収入設計・税務面の相談まで一貫してサポートしています。
一人で悩むより、まずは相談ベースで一歩踏み出してみませんか?
手取りをしっかり確保するために必要な視点
フリーランスとして安定的に生活を送るには、単に「たくさん稼ぐ」だけでなく、「効率よく手元に残す」視点が重要です。
ここでは、手取り額を安定的に確保するために押さえておきたい2つの観点をご紹介します。
継続収入・案件単価の見直し
フリーランスは案件ごとに収入が変動しやすいため、「安定した手取り」を実現するには以下のような収入の土台設計が重要になります。
◼︎継続案件の確保
- 月額契約、保守業務、継続開発案件など、“毎月の見通しが立つ”収入源を持つことが安定への第一歩です。
◼︎単価の適正化・見直し
- スキルや経験に見合った単価で受注できているか、**「値上げ交渉」や「高単価領域へのシフト」**も検討しましょう。
- 単価が安定しない短期案件ばかりだと、年収の振れ幅が大きくなります。
◼︎複数チャネルの構築
- クラウドソーシングに依存せず、直契約・エージェント経由・紹介など、複数の受注チャネルを持つことで、収入のリスク分散が可能になります。
税金対策と支出管理のバランス
「稼いだ分、税金で大きく持っていかれる」ことを防ぐためには、適切な支出管理と節税対策の両立が欠かせません。
◼︎節税の基本は「記録」と「選択」
- 青色申告の活用や経費計上の精度を高めることで、課税所得をコントロールできます。
- 小規模企業共済やiDeCoなど、節税と将来の備えを両立する制度の活用も有効です。
◼︎生活コストとのバランスを考える
- 固定費が高すぎると、売上が減った月に圧迫感が強くなります。
- 「最低限これだけあれば生活できる」というラインを把握しておくことで、案件の取捨選択も柔軟になります。
まとめ|フリーランスの手取りは「仕組み」と「設計」で大きく変わる
フリーランスの手取り額は、単に「いくら稼ぐか」では決まりません。
税金・保険・経費・生活コストなど、さまざまな要素を自分で設計していくことで、最終的な可処分所得が大きく変わります。
会社員と違い、フリーランスには収入や支出を自分でコントロールできる自由がある一方で、それをうまく活かすためには「知識」と「判断力」が不可欠です。
- 年収が同じでも、実質的な手取りは人によって大きく差がつく
- 節税や経費の活用、案件の選び方などが収入設計に直結する
- 継続収入や資金繰りも含めた「土台作り」が安定したフリーランス生活を支える
だからこそ、「なんとなくやってみる」から一歩進んで、「手取りを設計する」意識が重要になります。
不安な方は、専門家に相談してみるのもおすすめです。
特にフリーランス初心者の方や、これから開業を考えている方は、税金や契約、案件選びなどをサポートしてくれるエージェントに相談することで、より安心して一歩を踏み出せます。
「自分に合った働き方で、しっかり手取りも確保したい」
そんな方は、ぜひ一度【TECHBIZ】に無料相談してみてください。
\ 記事をシェアする /