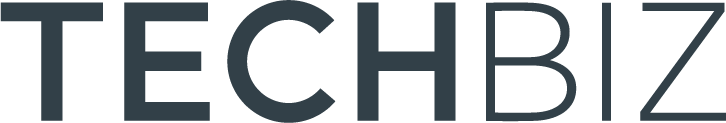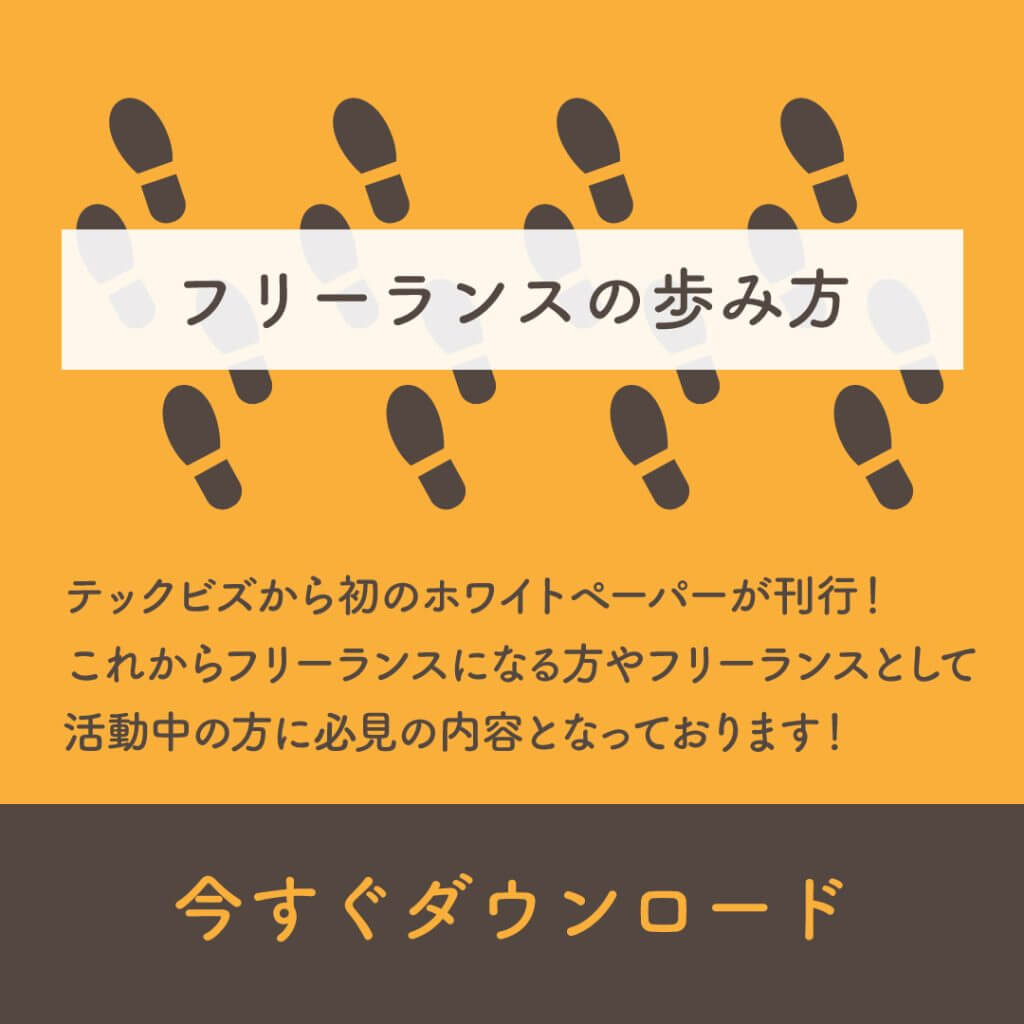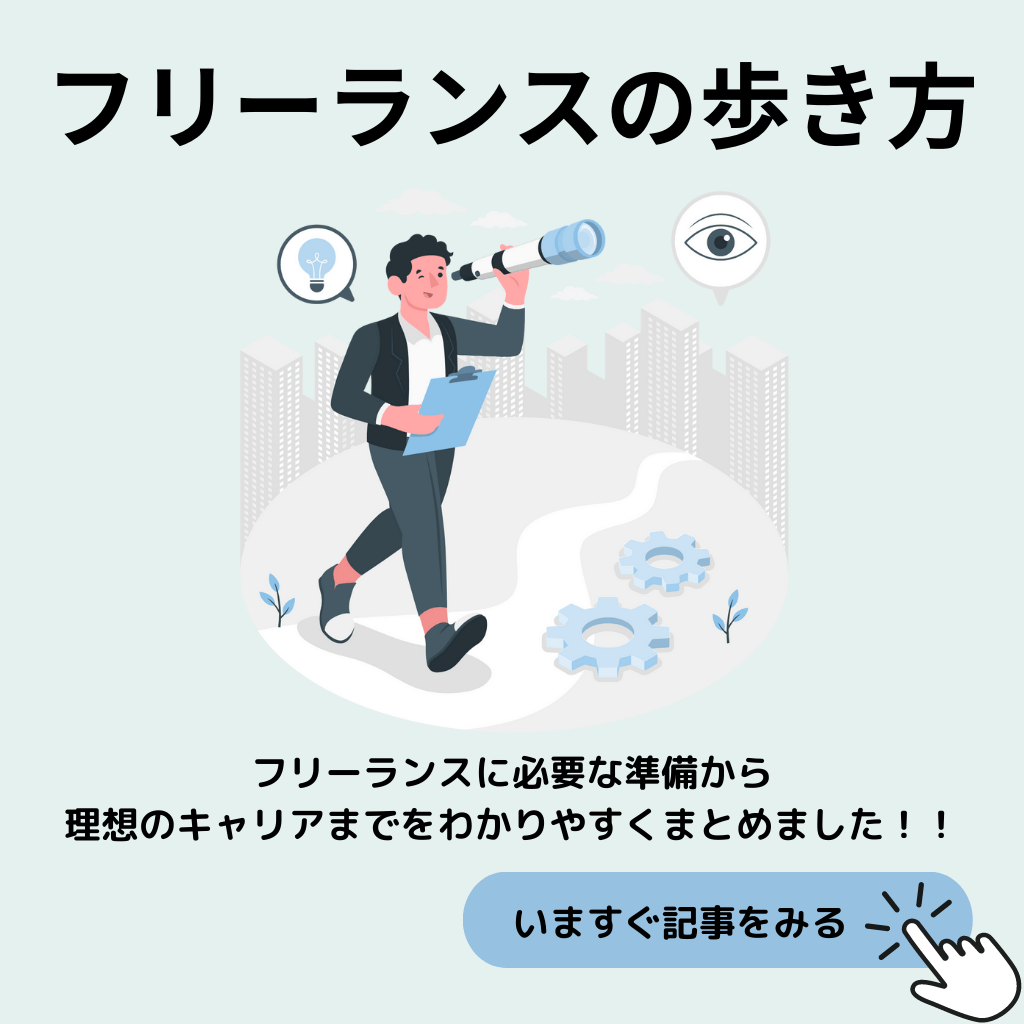仕事にも慣れてきたし、そろそろフリーランスという働き方を検討している方は多くいると思います。しかし、フリーランスにふみきれない理由の一つに現在の貯金額が関係していることでしょう。
フリーランスになったとしてもすぐに仕事を獲得できるとは限りませんし、不安に思うのは当然のことです。その不安を少しでも解消する、もしくは、案件を獲得できなかった期間のリスクヘッジとして貯金は重要になってきます。
そもそもフリーランスはに貯蓄は必要なのか、独立前にはどれくらい貯金があった方がいいのかみてゆきましょう。この記事はあなたの独立の後押しとなってくれるでしょう。
フリーランスが貯金をしておくべき理由
フリーランスの平均貯金額
フリーランスが貯金をする具体的な方法
フリーランスが貯金をしておくべき理由

フリーランスが貯蓄をしておくべき理由は複数あります。
さまざまな事態を想定し、いざというときにお金に困らないようにしましょう。
仕事が0になる恐れがある
正社員であればあまり心配することはありませんが、フリーランスはほとんどの場合契約期間があり、会社の経営が傾いてしまった場合や、あなたが思うようにパフォーマンスを発揮できなかった場合は契約が終了となる可能性があります。
そのような事態にならなければ良いのですが、もしも顧客に契約を終了されてしまった場合、別の案件を探さなければならず、案件を探している間は貯金に頼ることになるでしょう。
報酬が振り込まれない場合がある
フリーランスとして仕事を受ける際にはほとんどの場合、個社ごとに契約を結びます。その際、契約報酬の金額や振込期限などが明記されており、報酬が受け取れないケースはほとんど無いです。
しかし、会社が突然倒産してしまった場合、報酬の支払いがされない可能性も十分に考えられままた、外資系の企業に勤めており、送金が海外からの場合、報酬が銀行に振込まれるまでにタイムラグがあるなどのトラブルが考えられます。
会社員と比べて税金の支払割合が大きい
フリーランスは給与の中から自分で納税をする必要があり、会社員時代と比べて自らが払う税金を加味した上で貯蓄金額を考えなければなりません。フリーランスが納めるべき『所得税』『住民税』『個人事業税』『消費税』がどれぐらい収入から引かれるのかしっかりと理解した上で貯蓄の計画を立ててゆくと良いでしょう。
会社員時代と比べて税金を支払う金額は大きくなってくるのですが、しっかりと税金対策を行なった上で確定申告を行うことによって支払う税金の額額は大きく変わってきます。特に最近では、コロナの影響によって個人事業主の税金の減額や免除などの制度もありますので最寄りの税務署に問い合わせてみるのも一つの手段です。
傷病手当金がない
会社員には、加入する会社の健康保険から傷病手当金が給付されます。しかし、フリーランスが加入する国民健康保険には給付が無く、出産前後に仕事を休んだときに給付される出産手当金も受け取れません。そのため、万が一の事態にも備えられるよう、貯蓄はしっかりと行ってゆくべきです。
また、万が一の入院や働けなくなった時のために入院保険や医療保険に入っておくことも検討しましょう。現在の日本の医療制度では、保険に入っておくのは無駄だという考え方も一部ではありますが、フリーランスはライフプランや家族構成に応じて、ライフライフプランナーなど、お金の専門家にしっかりと相談しておくことも必要です。
退職金がない
全ての企業に当てはまるわけではないのですが、会社員は退職金が付与される場合が多いです。反対にフリーランスは退職金が付与されないため、老後の生活費のために計画的に貯金をしていく必要があります。
近年、日本では高齢化が進んでおり、年金の支給年齢が引き上げられるなどの対策が取られる可能性が高く、特にフリーランスの方は貯蓄をすることで老後に備えるべきです。
会社員と比べて年金受給額が低い
フリーランスは国民年金のみ加入することになります。通常の会社員が加入する厚生年金と比べ低い水準となっており、年金保険料を満額納付した場合でも年間で78万円程度、未納がある場合はさらに受給額は低くなります。
老後に受け取れる金額に不安がある方は保険会社が取り扱っている個人年金も検討してみると良いでしょう。ある一定の年齢になったら積み立ててきた金額が一気に受け取れたり、何回かに分けて受け取れるような仕組みになっています。
フリーランスは貯金できるのか?
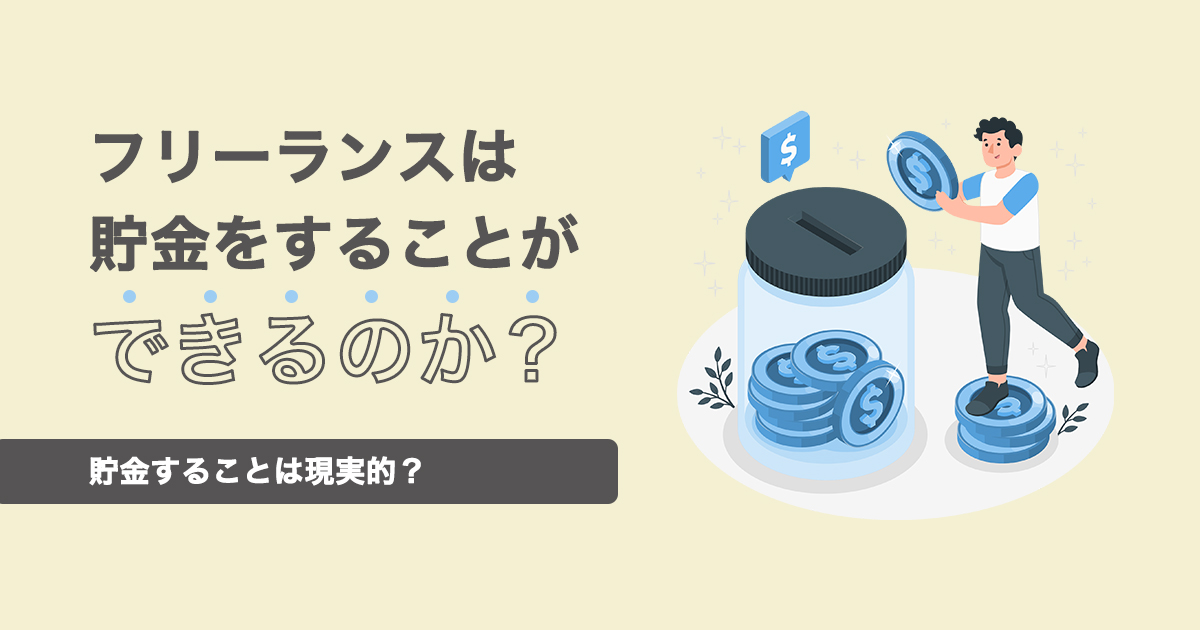
フリーランスが貯蓄できるかできないかは人それぞれになりますが、支出より多くの案件を受注することによって収入が支出を上回ることで貯金は容易になってきます。
自らの稼働時間をどれほど有効に使えるか、どれほど条件の良い案件を獲得してゆくか、などが重要となってきますので、案件を選ぶ際はすぐに飛びつかず、一度冷静になって考えてみることをおすすめします。
フリーランスの平均貯金額いくら?
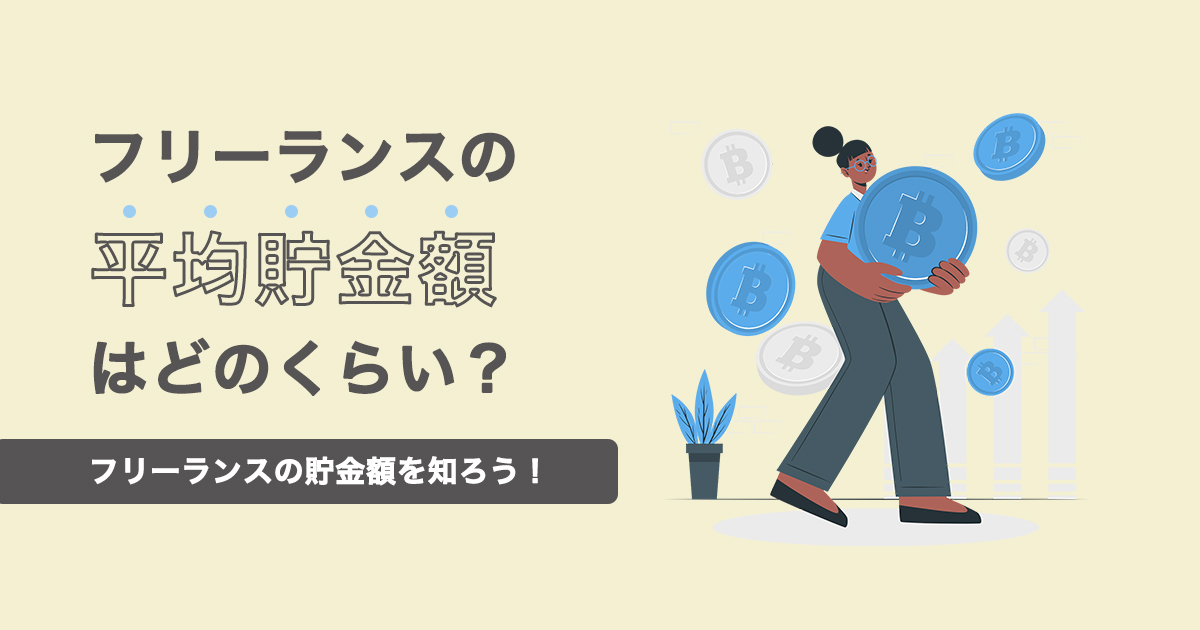
フリーランスの貯蓄額に関して一番多かった回答が「0円~10万未満」で約半数の貯金額が100万円未満という結果になりました。収入が不安定というイメージが強いフリーランスにとってこれは意外な結果となったかと思います。
フリーランスになるために必要な貯金額は?
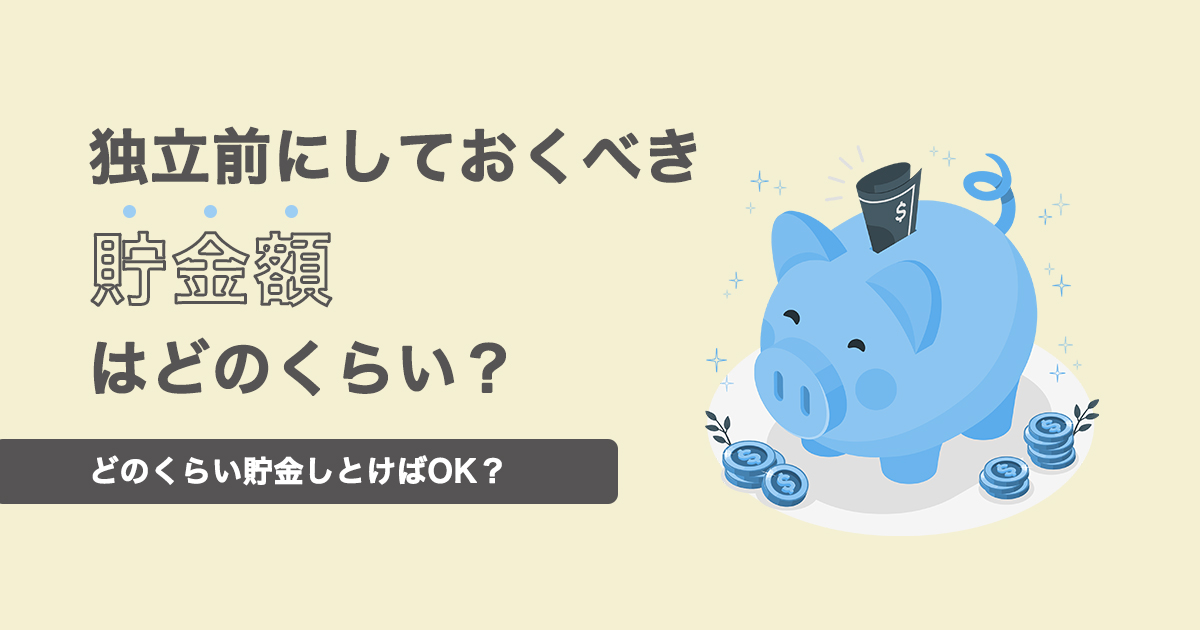
ここまででフリーランスになる前に自分の生活レベルに応じた貯蓄額が必要であることがわかったと思います。
では、フリーランスになる前の貯金とフリーランスになった後の貯金では差はあるのでしょうか。
独立前に必要な貯金額
独立前の貯金は最低限必要な生活費を1年分、可能であれば1.5年分の貯蓄があると良いでしょう。例として、都内在住の方であれば350万は生活費として必要かと思いますので、貯蓄も同様に350万、もしくは1.5倍の525万円程度を貯蓄し手からフリーランスに転職すると比較的、生活できないという状態にはなりにくいでしょう。
結婚や出産などのイベントが多くなってくると、貯蓄をすることは非常に難しくなってくると思います。しかし、残念なことにフリーランスが仕事を失った際に援助してくれる制度は少なく、多少無理をしてでも最低限の生活を確保しておくべきです。
独立後に必要な貯金額
独立後も貯蓄は必要です。確かに案件は継続的に取れて、フリーランスという働き方になれてきてしまうと無期雇用と同じく、定期的に給与が振りこまれる感覚に陥りがちです。
しかしながら『会社の経営が芳しくない』『体調を崩してしまい働けない』など自分の努力ではどうしようもできないわけで、急に収入がなくなってしまうことがないとは言い切れません。
フリーランスが貯金をする方法は?
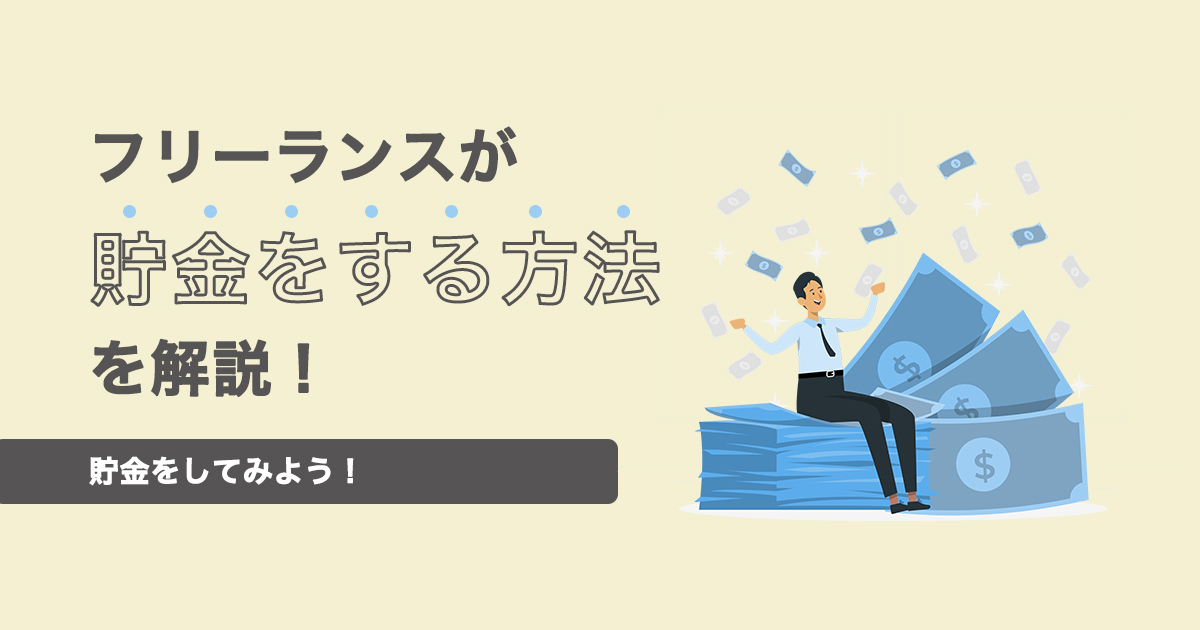
ここまででフリーランスの貯蓄の重要性はある程度理解いただけたかなと思います。
それでは具体的にフリーランスが貯蓄をするために有効な手段をご紹介いたします。
目標貯金額を決める
貯蓄金額の目標は必ず決めるようにしましょう。何事も目標が無いとゴールのないマラソンの様になってしまい、どこまで貯金すればいいのかわからず「貯金をしなければならない」という、精神的に辛い状態が続くと思われます。
目標設定をしたとしてもなかなか計画通りに貯金ができない方は、保険会社による個人金の積立も検討してみてください。毎月、給料から自動的に保険料が引かれるため、振り込まれた収入を全て使ってしまうという事態は比較的防げるはずです。
確かに60才~65才での払い戻しが主になってきますが、万が一の場合は自分が払い込んだ保険料の中から一時的にお金を借りることも可能な場合がほとんどです。
貯金額を控除した金額が収入だと考えて生活を送る
初歩的な貯蓄の方法にはなりますが、収入のうち毎月貯蓄に回す額を決めて残った金額を給料として考えると自然と貯蓄が楽になることでしょう。
ただし、これは実際に自分が使おうと思えば使えてしまうお金になりますので別口座に移すなど工夫が必要です。
貯金専用口座を作る
前述した通り、実際に収入が入金される講座と、貯蓄の口座をわけることによって貯蓄金額、もしくは生活費にあてられる金額を明確に管理することが可能です。
貯蓄口座の金額が大きくなるにつれて自分のモチベーションも上がり、より確実に目標の貯蓄が可能になることでしょう。
貯金額を定期的に確認する
貯蓄額の目標を具体的に決め、貯蓄用の銀行口座を持っていると明確に貯蓄金額が増えていることがわかり『あとどれくらいで目標貯蓄金額を達成できるか』また『日々の努力の積み重ねが目視できる』という点で貯蓄に関するモチベーションをあげてくれることでしょう。
最近では各銀行がインターネットを使用して入金や出金ができるように専用のアプリを用意しており、わざわざ銀行に行かなくても貯蓄口座へ入金できるので検討してみるのも良いかもしれません。
無駄遣いしている箇所を節約する
フリーランスは収入が増えるというイメージは必ずしも間違いではないのですが最初から数百万も年収が上がる人は少ないです。
フリーランスになって年収が上がったとしても最初は生活レベルを変えず、無駄な出費を抑えるよう意識しましょう。
一度上げてしまった生活レベルはなかなか落とすことが難しく、収入は増えているのに全く貯金が貯まらないというフリーランスの方も多くいらっしゃいます。
プライベート費用の削減
フリーランスになるということは正社員のようにきまった拘束時間がない場合が多く、その分プライベートの時間が増えることがほとんどです。
そのため、友人との交際費や取引先との接待費がかさんでしまうことが多くあります。心苦しくはありますが、本当にその費用はいま使うべきなか今一度考え直しプライベートでお付き合いをすべきなのか判断しましょう。
固定費の削減
毎年、もしくは毎月かかっている固定費を見直すことも貯蓄をする際には非常に重要です。例えば、自分の部屋を仕事場とする場合、社会人時代には家賃補助があったとしても、フリーランスになると会社に補助してもらっていた分を自分で払わなければなりません。
引っ越し費用との兼ね合いにもよりますが、あまりに自分の負担が増える場合は引っ越しを検討し、固定費を削減することも必要になってくるでしょう。
また最近では格安携帯が既存のキャリアと遜色なく使用できるようになってきました。月額にすると数千円、年間にすると数万円の経費節約になるので一度検討してみることをお勧めします。
変動費の調整
変動費は固定費とは違い、毎月かかってくる費用が変動するものを言います。
例えば、商品の原価や販売手数料、外注費や運送費などがイメージしやすいでしょう。変動費を安く抑えるコツは発注先への交渉や、発注先を変えてみるなどが効果的です。
ただし、あまりに強気な交渉は発注先があなたから離れていってしまう可能性があるため注意が必要です。
フリーランスが貯金をするなら節税も忘れずに!

フリーランスになりたての方が先輩方に良くアドバイスされることの一つに『節税』があるともいます。
フリーランスは会社員とは違い入金された収入の中から自分で納税をしなけれならず、特にはじめて確定申告をする人に取っては少々ハードルが高く感じるかもしれません。
節税についてメジャーなものを紹介いたします。
青色申告特別控除の利用
確定申告は大きく分けて白色申告と青色申告があり、白色申告は経理作業が申告に比べシンプルです。
しかしながら節税のメリットは少ないということがデメリットになります。
反対に青色申告は青色特別控除と呼ばれる控除があり、白色申告に比べると節税に向いていると言えます。ただし、準備するべき経理作業はより複雑となり、場合によっては税理士を雇わないといけなくなるため注意が必要です。
小規模企業共済等掛金控除の利用
意外と知られていない節税方法に「小規模企業共済等掛金控除」があげられます。
『小規模企業共済等掛金控除』とは、納税者が小規模企業共済法に定められた共済契約に基づく掛金等を支払うと、その支払った金額についての所得控除が受けられる仕組みです。最大84万円まで所得から控除できるため大きなメリットがあります。
生命保険料控除の利用
生命保険料控除はメジャーな節税方法の一つではないでしょうか。
生命保険料控除とは一年間に支払った保険料に応じた金額が所得から控除される制度です。『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』『個人年金保険料控除』などの区分に分かれており、ほとんどの保険に適応されます。
経費を増やす
事業を行っていくうえでかかった必要経費に関しては所得から控除することができます。
例えば、取引先との会食の費用、仕事場として利用したコワーキングスペース、業務中の移動で使用した電車賃やタクシー料金がそれにあたります。しかしながら業種や業態によって経費とできる金額が異なるため不安に思う方は税理士などの専門家に質問してみると良いでしょう。
ふるさと納税の利用
ふるさと納税は税金対策と勘違いされている方も多いようですが、厳密にはふるさと納税は税金対策ではありません。
ふるさと納税は2000円を超える寄付額に関して還付や控除を受けることができます。直接的に節税とはなりませんが、寄付先の自治体からその土地の名産品などを受け取ることができるためお得な制度であると言えます。
フリーランスとして独立するなら貯金とテックビズ!
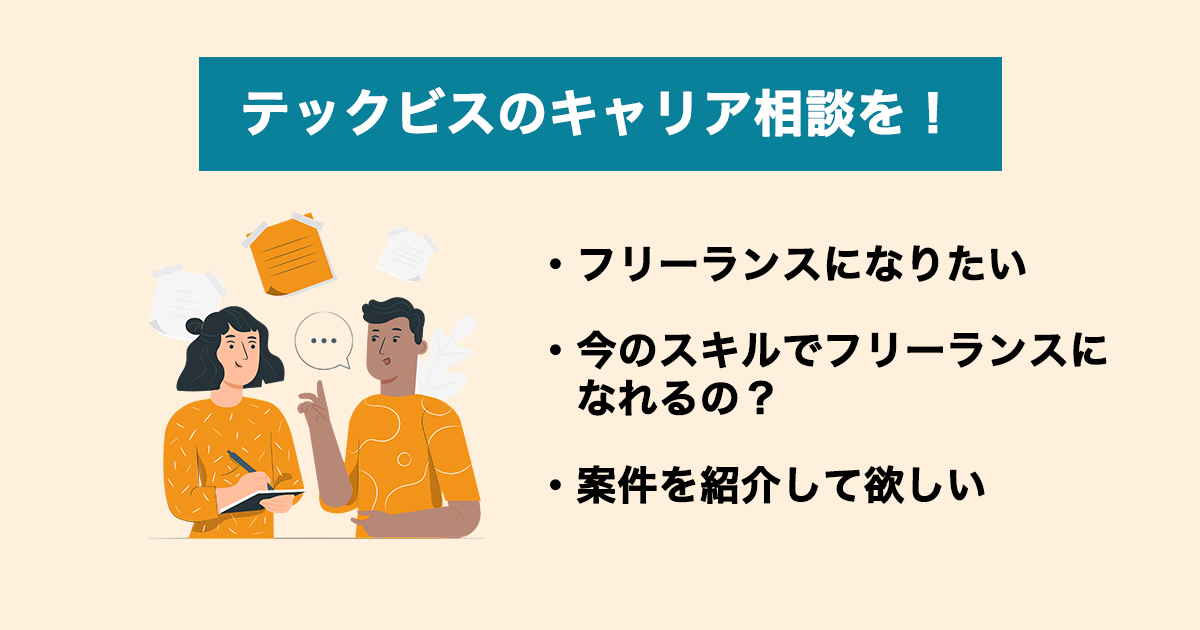
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。
\ 記事をシェアする /